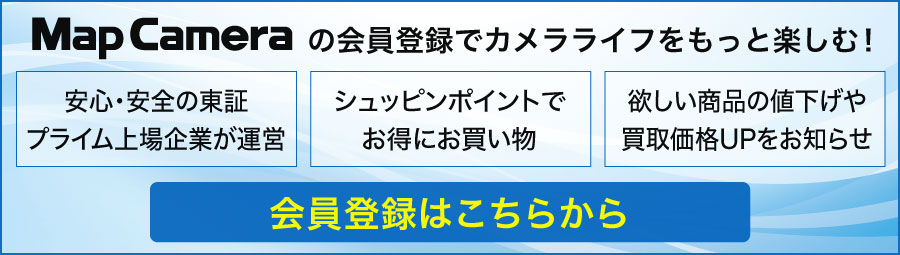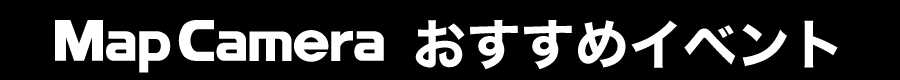絞り:F3.5 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:400 / 使用機材:LEICA M + Summicron 50mm/f2.0 3rd
絞り:F3.5 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:400 / 使用機材:LEICA M + Summicron 50mm/f2.0 3rd

ライカMマウント不動の標準レンズといえば、やはりSummicronを思い描く人は多い。
1939年に銘玉Summitar 50mm/F2.0を開発し、ライツ社のレンズ開発者として名高いMax Berek氏。その彼の最後の弟子、Walter Mandler氏が、師の創り上げたSummitarの接合面に改良を加えて1953年に世に送り出したのがSummicronである。
このSummicron 50mm第3世代は、コンピュータによる工学設計を取り入れて1979年から製造が開始された4群6枚のそれまでと異なる新設計で、ライカ・ニュージェネレーションの1本と呼ばれている。
 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M Monochrom + Summicron 50mm/f2.0 3rd
絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M Monochrom + Summicron 50mm/f2.0 3rd
さすがズミクロンと唸らせる描写だ。現行のボディの中でも突出した性能を誇るM-Monochromでも全く負けていないその描写力はライカレンズの底力を感じさせるものである。
 絞り:F3.5 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:800 / 使用機材:LEICA M + Summicron 50mm/f2.0 3rd
絞り:F3.5 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:800 / 使用機材:LEICA M + Summicron 50mm/f2.0 3rd
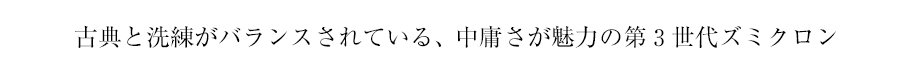
設計に無理もなく、安定して高い解像力を発揮する点や、先の世代よりも1割ほど軽量となった点。いろいろな観点からより一層Summicronの名に相応しいレンズとなっているように感じられる。
Elmarと双璧を成す、Leicaの代表的なレンズとして、初代空気レンズから続く伝統を守りながら、現行デジタル機で用いても遜色の無い高いポテンシャルを魅せてくれる。
 絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M + Summicron 50mm/f2.0 3rd
絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M + Summicron 50mm/f2.0 3rd
Leica M (Typ240)での1コマ。
この日は非常に寒く、レンズ前玉が曇ってしまった為、あたかもソフトフォーカスレンズのような描写になった。このレンズ本来の写りではないが、光の加減が気に入っている。
 絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1250秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M Monochrom + Summicron 50mm/f2.0 3rd
絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1250秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M Monochrom + Summicron 50mm/f2.0 3rd
 絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:1200 / 使用機材:LEICA M + Summicron 50mm/f2.0 3rd
絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:1200 / 使用機材:LEICA M + Summicron 50mm/f2.0 3rd
かなり暗いシーンでの1コマ。光量の少ない周辺部も潰れずに様相を呈してくれる。
ボディ側の性能もあるが、30年以上前に設計されたとは思えない解像力だ。
 絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M Monochrom + Summicron 50mm/f2.0 3rd
絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M Monochrom + Summicron 50mm/f2.0 3rd
M Monochromで撮影した開放での1コマ。高いコントラストと、立体感が情景を伝えてくれる。

50mmのSummicronはこの世代から先、レンズの基本構成を変更していない。次代の第4世代も、フードなど変更点はあるものの、同様に4群6枚の変形ガウスタイプを採用し、現在にまで至っている。
見方を変えれば、1970年代の後半に、既にLeicaは現代でも通用するだけのレンズを創り上げていた。とも言えないだろうか。
このレンズが誕生して35年、世相が目まぐるしく変わっていく中でも、変わらずにそこにあり続ける。言葉にするのは簡単だが、容易には真似の出来ない芸当だ。
Max Berek氏や、Walter Mandler氏が追求した拘りは、今も確かに、ライカユーザーの手の中に宿っている。
Photo by MAP CAMERA Staff