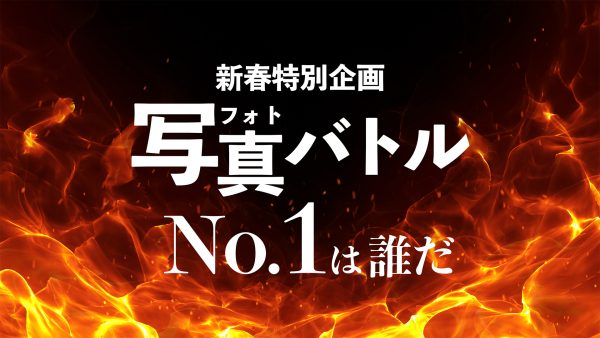【OM SYSTEM】明るく機動性があり近接性能も高い、マイクロフォーサーズ必携のズームレンズ
今から約11年前、OLYMPUSより登場したM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO。
35mm判換算で80-300mmの焦点距離をカバー、ズーム全域F2.8の明るさを持ち、さらにテレコンバーターの使用も可能という素晴らしい性能のレンズです。MC-14を装着すれば望遠側で換算約420mm相当に、MC-20を装着すれば約600mm相当になります。
つい最近にはOM SYSTEM よりM.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PROという更なる究極形というべきレンズが登場しましたが、価格の面で大きな乖離があります。今回はOM-1 II に M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO、さらにMC-14を装着して撮影に赴き、本レンズの魅力を改めて見つめ直してみました。
鉢植えでできた人型の置物を撮影。切り株に座り、丘の上から見下ろすような置物は道ゆく人や季節の移り変わりを眺めているのでしょうか。背景のボケから浮き上がるような描写は流石でポートレート撮影にもおすすめです。
ハーブ園では見頃を迎えたセージ。隣り合う鮮やかな色合いの花々を一緒に画角に入れてみ
このレンズはマクロ撮影も得意です。最短撮影距離70cm(レンズ先端で約50cm)から撮影で

もちろん超望遠ズームレンズとなれば野鳥も撮影できます。バラ園

バラ園の周囲は広い花壇があるのですが、春はチューリップ、秋はコスモスが植えられています。
この日はちょうどコスモスが見頃を迎えていました。
広角側少し絞ってみて全体を収め、望遠側絞り開放でその中の一輪にピントを合わせてみました。圧縮効果で実際には少し隙間がある花畑もそうは感じさせません。ボケもふんわりと柔らかく、ピントを合わせた花の部分はとてもシャープで解像度に定評があるレンズなのも頷ける描写です。

川沿いの道、鴨が泳ぎつつ羽繕いしつつといった風景を眺めながら歩いていたら川の中を歩くコサギと川岸の近くで佇むアオサギに続けて出会いました。コサギは足先だけ黄色かったり餌を探して歩く姿がユーモラスで好きな鳥の一種だったりします。
アオサギを撮影する際には、夏から秋に変わって少々川辺の景色の色味が寂しかったので黄色い花を思いきり前ボケとして取り入れてみました。青みがかったような灰色の羽が特徴的です。
小川の斜面では彼岸花が見頃を終えていました。
公園のお花情報によれば1、2週間前が見頃で白い彼岸花が先に咲き、その後赤い彼岸花が咲いていたようです。情報自体は目を通していましたがなかなか都合が合わず、訪れた時には見頃を終えていたのでした。
ただその中でも数株は咲いていてくれたので望遠レンズに感謝しつつ撮影。オシベが乱れているとなんだかクラゲのようにも見えます。
小川沿いを抜ければ大きな池があります。
夏の勢いを失った植物がまだ青々としていたので広角側で切り
真夏のゆだるような暑さに涼を添えてくれた大きな水車は、秋になったからか水量の問題か稼動しておらず、いつもなら水車からこぼれる水飛沫に隠れているコケや植物も簡単に撮影できました。
今回使用したOM-1 Mark II ボディと M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROの組み合わせなら、多少どころでない防塵防滴性能なので濡れても構わなかったのですが逆に少し残念でした。
たくさん実った柿が重そうな枝。野鳥に食べられそうなものですが、まだ食べごろではないのか渋いのでしょうか。水車に意外と近い場所に生えていることに初めて気付きました。いつもは稼動している水車に気を取られていたのかもしれません。
水車の付近のツリフネソウの花の周りを忙しなく飛んでいる虫がいると思ってレンズを向けてみると、11月頃まで姿を見せてくれるホシホウジャクがいました。じっとしていることがほぼなく、ずっと花から花へ飛びまわっているホシホウジャク、色味は蜂のようですが蛾の仲間だそうで、個人的にはかわいいと思います。
逆にこちらはじっと蜜を吸っているセセリの仲間。
これだけじっとしてくれているとこちらも露出やボケまで気を回せます。風に揺られている一瞬を明るい雰囲気で切り取ってみました。
ここまで早朝6時から出かけてだいたい2時間半ほど経過、疲れてくると足元に目を向けることが多くなり、ふと変わった模様の小さな花を見つけました。草丈は低く、ユリに似た形状で花は白地に紫の斑点模様、花の大きさは1-2cmほどと小さいためしゃがみ込みながら撮影。小さくふわふわしたつぼみも一緒に、ここまで大きく写し出せると楽しいものがあります。
ここまで撮影してきて本当にいろいろな撮影シーンで活躍してくれるレンズだと感じました。
登場から年月も経ち、中古の価格もこなれて手に届きやすくなっています。
特殊な機構を持つレンズフードは少々扱いに注意が必要ですが、いちいち取り外す必要なくカシュッとスライドさせてフードを伸ばしたり縮めたりできて、便利でもありなかなか楽しい機能です。
フォーカスリングを手前に引いて直感的にAF・MFを切り替えられる「MFクラッチ機構」、撮影スタイルに合った機能割付が可能なファンクション(L-Fn)ボタンの設置、レンズの全長が変化しないインナーズームの採用など、目立たないながら撮影者にとって嬉しい機能も搭載されています。幅広い撮影シーンで活躍してくれる、マイクロフォーサーズ必携のレンズの1本です。
マップカメラスタッフが語る「ニハチ」の魅力~F2.8編~OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F2.8 PRO