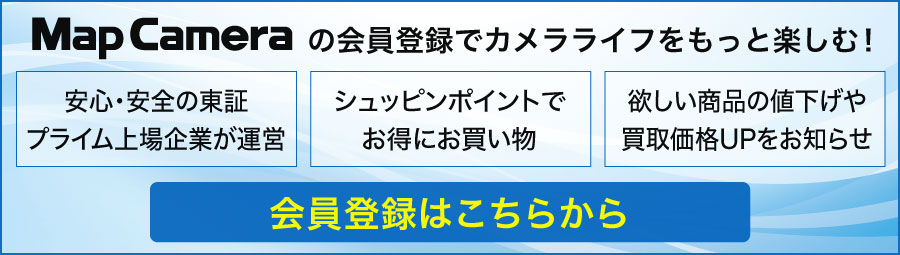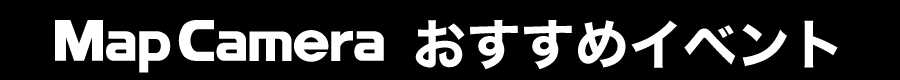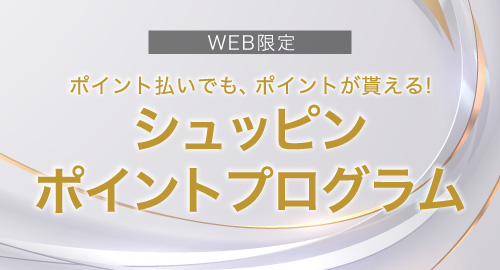【極私的カメラうんちく】第16回:一眼レフが見る夢
35mm判一眼レフが本格的に日本で作られ始めたのは第二次大戦の後である。しかし当時の一眼レフは小型精密カメラとして既に高い評価を得ていたレンジファインダー機と何かにつけ比較される運命にあった。
一眼レフはレンジファインダー機と比べて近接撮影時にパララックス(ファインダー像と撮影画像のズレ)が原理的に生じないことや、測距精度が焦点距離と撮影倍率に比例することが特長である。そのため接写や望遠撮影の分野では一眼レフの利用価値は早くから認められていた。
しかし当初の35mm判一眼レフは明快な二重像合致式のピント合わせのレンジファインダー機に比べると、暗く見づらいファインダーのためにピント精度が悪く、通常の撮影条件ではレンジファインダー機と比べて使い勝手の悪さばかりが目立っていた。
いわばカメラ先進国ドイツの技術をもって戦前から熟成されてきたレンジファインダー機に対して、新しい測距方式で挑戦した日本製の35mm判一眼レフだったが、皮肉にも新機構であるはずのファインダーの完成度の低さが決定的な弱点だったのである。
しかし35mm判一眼レフの将来性に賭けた日本のカメラメーカーはその後たゆまぬ改良を続け、ようやくその優れた特長を発揮出来る環境を手に入れた。緻密で明るいファインダー像を目指してマット面の粒状性を向上し、またファインダー光学系にコンデンサーレンズ(大きな凸レンズ)やフレネルレンズ(同心円状の傾斜溝)を刻むなどの様々な光学的な改良を施してきた。
そしてその後は原理的な特長を存分に発揮し、レンジファインダー機を遥かに上回る撮影領域を次々と手に入れてゆくことになる。
とは言ってもMF一眼レフのピント合わせにはレンジファインダー機に比べるとやはりそれなりのスキルが必要であり、特にマット面(スリガラス状の部分)でのピント合わせには依然として苦労するユーザーが多かった。そのためスプリットイメージやマイクロプリズムといった補助機能付きのスクリーンが標準装備として一般化する。
また70年代に広く一般化した多くのズームレンズは単焦点レンズに比べて開放F値がはるかに暗く、少しでも明るいフォーカシングスクリーンへの需要は依然続いていた。
スクリーンのマット面は微細な凹凸形状によってミラーからの光が拡散することにより映像として見ることが出来るが、より明るく見やすいマット面のためには均質で細密な凹凸形状が不可欠である。しかし一定の粒状度に達すると今度はマット面の明るさとピント位置の確認のしやすさが相反することが多くなり、各社この両立には苦心していた。明るすぎるファインダーは、使用するレンズによってはピント精度が落ちてしまうのである。そのためフィルムカメラ全盛の時代、スクリーン交換式のプロ用一眼レフには、使用する交換レンズの焦点距離や開放F値などの条件別に何種類ものスクリーンが発売されていたほどである。
ところが80年代後半から90年代にかけて、主にプロ用機種向けに、それまでのスクリーンに比べて格段に明るく、それでいてピント位置が格段に確認しやすい、非常に優秀なスクリーンが各社から続々と発売される。これらのスクリーンはマット面の凹凸を電子顕微鏡レベルの工作精度で均質で最適な形状にコントロールとすることにより、単に明るいだけではなくさらにピント位置が良く見える性能を同時に実現したのである。キヤノンのレーザーマットをはじめとし、オリンパスのファインルミマイクロマット、ペンタックスのナチュラルブライトマットなどがその例である。そして現在これらの技術はさらに改良され、もちろん現在のデジタル一眼レフにも存分に生かされている。
AF機でありながらもMF性能を重視するというのは、かつてはプロ用機だけの事情だった。アマチュア機ではファインダー性能を重視してもメーカーにとっての見返りが少なく、コストダウンのためにないがしろにされることが多かったのである。しかし現在のアマチュア用デジタル一眼レフにはハイエンド機と同じスクリーンが搭載されている。しかも好みに応じてファインダー倍率を向上するためのアクセサリーも安価で発売されており、明るい交換レンズを選べばさらに良質なファインダー像を、誰でも手軽に得ることができる時代になった。
AFカメラの登場から20年。市場成熟の成り行きといえばそこまでだが、理想的なフォーカシングスクリーンを搭載した一眼レフが50年後に登場するAF機だったというのは、暗いファインダーでピント合わせに苦しんだ黎明期の一眼レフからみればなんとも嫉ましい話しではある。