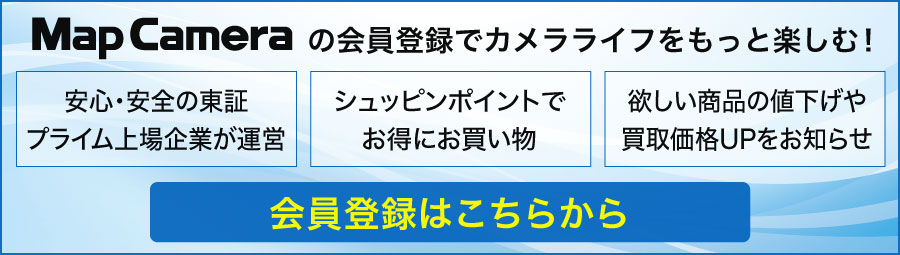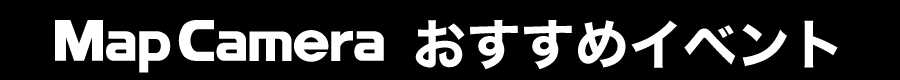【極私的カメラうんちく】第2回:ミドルフォーマット・ライカ
ミドルフォーマット・ライカという言葉をご存知だろうか。
直訳すると「中判ライカ」だが、実際にはそんなものは存在しない。ミドルフォーマット・ライカ(以下MFL)とは即ち「レンズ交換式距離計連動型中判カメラ」(長い!)を欧米のカメラファンが形や構造から比喩的に表現した言葉である。
具体的にいえばマミヤ6やマミヤ7あるいはブロニカRFのことになるが、言われてみればその外観はまさにM型ライカと相似形といってもよいほどよく似ている(巻き戻しクランクこそ無いが)。カメラの基本構造が「カタチ」に及ぼす影響の大きさを思い知る格好の教材といえるが、また同時にこの言葉からは合理性を重んじる欧米人ならではの発想が読んで取れる。大概の欧米の人たちにとってはどちらも「輸入品」であることも理由のひとつとして挙げられるが、ライカもマミヤもブロニカも同等の価値観で評価できなければこの発想は不可能である。欧米からの輸入品がある種神格化された価値観によって評価されることが多い日本では、仮にこの言葉を思い付く人がいたとしてもその後の市民権を得ることは難しいのではなかろうか。MFLがもともとそれほど華のある分野では無いにせよ、事実日本のメディアでこの表現を見かけることはほとんど無い。
戦前のライカが群を抜く高性能レンズと超精密金属ボディによって、当時標準とされていたはるかに大きなフィルムサイズを使用するカメラをことごとく凌駕したことは有名な話である。その思想は戦後の日本製一眼レフにも確実に受け継がれ、最終的に大きなフィルムサイズは主役の座から転げ落ちた。替わって35㍉判がフィルムカメラの世界標準となったが、さらにその後に登場した高性能中判カメラが、かつては大量の中判カメラを絶滅に導いた張本人ともいえるライカの名を冠するとはちょっと皮肉な展開と言える。
そこで一見相似形に見えるがライカとMFLだが、その生い立ちにおいては大きく異なっている。
ライカの場合当初のモデルにはなかった距離計を後から内蔵するなど、最終的な形が決まるまでに幾多の紆余曲折を経ているが、一眼レフの技術が未熟だったに時期において、当時はるかに信頼性が高かった距離計連動ファインダーは測距精度の確保とレンズ交換式の両立のためには都合が良かったと言える。
しかし一方で既に中判カメラにすらAF化の波が押し寄せていた時期に誕生したMFLの場合はどうだろう。
理由は簡単明瞭小さく出来るからである。
一眼レフは原理上そのフィルムサイズに比例する大きさのミラーボックスをボディ中央部に必要とするため、それぞれを距離計連動型とした場合35㍉判に比較して中判カメラの方が効果的に小さく設計することができる。実際M型ライカと国産MF一眼レフを比較してもボディの大きさに大差は無いが、マミヤ7は同社のRB67/RZ67と比べると同じ6×7サイズとは思えないほどの差がある。たったこれだけの理由ではあるが言ってみれば21世紀を目前に新しいカメラを世に出すためには「小さくすること」は十分な理由だったのである。
しかしライカとMFL、違いはこれだけでは無い。
シャッターである。シャッターの形式はカメラの性能や性格を決めるうえで測距方式と並ぶ重要な基本構造の一つである。シャッターの形式には大きく分けてフォーカルプレンシャッター(以下FPシャッター)とレンズシャッターがあり、ライカがFPシャッターを採用しているのに対してMFLを含む距離計連動中判カメラは(私の知る限り)例外なくレンズシャッターを採用している。
もちろんそれぞれの形式にはメリットとデメリットが存在するが、多くのレンズ交換式カメラがFPシャッターを採用する理由は、レンズシャッターに比べて①高速シャッターを無理なく実現し②交換レンズのコストと部品点数を抑え③システム全体の耐久性を高い次元で確保し④大口径交換レンズの設計を可能にするためである。
設計者にとって原理的に優れた方式を予め採用することは、技術の改良と同等かそれ以上に重要な使命である。ところが同じ中判カメラでも一眼レフにはFPシャッターの新型機や人気機種が存在し、また過去に遡れば二種類のシャッター形式と測距方式それぞれの利点を生かした全ての組み合わせ例が存在するにも関わらず、何故か「中判距離計連動+FPシャッター」という組み合わせだけが存在しないことは私にとって事のほか不自然に写って見える。測距計精度を無視する訳には行かないが、開放F2の大口径レンズを自在に操れる軽快な中判カメラは今後望むべくも無いのだろうか。
カメラ業界全体のデジタル化が急速に進む現在、いまさらFPシャッターを搭載したMFLの新型機を望むことは半ば絶望的ともいえる。しかし今や完全に作り尽くされた感すら有るあらゆるフィルムカメラの中で、このジャンルを最後の「宿題」として想像をめぐらすことも楽しいが、できれば近い将来意欲的なメーカーが登場し究極の「中判ライカ」を創造してくれることを願わずにはいられない。