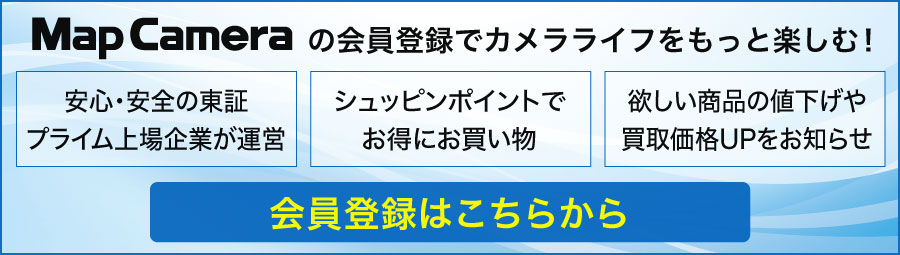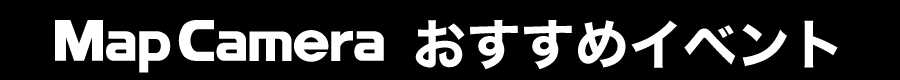【極私的カメラうんちく】第20回:ニュートンの鏡
現在写真レンズに使用されている光学ガラスは、その「屈折率」と「分散」の性質によって様々な種類に分類されている。「屈折率」は容易に想像できる性質だが、分散とはあまり聞き慣れない言葉であるが、分散とはプリズムが太陽光を分解するように、光の波長によって屈折率が異なる性質のことである。分散は色収差という性能に直結している。色収差が補正されていないと、像には虹色の輪郭線が発生する。そのためガラスの性質を分類する上では屈折率と同様に重要なものである。波長による屈折率の差が大きければ高分散、差が少なければ低分散と表現する。レンズカタログなどで見かける「特殊低分散」「異常低分散」などの用語はその一例である。
通常、ガラスは屈折率と分散が比例関係にある。つまり屈折率が高くなれば分散も高くなり、逆に屈折率が低くなると分散も低くなる。そのため写真レンズの黎明期においては、分散の影響による色収差を補正することが出来ない時代が長く続いていた。しかし1890年頃になって、分散と屈折率の比例関係が崩れた、特殊な性質をもつガラスが何種類も発明される。これらのガラスはその発明に大きく貢献したカール・ツァイス社の所在地から、イエナガラスと呼ばれている。このイエナガラスの発明により、高屈折低分散と低屈折高分散の相反する性質を持つレンズ同士を組み合わせて、分散、つまり色収差を大幅に低減したレンズの設計が可能になった。この時代に開発された、屈折と分散の性質が異なる2枚のガラス同士の組み合わせによって色収差の補正を行う技術は「アクロマート」と呼ばれる。アクロマートの技術は、特に焦点距離の長いレンズに劇的な効果を発揮する。
しかしアクロマートは可視光領域の一部波長を補正できない欠点があり、感光材料の進歩によって次第にカラー映像が一般的になるにつれて、全ての可視光領域を補正できる写真レンズが求められ始めた。可視光領域の全てを補正できる光学系は、相当以前から理論的には設計可能だったが、それまで作られてきたものとは全く違う屈折率と分散の特性を持ったガラスが必要だったため、実用化には至っていなかった。実は蛍石(ほたるいし)という天然鉱物の光学特性が、理想的なレンズ設計のために最適であることまで判っていたが、蛍石は天然鉱物のため、非常に高価でごく少数、しかも非常に小さなレンズしか作れなかったのである。そのため一部の顕微鏡用対物レンズなどには用いられていたが、写真用レンズとして実用化することは非常に困難だった。蛍石を使用し全ての可視光領域を補正した光学系はアポクロマートと呼ばれ、やがて蛍石にきわめて近い光学特性を持った「特殊低分散」や「異常低分散」と呼ばれるガラスの合成に成功したり、蛍石そのものの人工結晶化に成功したのがきっかけで、1970年頃からアポクロマートの写真用レンズへの応用が始まる。そして現在は大口径超望遠レンズから比較的廉価なズームレンズにも採用されるまでになっている。さらに現在の写真レンズの色収差との闘いは回折(かいせつ)光学素子を用いた新たな時代に入っている。
ここまで様々な色収差との闘いを見てきたが、実はアポクロマートの遥か以前から、色収差と無縁の光学技術が既に存在していた。
鏡を使った反射光学系である。分散は屈折の結果生まれるため、反射式の光学系には理論上色収差が発生しないメリットがある。さらに光路を何重にも折り返すために、一方通行の屈折系に比べて全長が非常に短くなるのも特長である。現在の写真用レンズに採用されている反射光学系は全て、反射光学系と屈折光学系を組み合わせたカタジオプトリック式である。カタジオプトリック式は反射面で生じた収差を屈折系で補正する巧妙なつくりで写真撮影に適した光学系でもある。
かの天才科学者ニュートン(1643~1727)は天体物理学者として望遠鏡の研究にも携わり、光学の分野でもその才能を発揮した。その際ニュートンはプリズムが光を分散させる性質についても詳しい研究を行っているが、当時イエナガラスはまだ発明されておらず、さしもののニュートンも屈折光学系による色収差の補正は不可能と判断した。その結果、反射光学系の研究に没頭し、ついに反射式望遠鏡を発明してしまったたことは有名な話である。ニュートンが発明したニュートン式反射望遠鏡は現在でも十分実用的であり、当然ながら当時の望遠鏡の主流だった屈折系のケプラー式と比べて、格段に鮮鋭な像が観察できたという。
様々な経緯によって、人類は色収差の回避方法を今や3つも手に入れたことになる。300年前の星空を、虹色の収差越しに見上げていた天文学者達から見れば、なんともうらやましい限りには違いない。