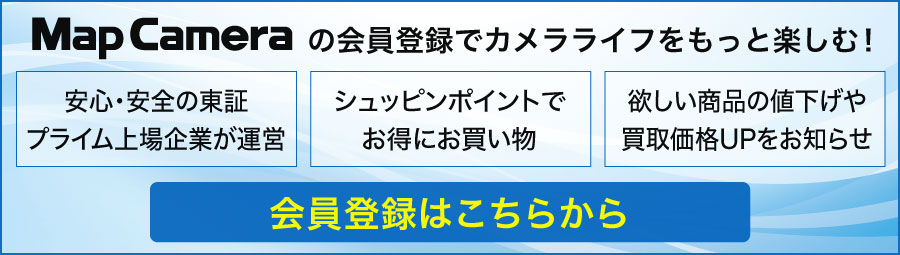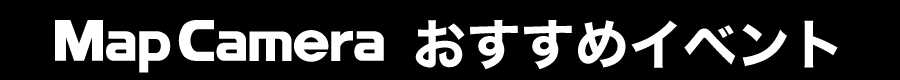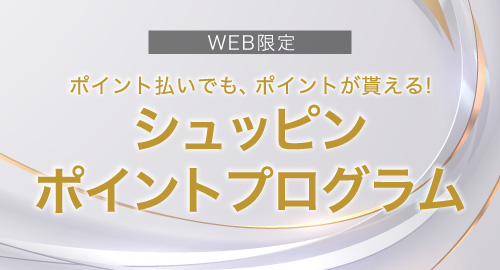【極私的カメラうんちく】第30回:改良限界論
カメラに限らず、人類が創り出してきた数々の道具はすべからく「改良」の歴史を歩んできたと言える。道具とはある必要に応じて開発され、その必要性が続く限りにおいて常に改良され続けるものだからである。しかし道具が創り出されたときに持ち合わせた「制約」には、その後の改良によって解消している場合と、そうではない場合とが存在する。つまりこの事は、その性能や仕様には、どうしても越えられない「改良限界点」が存在するということになる。また、逆に言うと道具は幾つもの「改良限界点」によってその仕様が決まっているとも言える。さらに言えば限界点そのものが「道具」としての定義すら決めていると言っても過言ではない。一見、その道具の仕様を決めているのは、開発/実装が可能だった「改良部分」と考えがちだが、もし一切の「改良限界」が存在しなかったとしたら、今現在私たちが使用している全ての道具がどうなっているかなど、全く想像すらできない。その意味で私たちが使う道具が、何故今こうなっているのかを理解する上で、「改良限界」の認識は非常に重要であるといえる。今回は普段私たちが慣れ親しんでいる、「改良進化」という概念とは全く裏返しの「改良限界」という発想で、「道具」の成り立ちを考察してみることにする。
「道具」の仕様に大きく関わっている改良限界には様々な種類があると考えられるが、では、それらはいったいどのようなものなのだろうか。改良限界をいくつかの種類に分類してみると、以下のようなものになる。
■原理(理論)的限界
たとえばジェット旅客機の巡航速度の限界は音速に大きく依存している。超音速飛行が可能な旅客機の製造は不可能ではないが、安全やコストを最優先する旅客機の巡航速度は音速の80パーセント程度であり、これはジェット旅客機の登場以来30年以上変わっていない。また写真レンズを含む光学製品の大きさは、焦点距離と明るさ(F値)の関係において物理的な制約を受けており、たとえば大口径レンズの小型軽量化には理論的な限界値が存在する。さらに光学系の解像力(分解能)においても回折限界という理論上の限界があり、理想的な光学系の解像力の限界は、その有効口径に依存する。またどんなに性能の良い光学系を設計しても、理論上光の波長以下のものは解像することができない。
■技術的限界
改良限界のイメージとしては最も一般に認知されていると考えられる。科学技術そのものの限界によって決まってしまうことであり、実験的には確かめられていたり、将来的には実現可能な見通しがあっても、製品として世に送り出すまでには時間がかかる場合も含まれる。現在、デジタルカメラの画素数やメモリーカードの容量はこの技術的限界によって決まっているといえる。
■実用的限界
技術的には開発/実用化が可能であっても、製品となった場合の大きさや重さ、または開発費用などの費用対効果によって達する限界。たとえば焦点距離600ミリでF2という一眼レフ用交換レンズは、需要があったとしても通常の使用環境ではとても使いものにならないのは明らかである。開発費用も莫大だろうし、製品となった場合でも「天文学的」な販売価格となるのは容易に想像できる。これは「実用性」を著しく損なう進化改良は実現しないことを意味する。また逆に小さすぎることも一種の実用限界と考えられる。カメラ用のメモリーカードは、これ以上小さくすると、紛失の可能性の方が高くなってしまうだろう。
■社会的(消費者)欲求限界
ある一定水準以上の性能(仕様)向上を、誰も期待しなくなることである。消費経済を前提に製造される道具に付与される性能は、消費者の需要がなければこの世に出ることは無い。つまり度を越えた「改良」はすでに改良とは呼べないのである。そういった意味で、携帯電話やコンパクトデジタルカメラの小型化は、操作性を確保する上ですでに社会的欲求水準に達したと思われる。また、単焦点レンズの結像性能には、筆者から見ると、ここ20年間ほど実用的な意味で大きな違いは見受けられない。これは単焦点レンズの性能が、既に筆者が認識できる性能評価の限界に達しているといえるが、これもまた個人的な社会的欲求限界のひとつと考えて良いだろう。ただし一般に社会的欲求限界は他の限界と異なり、常に社会事情に依存するものであるためその見極めは難しい。消費者の要求水準は時代とともに変化するものなのである。
こうしてみると、カメラのような最先端技術の塊のように見えているものですら、様々な理由で進化改良が滞っており、また現在の仕様は進化や改良の取捨選択を繰り返した結果であることがよくわかる。そして進化や改良の取捨選択の結果「改良限界点」から決まる仕様が、「進化改良」の結果に近いものほど進化した道具であると言えるが、それはつまり「あらゆる」進化改良を施した結果ともいえるからである。
カメラという道具の歴史や現状、またはその未来を正しく理解しようとするとき、普段とは全く反対の「改良限界」の視点からの考察が、「時折り」有効であることは間違い無いようである。