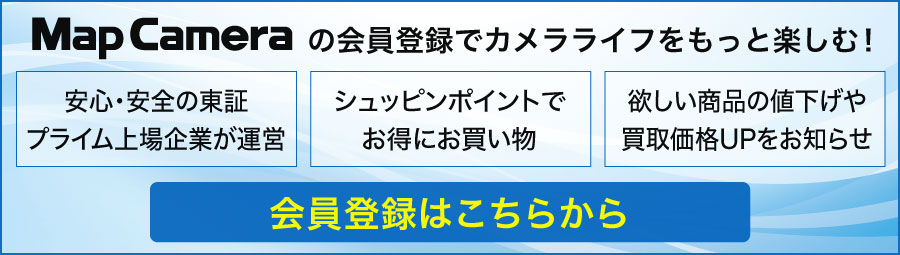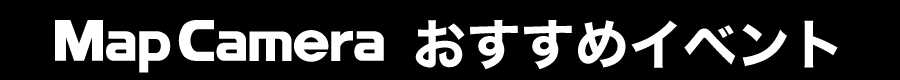【極私的カメラうんちく】第31回:手振れ補正技術の未来
先日のオリンパスE-510の発売で、一眼レフの手振れ補正技術がメーカー各社から出揃ったことになる。
手振れ補正技術には大きく分けて3種類があることは以前にもこのコラムで取り上げたことがあるが、現在一眼レフやコンパクトデジタルカメラで採用されている手振れ補正技術は、そのうち光学式手振れ補正と、撮像素子シフト(ボディ内蔵)方式の2種類である。
実はこの2種類の方式には「基本的技術」にそれほどの違いは無い。カメラ本体やレンズに内蔵された角速度センサーがカメラやレンズの動きを感知し、CPU(中央演算素子)がその動きに対応する動作指令の演算処理を行った後、アクチュエーター(駆動装置)に動作を指令伝達する。アクチュエーターはCPUからの指令通りに光学系や撮像素子を駆動するだけであり、このアクチュエーターが駆動する対象が光学系なのか、撮像素子なのかの違いだけである。
もう少し詳しく見てみると、光学式手振れ補正は交換レンズの光学系の一部を高速で動かして手振れを補正する。そのため手振れ補正機能を内蔵した交換レンズでなければ手振れ補正が効かない一方、撮影前のファインダー像が格段に安定する大きなメリットがある。そのためAFで撮影する場合はもとより、MFを多用する状況のピント合わせでは光学式手振れ補正の方が明らかに有利である。言ってみれば、「光学式」は手振れ以外に「ピンボケ」をもカバーしているのである。
光学式手振れ補正方式は、1995年にEF75-300mmF4-5.6 IS USMで始めて実用化したキヤノンを筆頭に、ニコンの「VR」とシグマの「OS」が採用している。
一方、撮像素子シフト方式は撮像素子側を高速運動して手振れを補正する。AF交換レンズの大半で手振れ補正が作動するため、ユーザーに交換レンズのコスト負担が発生しないのが最大のメリットである。中でもペンタックスの「SR」のように、焦点距離の手動入力まで可能なものになると、理論上物理的に装着できる全てのレンズで手振れ補正が働くわけで、その恩恵は計り知れない。ただし、アダプターを介して装着したレンズは大抵MFで使用するわけだが、そこで撮像素子シフト方式であるが故にファインダー像の安定効果が望めないところは、なんとも歯がゆいところではある。撮像素子シフト方式はコニカミノルタが2004年にα-7デジタルで初めて実用化して以来、現在はαの血統を受け継ぐソニーの他、ペンタックスが「SR」、オリンパスが「IS」という商標で採用している。コニカミノルタは既にカメラ事業を撤退しているが、当時の新技術への飽くなき探求心は確実に受け継がれ、今や手振れ補正技術の双璧をなすまでに成長したのである。
ところで、手振れ補正の方式が業界を大きく二分している最大の理由は、それぞれの方式のメリットやデメリットの議論以前の問題として、それぞれのメーカーが手振れ補正技術を実用化した「時代背景」が大きく関わっていることをご存知だろうか。
世界初の光学式手振れ補正内蔵カメラは1994年のNikon ズーム700VR QDというコンパクトフィルムカメラであり、また一眼レフの分野でキヤノンが独自の手振れ補正技術「IS」を開発した1995年当時も、カメラといえばフィルムカメラがあたりまえだった。
当時各メーカーは最新型のフィルムカメラを続々と発売しており、一部のユーザーを除くと、新製品に関するほとんどの興味対象はフィルムカメラが提供していたといってよい。一方でレンズ交換式のデジタル一眼レフカメラは、当時はまだ業務用機種に限られており、とても一般ユーザーの手の届くものでは無かった。またそれらは当時最新型のフィルムカメラの外装やシャッターやファインダー光学系を一見そのまま流用して作られており、一種の「改造品」という意味から、元になったフィルムカメラを指して「ベースカメラ」なる言葉も存在していたほどである。軽量でモジュール化されている撮像素子とは違い、支持構造を含めると相当の重量になるフィルムバック全体を高速で駆動することには相当の技術的困難があったと見るのが自然であり、いわば全てがフィルムカメラ基準だった時代にオートフォーカスに続く新技術として開発された手振れ補正方式が、比較的軽量で、モジュール化されているレンズ光学系の一部を高速運動させることによって実現したのは当然の帰結といえる。そしてその後ニコンやシグマが追従した時代背景も、基本的にはキヤノンの場合と全く同じだったといえる。
しかしα-7デジタルが発売された2004年当時は大きく事情が異なっていた。この年はデジタルカメラの出荷台数がついにフィルムカメラを追い抜き、デジタル一眼レフにもプロ用機種以外のコンシューマーモデルが続々と発売されていた。いつしか「ベースカメラ」といった概念も姿を消し、全ての基準がデジタルカメラに移りつつある時代だったのである。その時点で手振れ補正を新規実用化するにあたって、もはや光学式にこだわる理由は無く、撮像素子を駆動する方式を選択したことはこれまた自然な流れであり、それどころかこの時点であえて「光学式」を選択することは、メーカーにとって新型レンズの開発やラインナップの拡充に莫大なコストや時間がかかり、ユーザーには新たな買い替え負担を要求する、むしろナンセンスな選択だったといえる。しかもペンタックスやオリンパスが追従したのは昨年から今年にかけての出来事であり、時代背景は撮像素子シフト方式にとって、α-7デジタルの時代よりもさらに有利に働いているといえる。
かつて「露出不良」「ピンボケ」「手振れ」の三つは「写真の三悪」と呼ばれ、その駆逐のためにカメラは進化改良を繰り返してきたといって良い。そしてこの駆逐にかかった時間は優に半世紀を越えている。いわば半世紀以上の時間の中で「たまたま」デジタル化の転換期に差し掛かっていた時に手振れ補正技術の普及が進んだ結果が、現在の状況であるといえる。手振れ補正技術の「老舗」と「新鋭」で大きく方式の異なる手振れ補正技術が作られたというわけだが、冒頭で述べたように、手振れ補正に関する技術はどちらの方式も原理的には同じであり、またカメラという小型精密機械の中で、センサーからの情報を高速でアクチュエーターの駆動にフィードバックする技術は、オートフォーカス技術の発展応用によって確立したものであることは間違いない。そのため「駆逐」の順番はその優先順位とも同等であり「必然」だが、ちょうど手振れ補正技術の「普及期」に、手振れ補正とは全く別個の技術である「デジタル化技術」が加わった結果、駆動される対象が二つに分かれたと考えるのが自然である。
ともあれデジタルカメラが「常識」となった現在、今後は撮像素子シフト方式に有利であるかのように見える。ならば光学式の補正技術は淘汰されてゆく運命なのだろうか。
実はコンパクトデジタルカメラの分野は双方の方式が入り乱れており、一概に光学式が不利とは言えない状況である。最新機種同士で比較しても、ソニーは一眼レフでは撮像素子シフト方式を採用していながら、コンパクトデジタルのサイバーショットシリーズでは光学式を主に採用している。またニコンは一眼レフで光学式を採用している一方で、コンパクトデジタルのクールピクスシリーズの一部では撮像素子シフト方式を採用している。
1960年代から70年代にかけて、写真の三悪のひとつである「露出不良」を駆逐すべく、メーカー各社が「自動露出」の機能を搭載した一眼レフを初めて発売した時代がある。AE(自動露出)時代の本格的幕開けである。その頃の一眼レフに搭載された自動露出モードは、「絞り優先(AV)」か「シャッター優先(TV)」のどちらかひとつしかなかった。そのため、当時の購入者はそれぞれの露出モードの特長を見比べた上でカメラを選択するのが当たり前だった。今となっては笑い話に聞こえるかも知れないが、メーカーは自社が選択したたった一つの自動露出モードのメリットを広告でアピールし、何とか自社のカメラを買ってもらおうと必死だったし、カメラ雑誌も真剣に露出モードのどちらが良いかを誌上で議論し、読者もそれについて興味津々だったのである。ある著名な写真家は、この議論についてのコメントを求められたとき、いみじくも「そりゃあ両方あるのが一番だろう」と答えたという逸話すら残っているほどである。そして程なく「両優先」という、どちらの露出モードも搭載したカメラが発売されるに至ってこの議論は急速に収束したのだが、この昔話が現在の手振れ補正の状況に良く似ていると思うのは筆者だけだろうか。
事実、現在フォーサーズシステムの手振れ補正は、パナソニックが発売した光学式手振れ補正レンズ「ライカDバリオ・エルマリート14-50mm/F2.8-3.5 ASPH」を含めると、既に二つの方式が存在していることになる。
歴史は繰り返す。手振れ「両補正」方式の時代は、実はもうそこまで来ているのかも知れない。