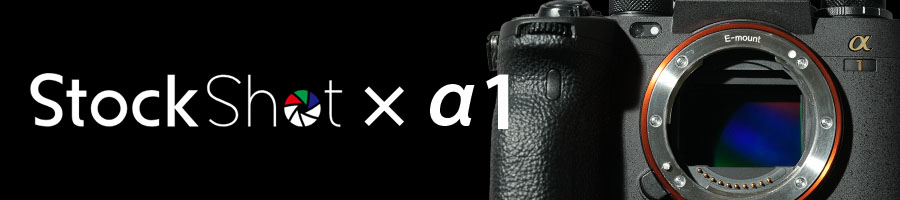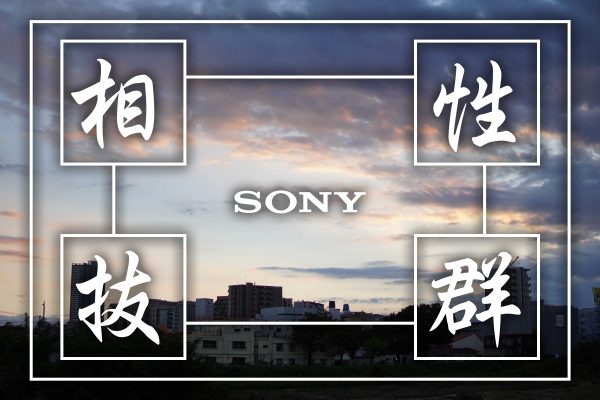【SONY】最強の組み合わせ、フラッグシップと望遠レンズで撮るアニマルフォト
高画質、高速連写、高性能AF
これら全てをギュッとまとめて一台に凝縮させたようなカメラこそ『α1』
今回そのα1と共に、FE 100-400mm F4.5-5.6 GMという定番レンズを組みあわせて動物園へと撮影に向かいました。

α1といえば、αシリーズでも最上位モデルのいわゆるフラッグシップ機に該当します。フラッグシップと聞くとどうしても「プロ用」であると思い込んでしまい、カメラ選びの選択肢から外してしまう方もいるのではないでしょうか。
確かにフラッグシップモデルの多くはプロの用途に応えることができるよう、一台で様々な用途に対応することが可能であるため、出来ることが多く難しいカメラだと感じるかもしれません。しかし、だからこそ選んでいただきたいと考えております。
理由はただ一つ。プロが選ぶからこそなのです。プロに選ばれるモデルは自分自身にとってオーバースペックと感じるかもしれません。しかし、オーバースペックだからこそ撮影をラクに・快適にしてくれるのです。


さて、ではα1のどういった点が優れているのか、プロ機として選ばれるスペックを有しているのかと言いますと、まず注目したいのが約5000万画素の高画素で撮影ができる点。動きの少ない被写体にはISOを落として撮影を行うことで高画素特有の精細な写真を撮影することが出来ます。
上記作例の写真はISOを100で撮影されたサーバルキャットとISO250で撮影されたアムールトラの写真です。どちらもネコ科の猛獣特有の短く硬そうな体毛の質感をしっかりと表現してくれています。

そして高画素であるメリットの一つにクロップ耐性が挙げられます。カメラ内にもAPS-Cクロップという機能がαシリーズには搭載されており、焦点距離を1.5倍にすることが出来ます。今回用いたレンズをAPS-Cクロップした場合の焦点距離は最大で600mm相当になります。
あくまでも光学的なズームでなく使用画素領域を減らして行う電子的な処理であるため、使用画素数が約40%程度に減ってしまいます。通常の2400万画素のカメラであればクロップをかけた際に内蔵されている1.5倍クロップで画素数は1000万画素弱にまで減少してしまうのですが、α1は倍以上の画素を有しておりますので約2100万画素も残すことが可能です。

クロップをかけていない状態がこちら。
割と近くにいたので、大きく撮影することが出来ましたが、それでもそこそこ小さいので少し被写体を探すのに苦労するサイズ感です。

4K相当の画質である約800万画素(16:9)までクロップをしてみると、ここまで拡大させることが出来ます。
小型な野鳥として知られるエナガをたまたま園内で見かけたので撮影をしたのですが、400mmではエナガほどのサイズだとよほど近寄れたりしない限り大きく撮影するのは至難の業。高画素機だからこそ、ここまでアップで残すことが出来ました。


小型の野鳥全般、動きが非常に速く予測が非常に難しい被写体で、加えてあまり同じ場所に留まることがほとんどないので捉えてオートフォーカスを作動させたとしても合焦する前にフレームアウトしてしまう事が多いのですが、α1であれば一度ファインダー内に捉えることさえ出来てしまえばオートフォーカスが速いためしっかりと合焦させて撮影することが出来ます。

園内の動物の写真に話を戻します。
続いてはレッサーパンダの撮影を行いました。訪れた際はたまたま食事をしている最中だったのでそのシーンを収めました。

αシリーズのカメラといえば優れた「瞳AF」の機能を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
実際にα7Ⅲから搭載された瞳AFは当時のミラーレス市場はおろか、カメラ市場全体に大きな激震を与えたといっても過言ではない機能の一つです。カメラを向けるだけでカメラが人物の瞳を認識し、そこに自動でオートフォーカスを合わせてくれる。今でこそ大きく普及した機能ではありますが、当時はとても話題なった機能で今ではαシリーズの代名詞的な存在です。
α1には、この瞳AFの検出対象に人物の他に動物と鳥が追加されており、上記のレッサーパンダはすべて動物を対象とした瞳AFを用いて撮影行いました。
笹を頬張るために顔を左右様々な向きに振ったり手前に笹が被ってしまうことが多々ありましたが撮影中は、常時レッサーパンダの顔をフォーカシングし続けてくれました。
後ろを向いた瞬間に外れるシーンがありましたが、こちらに向き直った瞬間に即リフォーカスしてくれたのでシャッターを押すだけでしっかり瞳にピントの来ている写真を量産できました。

最後はイヌワシの撮影を行いました。
これは、今回の撮影で一番の当たりカットです。先ほど紹介した小型なエナガ然り、鳥類の撮影は非常にタイミングと運に左右されます。たまたま飛び立った瞬間を見てカメラを構えることが出来てもピントが合う前にフレームアウトしたり、ピントが合い切らずピントの甘い写真になってしまったり。特定の個体に当たりを付けてカメラを構えていたら、全然違う個体が気づかぬ内に優雅に自分の近くを飛んでいたり。
後者は正直どうしようもないのですが、前者はα1であれば何とかなってしまう事があります。何故ならα1には鳥に対応した瞳AFと積層型センサーによる高速のAF性能を備えているからです。
既に登場から時間が経っておりご存知の方もたくさんいると思うので簡単に説明をさせていただくと、α1は秒間30コマの連写に加えて1秒間に120回のAFとAEの演算処理をしてくれます。これは1秒間に120回ピント位置と画面の明るさの計算を行ってくれます。秒間30コマ連写の設定の場合、1コマあたり4回ピントと露出の計算をしてくれるため連写中でもピント位置はもちろん僅かな明るさの変化でも正確に対応することが出来ます。


こちらが先ほどの作例の差分です。このイヌワシは筆者がいるほうに向かって飛んできており、前後の動きが出ていますがピント面が外れることなくイヌワシを合焦し続けております。
この飛翔があったとき筆者はカメラをしっかりと構えておらず、咄嗟の出来事にかなり焦っていたので設定とかは全く詰められていない状態でとりあえずカメラを向けてフレーミングして連写を切っただけの状態でした。
しかし、撮影後見てみると6割近くがしっかり顔にピントが合っており撮影中はなんと鳥瞳AFが認識している瞬間もありました。そのおかげで飛翔の撮影で成功を収めることが出来ました。

いかがでしょうか。
今回α1と定番の望遠レンズであるFE 100-400mm F4.5-5.6 GMとの組み合わせでご紹介させていただきました。筆者は動物の写真を撮影することは大好きなのですが特別上手なほうではありません。そんな筆者でも動体撮影を行ったときに、成功体験を収めることが出来たのはα1のおかげだと思います。
プロに選ばれるフラッグシップモデルであるからこそ、アマチュアの我々でも非常に大きな恩恵を受けることが出来ます。
在庫が多数ありお買い得である今こそ是非一度手に取って体験していただきたいカメラだと思いますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いします。
▼期間限定!中古全品ポイント最大10倍還元α1は10倍対象です!▼