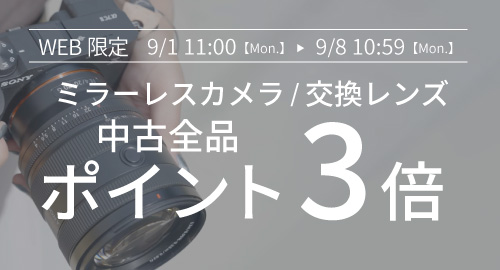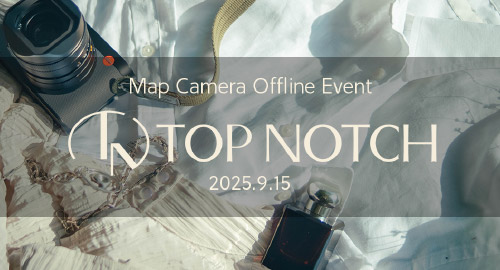朝晩の気温がぐっと下がる中、バードウォッチャーにとって熱い季節がやってきました。北方からやってくる渡り鳥だけでなく、一年を通してその土地で生活する留鳥も動きが活発になることで様々な姿を観察することができる季節、それが「冬」です。今回のテーマは『カワセミ』。バードウォッチングを始める人々の多くがそのきっかけとして挙げる鳥であり、留まりから飛び込みまで撮影の難易度が大きく変化する鳥でもあります。筆者自身学生時代から河川敷で見かけるたびに心惹かれ、いつかはその姿を美しく記録したいと考えておりました。特にベテランのバードウォッチャーが写す狩り瞬間は芸術とも言え、この記事をご覧になっている方の中にもその道の先輩がいらっしゃるかもしれません。本連載では所謂「カワセミの飛び込み」を目標に、カワセミ撮影初心者の紆余曲折を私たち人間との関係性や様々な野鳥の紹介を交えながらお届けします。

記念すべき初回のお供に選んだ機材は『Leica SL3』と『Sigma 500mm F5.6 DG DN Sports』。動体撮影のイメージがあまりないライカですが、位相差検出・物体認識・コントラストの3つのテクノロジーを撮影状況に合わせて相互作用させることができる最新モデルに期待値は上がります。数少ないライカLマウントの望遠レンズの中でも超望遠に類するシグマ自慢の単焦点レンズの実力にもご注目ください。この連載では様々なメーカーの機材を使用してカワセミ撮影を行います。それぞれの特徴や画作りの違いについてもお伝えしていきますのでお楽しみに。
・・・

カワセミ:翡翠
英名:Common kingfisher
学名:Alcedo atthis
こちらがターゲットであるカワセミ、わずかに下の嘴がオレンジがかっているためメスだとわかります。オスの場合は上下ともに嘴が黒くなっています。和名である翡翠(ヒスイ)は一般的には宝石の名前として知られていますが、「水辺の宝石」と呼ばれるほどの美しいコバルトブルーの羽にちなんで室町時代にカワセミと読むようになったそうです。河面に突き出た枝の上から餌となる小魚を探し、電光石火の如く水中に飛び込み捕らえるハンター。その決定的瞬間を捉えることが本連載の最終目標となります。全長は約17センチとかなり小型ですが、自転車のブレーキ音に例えられる高い鳴き声と青とオレンジの美しいコントラストを目印に比較的簡単にその姿を見つけることが可能です。
・・・

自宅近くの川、そのすぐ横を通る首都高の下には企業と地域住民が協力して管理するビオトープがあります。今回はこのビオトープを中心に撮影を行いました。ビオトープとはギリシャ語で「生物」を意味する「bios」と「場所」を意味する「topos」を合わせた造語で、人間による都市化や開発の影響で失われた生態系を取り戻すためにヨーロッパなどで始まった動きのことを指します。工業が盛んなドイツでの環境悪化を受けて始まったこの動きは、「自然型」・「保全型」・「公園型」・「教育型」・「憩い型」の5種類に分けられているそうです。近年増加している豪雨による河川の氾濫を防ぐことなどの治水を目的として護岸が進められ、カワセミが本来巣作りをする河岸が使えなくなってしまっていることもあってその重要性は増すばかり。

さて、こちらが今回のフィールドです。河岸に降りることができかなり低い視点から撮影を行うことができます。500mmというかなり限られた画角で相当なスピードの動きを追うということで、対岸の枝から真下に飛び込む瞬間を狙うイメージでアプローチしていきます。


カワセミを観察しながら気がついたのは同じ川で生活する野鳥たちの多様性です。市街地でもよく見かける小鳥から、様々な色合いの水鳥、身体の大きなサギ科の仲間やカワウまで。もちろんこれで全てではなく、タカ科を含む猛禽類に出くわすこともあります。気温の低い時間帯に活動が盛んになる彼らの姿を写すべく、明け方と日の入り前に撮影を繰り返す日々。仄暗い時間帯の撮影が多く高感度での作例が多いのですが、ノイズを無理に処理するのではなく活かそうとするライカの姿勢のようなものが感じられます。自然の営みは脆く儚いもので、人の手によって急激に変化する環境に適応できた種だけが生き残っています。撮影に際して彼らの生活を脅かすことがないよう常に一定の距離を保ち、部外者としてストレスを与えない工夫が必要です。
草木の葉が落ちるこの季節は見晴らしが良く、春や夏に比べその姿を発見することも容易に。多くの場合は50~100mの範囲を行ったり来たり、留まる枝もお気に入りのものがあることが多いため、一度見つけることができれば同じ個体を継続して観察できるかもしれません。
・・・

時間を見つけては川へ足を運ぶ日々。寒空のなか独り、シャッターボタンにかける人差し指を小刻みに震わせながらその瞬間を待っていました。水面を見つめ微動だにせず、飛んだかと思えば別の枝に移動したり、来た時にはすでに魚を咥えていたり。踏めない地団駄を踏みながらも、その愛らしいフォルムと美しいカラーリングに見惚れておりました。
・・・
とある日の昼下がり。枯れ草をブラインド代わりに息を潜めていると、やってきました。それも対岸ではなくすぐ横の木に。ふっくらとした腹部と鮮やかな朱色の脚が冬の河川敷に映えますが、あまりの近さに身動きが取れず水面が画角に入らないため飛び込みの撮影は叶いません。身を隠すこと以上にポジショニングが大切だということを痛感した瞬間です。

今回はここまで。残念ながら飛び込む瞬間を目にすることはできませんでしたが、想像以上に近い距離でその生態を観察できたことは次につながるはずです。昨今多くのカメラに搭載されているプリキャプチャー機能。『SL3』に搭載されていないことは承知していたものの飛び出す瞬間さえ何度も撮り逃す有様。必要とされる集中力の高さに驚きながら、しかしそれ以上に野生動物撮影特有の緊張感を楽しむことができました。
・・・
河川敷で夕暮れ時を過ごすことの多い筆者にとってカワセミは、そばで黄昏る友人のようであり、自然に生きる哲学者のようでもあります。首を傾げるような動きやじっと水面に目を凝らす様子は見ていて飽きることがなく、考え事や悩み事を勝手に共有しているような気持ちになるのです。
目を凝らせば、耳を澄ませば、いつもの景色の中に驚くほど美しい情景を垣間見ることができます。あらゆる情報が溢れ、常にそれらにアクセスすることのできる現代では、目の前の出来事に気づかないこともしばしば。写真撮影を趣味にして良かったと思うのは、それまで見過ごしていた何気ない景色やありふれた瞬間に感動できるようになったことです。綺麗だとだけ思っていたカワセミを、じっくりと時間をかけて観察したことで気づいた魅力や撮影そのものの面白さ。次回は「カワセミの飛び込み」を写すことができるのか。乞うご期待ください。