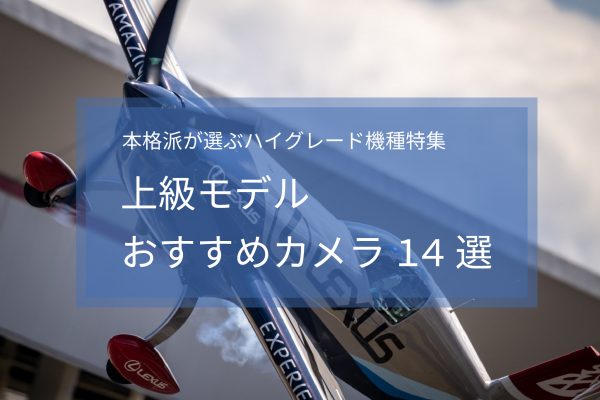ついに本日、SIGMAから待望の最新レンズ「Art 17-40mm F1.8 DC」がソニーE用、ライカL用、そして富士フイルムX用の3マウントで発売されました。
今回使用した機材
使用したレンズ「SIGMA Art 17-40mm F1.8 DC」

さてこちらが「SIGMA Art 17-40mm F1.8 DC」の姿です。今回使用したのは富士フイルムXマウント用です。
レンズ名の「DC」が示すように、こちらのレンズはAPS-Cフォーマット専用設計となっています。
SIGMAでF1.8通しのレンズといえば昨年発売の「Art 28-45mm F1.8 DG DN」が記憶に新しいですが、あちらはフルサイズフォーマットに対応する一方でズーム倍率が1.6倍と極めて低倍率であったのに対し、今回は17mmから40mmと、約2.3倍にズームレンジが大きく広がっています。35mm判換算ではおよそ25.5mmから60mmをカバーします。
実はSIGMAはおよそ10年前にAPS-Cフォーマットの一眼レフ向けに「Art 18-35mm F1.8 DC HSM」というレンズを発売しており、これがデジタル一眼レフ用交換レンズとして世界初のF1.8通しズームレンズです。この当時はわずかにズーム倍率が2倍に届かなかったのですが、今回は広角側、望遠側ともに焦点距離が伸びています。
また特筆すべきはその大きさで、重量は530g(富士フイルムXマウント用)と、一眼レフ用18-35mm F1.8から30%以上の軽量化に成功しています。
使用したボディ「FUJIFILM X-T5」

今回そんなレンズと組み合わせたのは「FUJIFILM X-T5」。
有効画素数4020万画素の高画素センサーと第5世代の最新エンジン「X-Processor 5」を搭載し、露出系をダイヤル操作によって設定変更することが可能な、小型軽量モデルです。
F1.8通しのズームレンズということでかなりの大きさを想像していたのですが、実際に装着してみると、グリップが比較的小さめなX-T5との組み合わせでも問題なく構えることができました。レンズが小さく軽くなることでボディも小さなものでバランスが取れるようになるため、レンズ重量という数値以上にシステム全体を軽くすることができます。
作例
SIGMA Art 17-40mm F1.8 DCの画角
約2.3倍というズーム倍率は、やはり数値として見ると小さく感じてしまいます。
実際に撮影する際、どの程度このズームレンジを活用することができるのか、画角を変化させながら見てみます。


それぞれレンズの広角端、望遠端に設定し、同じ被写体を撮影してみました。
こうして並べてみると、広角側ではパースペクティブが強調され、望遠側では圧縮効果が出ています。標準画角である50mmを挟んで広角、望遠それぞれの効果を1本で得ることができます。

特に、広角側がこれまでの18mmから1mm広い17mmになったことで、よりワイドな構図を楽しめるようになりました。広角側の1mmの違いは数値以上に大きく感じます。
SIGMA Art 17-40mm F1.8 DCの描写力

まずF1.8というF値の明るさについて、APS-C用とはいえ被写界深度はかなり浅くなるためボケは大きく出ます。
このボケ感はまさに単焦点レンズを扱っているときの感覚そのものです。

また解像度に関しても申し分ないものです。
F値開放での撮影ですが画面周辺部の枝まで克明に描ききっています。

最短撮影距離は28cmで、最大撮影倍率は40mm時に1:4.8となります。ピント面は鋭く、ボケは大きく表現することができます。

このレンズで撮影していて最も驚いたカットがこちらです。
写真から透明感、抜けのよさを感じます。感覚的な評価になってしまうのですがこのような写りは高級単焦点レンズでのみ得られるものだと思っていたので、この写りがズームレンズで出てきたことを非常に嬉しく思います。11群17枚のレンズ構成を採用し構成枚数はむしろズームレンズとしても多い部類に入ると思いますが、それでこの透明感、SLDレンズを4枚使用した贅沢な光学系と高性能コーティングが成せる写真だと思います。

また逆光耐性の高さにも驚かされました。太陽に思いきりカメラを向けてもゴーストやフレアの発生は皆無と言っていいです。
コントラスト低下もほとんど見られず、見たままありのままを捉えることができます。
まとめ


ズームレンズの利便性に単焦点レンズの写りを持ち合わせた、まさにズームと単焦点の良いとこ取りをしたようなレンズです。
筆者自身このレンズと試写をして、約10年前にSIGMA 18-35mm F1.8 DC HSMが発売されたときの、あの衝撃と感動が帰ってきたような感覚になりました。
SIGMAが世に送り出すレンズ群は唯一無二のラインナップばかり。そのラインナップの一角としてまた新たな選択肢が生まれたこと、そして撮れる世界が広がったこと、是非新たなる視点を手に入れてみてはいかがでしょうか。
▼その他のマウント用はこちら▼