
【2025年前半】新品デジタルカメラ人気ランキング
2025ランキング前半編CanonFUJIFILMNikonSIGMASONYエントリーモデルカメラと共に新品・中古デジタルカメラ人気ランキング
おかげさまでマップカメラは2025年8月13日に創業31周年を迎えます。
これまでマップカメラをご利用いただきました多くのお客様にあらためて感謝申し上げます。
今回は創業祭の特別企画として、2025年前半の価格別新品販売ランキングをお送りいたします。
5~15万円、15~30万円台、35万円以上と、3つの価格帯それぞれのTOP3に輝いたカメラたち。
実際に使用したからこそわかる魅力や特徴を、余すことなくご紹介いたします。
それでは早速行ってみましょう!
5~15万円のTOP3
エントリー機が中心の価格帯ということもあり、TOP3の顔ぶれもバラエティ豊かな結果になりました。
これからカメラを始める方が一番先に検討されるであろうボリュームゾーン、その激戦区を勝ち抜いたのはこの3機種です!
第1位 FUJIFILM X-M5


【手のひらサイズの本格派ミラーレス】
デビューから大人気のX-M5。小型ながら機能は本格派で、特に動画に至っては6.2K/30P 4:2:2 10bitの内部記録が可能です。
画質が良いのはもちろんのこと、とりわけ音へのこだわりが素晴らしく、「風音低減」、「定常ノイズ低減」、「ローカットフィルター」を駆使すれば外部マイクと聞き間違うほどのクリアな音声を収録可能!
さすがに音像定位や周波数帯域の広さでは外部マイクにかなわないものの、ほとんどは内蔵マイクでいけるのでは?と思うほどの音質を誇ります。
目玉であるフィルムシミュレーションダイヤルは便利な上に遊び心もあり、ダイヤルを回した時に画面に表示されるアニメーションでは「たくさんのワクワクが詰まったアソート感」を感じられます。
フィルムシュミレーション x 本格的な動画機能 x 超小型と、3つの強力な武器をもつFUJIFILM入魂のプロダクト、堂々の第1位となりました。
第2位 FUJIFILM X half X-HF1


【デジタルとフィルムの融合】
デジタルカメラながらフィルムカメラの撮影体験を味わえる、新しいコンセプトのコンパクトデジタルカメラです。
フィルムカメラを使用する際の大きな障壁となっているランニングコストがかからないので、現在フィルムカメラを使っている方の更なるステップとしても、フィルムを使ってみたい方のファーストステップとしてもおすすめなカメラです。
縦構図で撮れる事に加えてタッチパネルで色々と操作できるので、スマホのような操作感で使用できます。
また背面左側にある液晶には使用中のフィルムシミュレーションが表示されます。フィルムカメラユーザーにとっては馴染み深い位置にある覗き窓のような液晶は、スワイプ操作でフィルムシミュレーションを変えることができるので色の変更も簡単です。
さらに期限切れフィルムや光線漏れフィルムを再現したモードもあり、フィルムならではの現象を追体験することも可能です。
カメラに委ねて、色々と撮影してみるのはいかがでしょうか。
第3位 RICOH GRIIIx

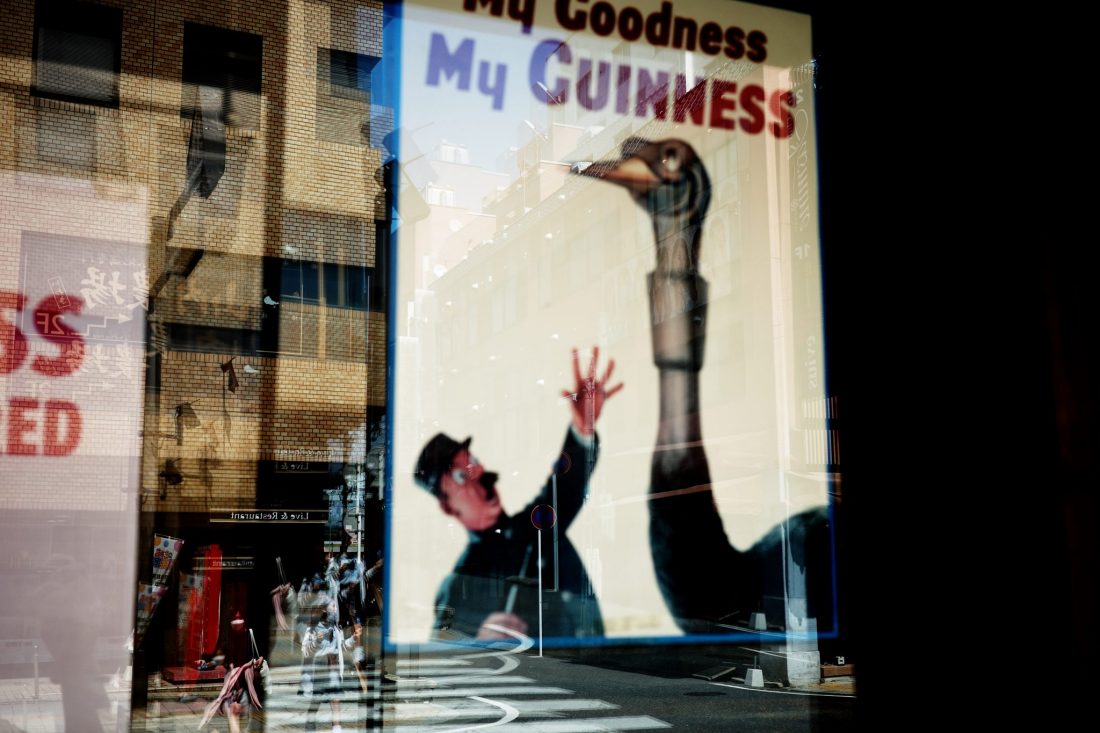
【RICOHの誇るスナップシューター】
操作レスポンスの良さや起動時間の早さといったGRの美点はそのままに、通常モデルのGRIIIからレンズが変更され、35mm判換算で約40mmという扱いやすい画角になっています。
新規設計されたレンズの切れ味はすさまじく、絞り解放から非常にシャープ。
周辺減光も緩やかなため、どのような被写体を切り取っても大きな癖なく描いてくれます。
更にこのレンズはボケ味も良いので、ボケを取り入れた写真も積極的に撮りたくなります。
どちらかというと「パンフォーカスのフルプレススナップで街に切り込みたくなる」GRIIIとは別の魅力があるといえるでしょう。
また、GRシリーズの美点である「影(シャドウ部)の美しさ」にはさらに磨きがかかり、コントラストがしっかりしているのにどこか柔らかく、時折ハッとするほど美しい陰影を魅せてくれます。
質実剛健な“道具”のはずなのに、だからこそ心をつかんで離さない。それがGRIIIxなのです。
一昔前より価格が上がったとはいえ、依然としてコンパクトデジタルカメラが強い存在感を示しています。
ミラーレス一眼で唯一ランクインしたX-M5も、サイズや使い勝手の面では所謂「コンデジライク」な面が目立つ機種と言えるでしょう。
今も昔も大人気のコンパクトデジタルカメラは、スマートフォンでは出来ない“撮影体験”を望む方に、「カメラって楽しいんだよ」と教えてくれる大切なポジションです。
カメラは小さく、楽しみは大きく・・・。
この矛盾がかなえられるのは、エントリークラスの価格帯ならではの特権かもしれません。
15~30万円のTOP3
ミドルクラス、所謂「中級機」が属する価格帯です。
各社それぞれの技術や考え方が性能として現れる、非常に面白いレンジとなっています。
コストパフォーマンスに優れたモデルや、飛び道具をもつ個性的なモデルといったバラエティ豊かなカメラの中から、「選ぶ楽しみ」も味わえる価格帯。
そこで栄光を手にしたのは以下の3機種です!
第1位 Nikon Z5II


【次世代のベーシック】
上位機種譲りの画像処理エンジン「EXPEED7」を搭載。
AFスピードは前機種のZ5から約3倍に、人物から飛行機までの被写体検出にも対応可能になり、AFを使ったピント合わせに関しては文句なしの性能です。
特に鳥認識の精度・速度はすさまじく、枝かぶりをものともしない検出能力には畏怖すら覚えます。
裏面照射CMOSセンサーを採用したことでの画質の進化や、連写速度が14コマになった所も大きなポイントで、インターフェースとしてのダイヤルなどが背面右側に集中している点も親指で操作が完結しやすく非常に好印象でした。
サイズ感はベーシックながらも内に秘めたその性能は実にパワフルです。
第2位 FUJIFILM X100VI


【手ブレ補正を手にしたX100の血統】
アルミ削り出しで作られたクラシカルなデザインが特徴的な本機は、スナップや日常撮影に特化した高画質・高性能の固定レンズコンパクトカメラです。
搭載している4020万画素の X‑Trans CMOS 5 HR センサーは、常用感度域でのダイナミックレンジが非常に広く、RAW編集の際の現像耐性が抜群。前機X100Vより階調の幅が広がり、シャドウからハイライトまで豊かなトーンを維持しています。
AF性能は顔・目・動物・車などの被写体検出は特に優秀で、被写体追従や精度においても大きな進化を遂げています。
また、6段分の5軸ボディ内手ブレ補正を搭載しており、夜間や屋内などの低照度環境でも1秒クラスの超スローシャッターでも手持ちで十分に安定して撮影可能!
そして人気の高いフィルムシミュレーションを20種類も搭載してる点も魅力の一つです。
第3位 Canon EOS R6 Mark II


【どんな被写体でも作品に】
EOS R6 MarkIIは約2420万画素のフルサイズセンサーを搭載しています。
どんなシーン、被写体の撮影でも対応ができるマルチロール機。ポートレートからスナップ、動体撮影までなんでもこなせます。
高画素すぎないバランスの取れた画素数で秒間40コマの高速連写との相性も抜群です。
また、被写体認識AF精度が素晴らしく、動体撮影・モータースポーツといった動きの速い被写体も容易にキャプチャーできます。このAF性能は上位機種であるEOS R3やEOSR5 MarkIIとも肩を並べるレベルです。
初めての方の本気の一台目として・プロフェッショナルユースの方のバックアップ機・サブ機としても。万人におすすめできる機種です。
マルチなシーンに対応できる性能を持った、ハイレベルなバランスを持ち合わせる中級機であるNikon Z5IIとCanon EOS R6 Mark II。
写真を撮る楽しさを追求し、特別な撮影プロセスを味わえるFUJIFILM X100VI。
ある意味正反対の方向を向いたカメラたちですが、それらが一堂に会するのもまた一興。
「好き」の形は一様ではなく、それぞれにお客様の撮りたい!が詰まった結果となりました。
35万円以上のTOP3
憧れのハイエンド機がずらりと揃う価格帯です。
類まれなる高画質、一瞬を逃さない高速性能、贅を尽くした造りやタフな環境でも撮影をサポートする耐久性と、誰もが頷く高い性能!
メーカーの顔ともいえるフラグシップ機はもちろん、そのフラグシップに劣るとも勝らないNo.2クラスも顔を並べる中、栄光を手にしたのは・・・
第1位 FUJIFILM GFX100RF


【ラージフォーマットセンサーを持ったコンパクトデジタルカメラ】
FUJIFILM GFX100RFは、「中判カメラといえば重い」という概念を覆した約735gの高画素コンパクトデジタルカメラです。
クラシカルな見た目に軽量で持ち運びやすく、中判センサーから生み出される幅の広いダイナミックレンジ、高精細な描写は唯一無二の存在。
最大1/4000秒となるメカニカルシャッターで運用する場合でも、4段階分のNDフィルターを内蔵しているおかげで、日常の明るい場所でも絞りを開けてボケ感を楽しむ撮影などが可能です。
また9種類のアスペクト比をダイアルで素早く切り替えられ、写真で慣れ親しんだ4:3や3:2といったアスペクト比だけでなく65:24のような横に長い構図でのアプローチも簡単に行えます。
第2位 Nikon Z8

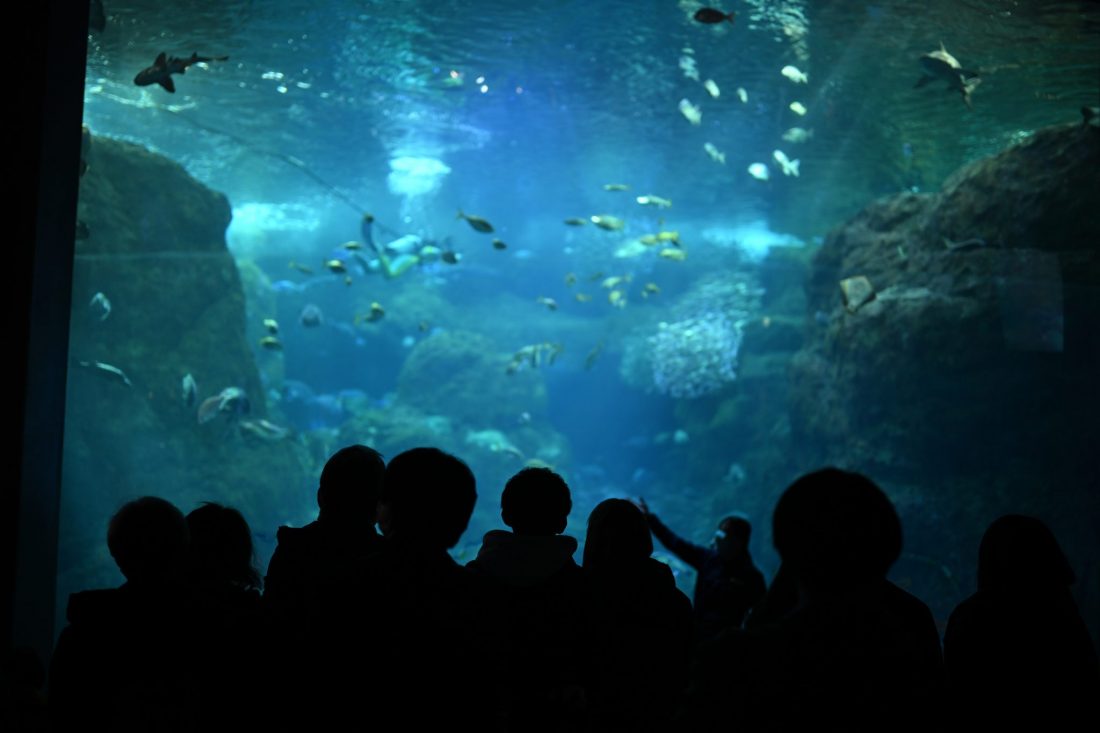
【万能のオールラウンダー機】
Nikon Z9の性能をそのままに高い堅牢性を有しながら、重量は820gとより軽く設計された本機。
グリップ部分がしっかり握れるので撮影ではさほど重さを感じません。
明るい場所では4571万画素という高画素を活かした解像度の高い写真が撮影できる他、最新エンジンEXSPEED7によりAF測距輝度範囲-7EVを実現。
これによりZ9譲りの高いAF性能と被写体認識性能を有し、高画素でありながら暗所での撮影も抜群の性能を発揮します。
さらに積層型センサーを搭載しているので高速読み出しが可能、高い連写性能を誇っています。
メカニカルシャッター非搭載でシャッターが動く微かなブレも無い為、ブレに対してシビアな高画素機にとってうれしいポイント。
メカニカルシャッターに慣れた人にはまた一味違った新鮮な撮影体験ができます。
また、最近Ver.3.0のファームウェアが公開され、発売から2年経っても進化する大人気機種となっています。
第3位 SONY α1 II


【“最高”を磨き上げたフラッグシップ】
SONY α1 IIは動体撮影に特化したハイエンドカメラです。
α1のマイナーチェンジ機ととらえられがちですが、実はAF性能のみならず画質も大幅に進化しています。
「積層型センサーは高速読み出しが可能だが、画質では非積層型に劣る」という常識を覆すほどの高感度耐性やダイナミックレンジを獲得しており、特に暗所撮影ではα1からの進化を感じられるでしょう。
また、AIプロセッシングユニットによるAFはその認識能力に驚くばかり。
人や動物、乗り物など、撮りたいものが何なのかをカメラが正確に判断して、しっかりとピントを合わせ続けてくれます。
ブラックアウトフリー撮影によるファインダーの見やすさも手伝って、被写体の一瞬の動きを見逃さないフラグシップ。
スポーツ選手や動物といった、予測できない動きをする高難易度の被写体を狙うことに、きっと喜びすら感じるでしょう。
この価格帯のトピックはやはりGFX100RFではないでしょうか。
ブラックとシルバーのカラーバリエーションを統合しているという点を加味しても、「ラージフォーマットのコンパクトデジタルカメラ」という今までにないジャンルのカメラが登場したことにより、大きさや重さが原因で「中判デジタルの世界」に踏み込めなかった方にとっての有力な選択肢であったことは想像に難くありません。
そうだとしてもSONYの「1」とNikonの「8」を抑えて勝ち抜いた人気ぶりには驚きました。
総評
新品ランキングでは、FUJIFILMの強さが目立つ結果となりました。
9機種中4機種と、実に半数近くを占めているその人気の秘訣は、やはりフィルムシミュレーションとクラシックデザインでしょうか。
店頭でカメラのご案内をさせていただく際も、よくお問い合わせをいただく印象があります。
Canonは1機種と少し寂しい結果になりましたが、もう少しでランクインか!?というところまでPowershot V1が来ていました。
NikonはZ5IIやZ50IIの人気が高く、新世代(EXPEED7)機種で大きく向上したAF性能が好評です。
SONYは充実したラインアップで様々なユーザーの要望に応え、小型軽量な新世代レンズが話題となっています。
今回は惜しくもランク外となってしまったOLYMPUSはOM-3が人気、PanasonicはS1RIIがもう少しランクインという結果でした。
新品ミラーレスカメラTOP10
さて、今回ご紹介したカメラたちはその人気の為、どうしてもお取り寄せ商品が多くなってしまっております。
(ご注文いただいているお客様、早めのお渡し頑張ります!)
すぐに欲しい!とお悩みのお客様のために、コンパクトデジタルカメラを除いたミラーレスカメラのTOP10も併せてご紹介いたします!
第1位:Nikon Z5II
第2位:FUJIFILM X-M5
第3位:Canon EOS R6 Mark II
第4位:Z50II
第5位:Nikon Zf
第6位:SONY α7C II
第7位:SIGMA BF
第8位:Nikon Z8
第9位:SONY α1 II
第10位:Canon EOS R5 Mark II
惜しくもTOP10入りならず!10位以降を2機種だけご紹介!
第11位:OM SYSTEM OM-3
第12位:Nikon Z6III
ピックアップ
ここからは、ミラーレスカメラTOP10にランクインしたカメラのうち、最初のランキングに未登場の機材をピックアップしてご案内いたします。
Nikon Z50II


【紛うことなき、小さな実力者】
Nikon Z50IIはエントリ―クラスに位置しながらも上位機種「Z8」などと同様の画像処理エンジン「EXPEED 7」を搭載しており、豊かな表現力とAF性能を持ち合わせる一台です。
被写体認識AFには「鳥モード」も追加されており、野鳥撮影に挑戦したい方にもおすすめです。
被写体と向き合いながら自分らしさを色で表現することができる「イメージングレシピ」に加え、多彩な「クリエイティブピクチャーコントロール」など31種類のカラープリセットがあらかじめ搭載されているので、自分好みの色合いを簡単に作れるのでカメラデビューにもってこいの一台となっております。
SONY α7CII


【どこへでも連れて行ける本格派】
ファインダー内蔵のフルサイズ機として、驚異的なコンパクトネスを誇ったSONY α7CII。
その後継機たる本機は「AIプロセッシングユニット」を搭載したことで被写体認識が豊富になり、これまでの人物だけでなく、動物、昆虫、乗り物などさまざまな被写体を自動で認識。素早く正確にピントを合わせ続けることができます。
ボディは旧型に引き続き小型軽量で、本体はわずか514gと500mlペットボトル1本とほぼ同じ軽さ。
パンケーキレンズをマウントしクリエイティブルックを駆使すれば、本格派なコンパクトデジタルカメラのような使い方も可能です。
旅行や日常のスナップ撮影で大活躍間違いなしの、コンパクトで高性能なカメラです。
SIGMA BF


【シンプルかつ美しい】
アルミニウムインゴットから削り出される、継ぎ目のないユニボディ構造。
操作系はわずか3つのボタンと一つのダイヤル、電源・シャッターのみを配置し、直感的な操作ができます。
この洗練されたシンプルな外観と同じように撮れる写真も美しいのがSIGMA BFの特徴の一つと言えるでしょう。
fp、fpLからカラーモードを引き継ぎ、新しく追加された「RICH」は赤・オレンジ・黄色など暖色系がはっきりと出ながら、グリーンの色味も鮮やか。ビビッドのポジションかと思いきや少しそれとも違う。色鮮やかでまさにリッチな色味でした。この写真も「RICH」で撮影しており、様々な表情が出せる懐の深いカラーモードです。また、同じく追加された「CALM」は「穏やかな、落ち着いた」という意味の通り、ハイライトが抑えられ全体のトーンがふわっと浮き上がるようにナチュラル系の仕上がりになります。
カラーモードでの写真の広がりも持ちつつ、ボディは洗練された美しさが際立つ一台です。
Canon EOS R5 Mark II


【視線入力・高画素・高耐久すべてをこの一台で】
Canon EOS R5 MarkIIは先代から4500万画素の高画素を受け継ぎ、上位機種であるEOS R3、EOS R1が搭載する「視線入力AF」を搭載しており、風景写真・スポーツ撮影など多種多様に活用できます。目線を動かすだけでAFポイントが追従してくれる機能なのですが、実はフィルムカメラ時代からCanon EOS3などでも実現されていました。現代になり、追従性がさらに上がった本機はまさに自分とカメラが一体となったように感じられます。
連写性能も一級品で、電子シャッター使用時に秒間30コマを実現しあらゆるシーンで活躍できます。本体に使用されている部材はマグネシウム合金を多く採用し、耐久性も一眼レフ時代からしっかりと継承しています。一眼レフ時代から続く”5シリーズ”の最高性能を体感してみてください。
OM SYSTEM OM-3


【見た目はクラシカル。中身は現代最高性能】
OM SYSTEM OM-3はフィルムカメラ時代のOM-1をモチーフにされており、そのクラシカルさはとても趣があるデザインです。コンパクトな単焦点レンズをつけても、オールドレンズをつけてもその見た目は見る者を魅了します。
どんなファッションにもマッチするので毎日持ち歩きたくなるデザインなのですが、その一方で、実はこのクラシカルさからは考えられないほどの性能を搭載しています。
現在のフラッグシップ機であるOM-1 MarkIIと同様のAF性能・エンジンを搭載し、望遠レンズをつけての野鳥撮影などにも対応できるオールジャンルカメラと言っても過言ではありません。
Nikon Z6III


【第3世代を迎えさらに進化したマルチロール機】
Nikon Z6IIIは部分積層型CMOSセンサーを採用した、世界初のフルサイズミラーレスカメラです。
画質への影響を最小限にしながら、類まれなる高速性能を獲得しました。
明るいうえに反応の良いファインダー像、ローリングシャッターの少ない動画、光量の少ない屋内でも面白いように決まる瞳AF。
前機種であるZ6IIから大幅に進化し磨きをかけられた性能は、決して撮影者を裏切らないでしょう。
バリアングルディスプレイによる自由度の高い撮影可能になり、動画をされる方からも支持を得ています。
おわりに
SNSで話題のカメラや、通好みのツボを押さえたカメラ、そして実直に基本性能を高めたカメラと、様々な種類のカメラが火花を散らした新品ランキングとなりました。
メーカーの情熱や信念とユーザーの多様性が、良い化学反応を起こした結果と感じます。
日常を記録する相棒として、はたまた自己表現のツールとして、旅のお供として。
今までもこれからも、様々な場所で活躍し続けるカメラたち。
また次にランキングを発表するとき、どのようなカメラが並ぶのかを楽しみに待ちつつ筆を置こうと思います。
ぜひ中古ランキングもご覧ください。
















