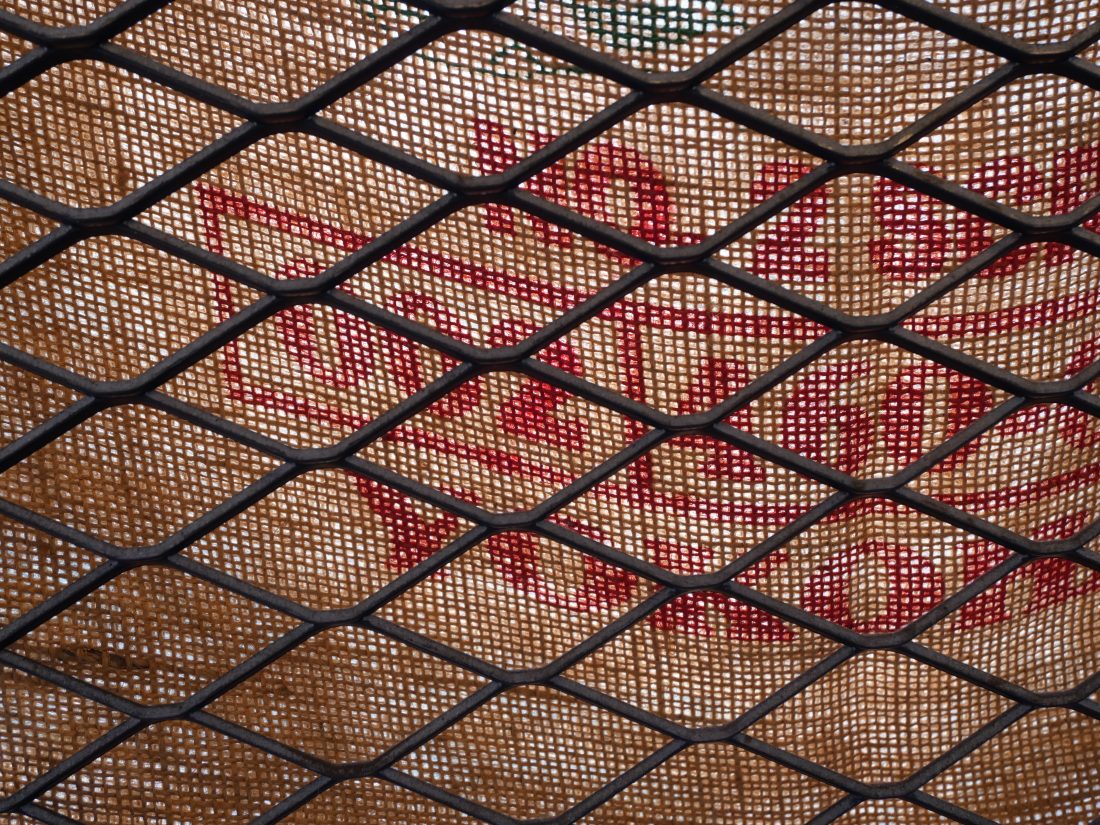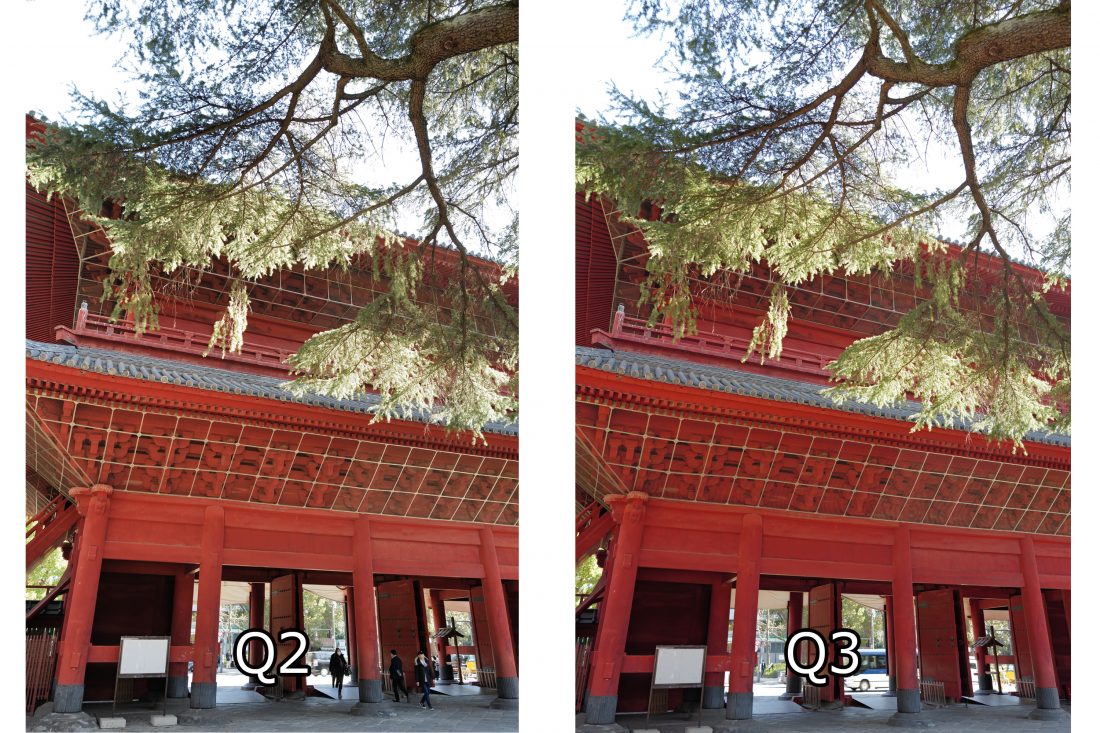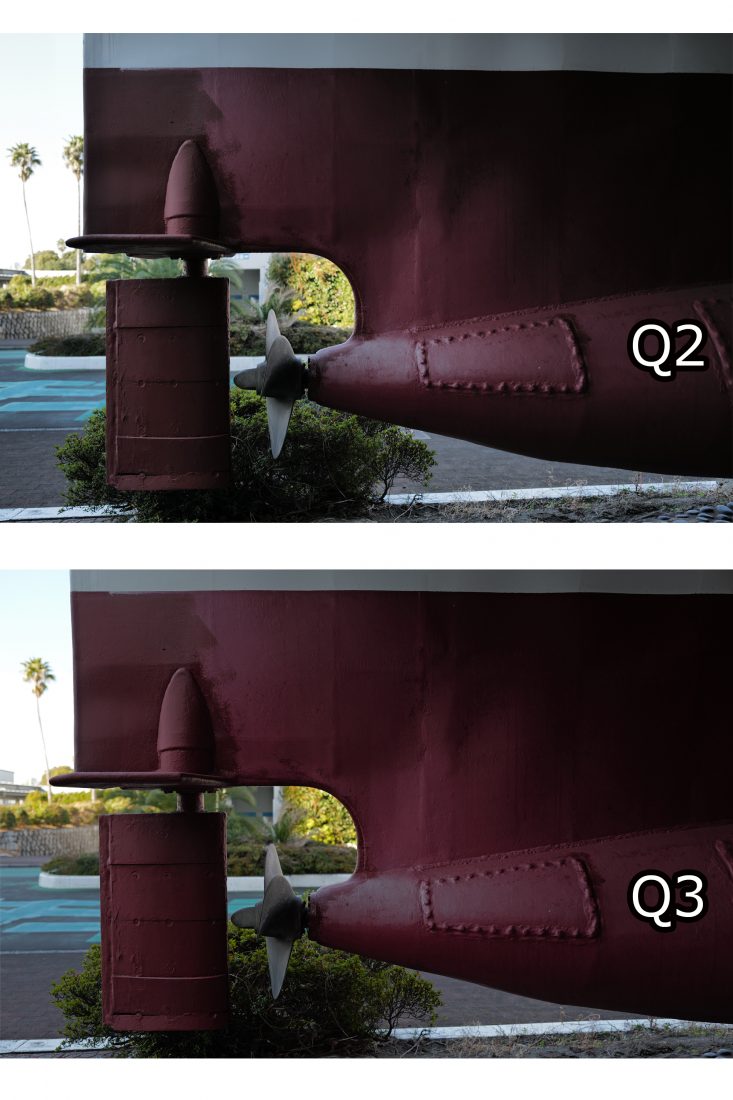OM SYSTEMから新たなフラッグシップ機「OM-1 Mark II」が発表されました。
マップカメラでは先行してYouTube動画とフォトレビューサイト Kasyapaにて作例を交えたファーストレビューを行ってきましたので、そちらも是非ご覧ください。
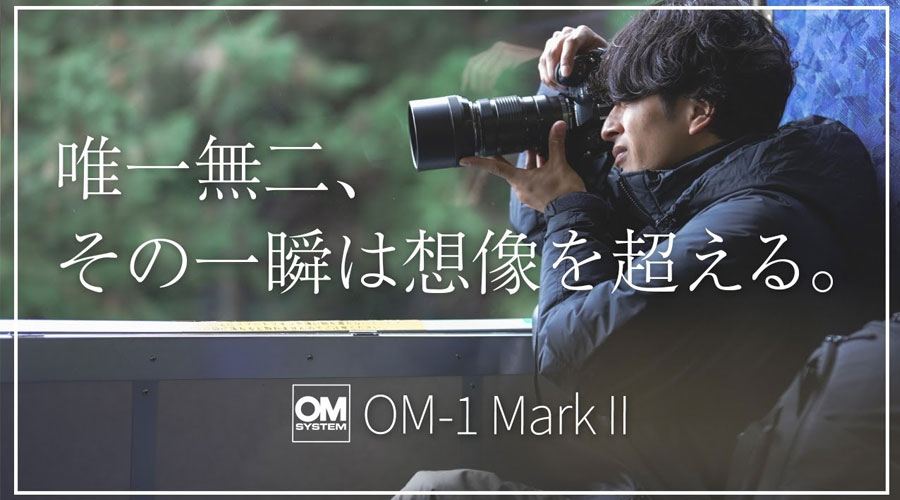
913: 質実剛健、確かな進化。『OM SYSTEM OM-1 Mark II』
筆者も幸運なことに本機を使う機会がありましたので、早速レビューしていきたいと思います。
私は元々SONYのフルサイズ機を使用しており、一眼レフから進化した「鳥瞳AF」に魅了されて以降、たまに大きなレンズをぶら下げて野鳥の撮影を行っています。
今回フルサイズ機をメインに撮影を行っている筆者がOM SYSTEM、大きく括るとマイクロフォーサーズ機の最新機種でもある『OM-1 Mark II』を使用して、フルサイズ機では味わえない魅力に迫ってみたいと思います。

オススメポイント:何と言っても「軽さは正義」
まず一番初めに感じたのが「圧倒的な軽さ」です。
今回「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」の組み合わせをメインに2~3時間ほど撮影を行ったのですが、これが本当に凄い組み合わせでメリットを上げたらキリがありません。
機動力重視のため一脚もあまり使わない筆者にとって、軽さは正義。これはマイクロフォーサーズシステムだからこその強みです。
OMSYSTEMの望遠レンズは色々と出ていますが、どのレンズもフルサイズ機では実現できない「軽さ」が大きな武器となります。
望遠系をメインに野鳥撮影や動体撮影を行う際にマイクロフォーサーズシステムはかなりメリットがあると感じました。
フルサイズ機では400~600mmクラスとなると重くて高額なレンズが多い中、手が出しやすいレンズが多いこともうれしいポイントです。

特に今回使用した「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」は35mmフルサイズ換算で300mm-800mm F4.5(更に1.25倍のテレコン付き)
このレンズをフルサイズ機で実現しようとすると、
Canonであれば「RF100-300mm F2.8 L IS USM」に「エクステンダー RF2X」という、とんでもない重装備になってしまいます。金額も軽く100万オーバー。
Nikonからは「NIKKOR Z 800mm F6.3 VR S」という銘レンズが出ていますが、明るさは「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」の方が上手です。
その他SONYの「FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS」やNikonの「NIKKOR Z 180-600mm F5.6-6.3 VR」など鳥の撮影に便利なレンズは各メーカーから発売されていますが、「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」には敵わないのではないか?と思うほど、本レンズは野鳥撮影に最高な一本。
本レンズが発売以降品薄が続くほどの人気となる理由が今回撮影していてよく理解できました。
※余談ですが300-800mmまで撮影できるズームレンズといえばSIGMAの「SIGMA APO 300-800mm F5.6 EX DG HSM」や「APO 200-500mm F2.8/400-1000mm F5.6 EX DG」を思い出してしまいます。あのサイズ感がマイクロフォーサーズの現行レンズになるとこんなにも小さく…驚愕です。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000
野鳥を撮影するにあたって明るくて軽いレンズのメリットといえば
・暗い環境下でもシャッタースピートが稼げる
・少し高い位置にいる鳥をじっくりと狙える
この2点は特に挙げたい部分です。
上記写真は早朝の薄暗い木陰にいたオナガを見上げて撮影したカットです。不要にISO感度を上げることなくシャッタースピードを上げることが出来たので、飛び立つ瞬間も綺麗に残すことが出来ました
鳥が活動を開始するタイミングを狙って撮影を行いますが、朝6~7時から撮影することも多く、冬場は特に日光が弱く薄暗い環境になりがちです。
更に木の上の高い場所にいることも多く、見上げて撮影するシーンも多いです。更に木の上にいる鳥は遠い…。
そんな環境下をすべて打破してくれるのが「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」でした。本当にこのレンズは銘玉です。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000
こちらも早朝のカット。くちばしに朝ごはんを加えてご満悦なシジュウカラ。
「OM-1 Mark II」のレビュー記事を執筆するつもりでしたが、「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」のレビューをしたくなってしまうくらい本レンズに魅力を感じてしまいました。
「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO」を最大限活用するためにために「OM-1 Mark II」を使って欲しいです。
逆に言えば「OM-1 Mark II」の能力を最大限引き出すなら「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」と言い換えられるかもしれません。
野鳥撮りマストバイレンズです。現状お取り寄せとなってしまっておりますが、前に比べるとお届けしやすくなっております。是非このタイミングにご注文をご検討ください。
「OM-1 Mark II」が発売されてから、また手に入りにくくなってしまうと思います。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 378mm(換算756mm) F4.5 SS 1/60 ISO 1600
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 378mm(換算756mm) F4.5 SS 1/60 ISO 1600
オススメポイント:常識を覆す「AI被写体認識AF」の進化
レンズについて熱く語ってしまいましたが、「OM-1 Mark II」を使って素晴らしいと感じたポイントがいくつもあります。
まず驚いたのが「AI被写体認識AF」の正確さ、圧倒的な判断能力の高さです。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※X1.25内臓テレコン使用」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/60 ISO 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※X1.25内臓テレコン使用」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/60 ISO 2000
カワセミの前に覆いかぶさる「枝」本来であれば不要物ですが、このシチュエーションが今回のポイントです。
野鳥の撮影において、今回の章の冒頭にあげた綺麗な鳥の写真のような「ベストな場所に全身が観察できる姿で野鳥がとまっている」という環境。
実際に撮影してみると分かりますが、そのような構図は非常に稀です。
木の枝や葉が生い茂った中に野鳥がいる。幾度となく遭遇するシーンです。そしてこう思ったことのあるカメラマンも多いのではないでしょうか。
「鳥の前にいる枝にピントが合ってしまう」
「家に帰ってデータを見たら枝ばかり解像している」
「ピント調整している間に逃げてしまった」
それが更に希少な渡り鳥であったり、遠くから探しにきたお目当ての野鳥だったと考えると…。
野鳥に限らず、様々な環境下で誰もが通る道かもしれません。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 335mm(換算670mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 1600
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 335mm(換算670mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 1600
枝の先に付いた種をついばむアトリ。小枝が多い環境下でも的確にピントを合わせます。凄いの一言。
「綺麗な環境下で綺麗に撮る」
だけでなく
「難しい環境下でも瞬時に撮影できる」
という事を成し遂げてしまうカメラ、それが「OM-1 Mark II」です。
 「OM-1 Mark II」+「 M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS 」+「MC-20」 800mm(換算1600mm) F12 SS 1/2500 ISO 6400
「OM-1 Mark II」+「 M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS 」+「MC-20」 800mm(換算1600mm) F12 SS 1/2500 ISO 6400
かなり遠くから葉がガサガサしている気配を察知し、新型レンズ「 M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS 」+「MC-20」を付けて単眼鏡替わりに。
半押ししながら探しているとカメラがメジロを見つけて被写体検知。ツバキの花をついばんでいる姿を収めました。このような使い方もできます。
今回様々なシーンで撮影を行いましたが、「AI被写体認識AF(鳥)」の正確さと俊敏、そして鳥を認識する速さに脱帽しました。
特に枝木が被るような環境下において、その違いは顕著に表れているように感じます。
「OM-1 Mark II」で進化した点の中に「被写体の手前にあるものにピントが引っ張られにくくなった」という項目があるのですが、野鳥撮影にとってこれはかなり大きな進化ポイント。
この機能だけでも「OM-1」から買い替えるメリットはあるように感じます。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/4000 ISO 3200
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/4000 ISO 3200
こちらはウグイス。約15cmとスズメより小柄な小鳥。
普通であればボツ写真かもしれませんが、この環境下でも即座に被写体を判別してピントを合わせる「OM-1 Mark II」の性能を感じてください。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/4000 ISO 2500
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/4000 ISO 2500
先の環境下でも被写体に食らいく粘り強さ。その結果、茂みの中を飛び交う瞬間を捉えるが出来ました。
様々な機材を使用する上で鳥瞳AFに対応した各社フルサイズ機や、OLYMPUS/OM SYSTEMの先代モデル「E-M1X」や「OM-1」も何度か使用したことがあります。
その上で「OM-1 Mark II」を使ってみて「AI被写体認識AF(鳥)」の精度、判別能力は過去一番だと感じました。
数値化できるものではなく個人的な感覚ではありますが、本機を持ち上げるために盛っているわけではなく、筆者の率直な感想です。
AI関連の技術はここ1年間の間にも劇的に変化してきていますので、その時代背景を考慮すると納得の結果かもしれません。
このAI被写体認識AFは鳥以外にも
人物 / 車、オートバイ / 飛行機、ヘリコプター / 電車、汽車 / 動物 (犬、猫)
と幅広く対応しており、今回試していませんが、機能として更に「人物」も判別可能となりました。
動く被写体については「OM-1 Mark II」かなりおすすめできます。
スポーツやポートレート、ペットなどの撮影においても真価を発揮しそうです。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 306mm(換算612mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 6400 ※等倍トリミング
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 306mm(換算612mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 6400 ※等倍トリミング
オススメポイント:決定的瞬間を撮る!「最新AF」と「プロキャプチャー」の組み合わせで真価を発揮
先に挙げた「AI被写体認識AF」は素晴らしいのですが、これと従来から人気の高い機能である「プロキャプチャーモード」が合わさると本当に今まで撮れなかった写真が簡単に撮れてしまいます。
この「プロキャプチャーモード」を簡単に説明すると「シャッターを押したら少し前の状況を撮影できる」タイムマシンをカメラの中に搭載しているような機能です。
半押しAFを行っている間の写真を本体バッファーに書き込み続け、シャッターを押した瞬間にため込んだ写真の一部をメモリーカードに保存するような仕組みとなっているのですが、バッファーや処理エンジンに負荷がかかるので、結果的にハイエンド機に多く搭載されている機能となっています。

シャッターを押したタイミングがこの位置でも…。

その直前ピントを合わせ続けていた写真が自動で保存されます。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 250mm(換算500mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 5000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 250mm(換算500mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 5000
ちょうどキセキレイの羽が平がっているカットをセレクト。決定的瞬間も逃しません。
最近ではAPS-C機やフルサイズ機においても搭載されている機種が増えてきましたが、洗練された「AI被写体認識AF」を使用してプリ撮影が出来るカメラで「OM-1 Mark II」と同様の価格帯の機種は他に存在しません。
カメラを購入する観点は様々ありますので一概にこれがよい!と断定できるものはないのですが「AI被写体認識AF」×「プロキャプチャー」を使用する環境下では間違いなく実力、コスパ共にNo.1のカメラです。

 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 250mm(換算500mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 320 ※等倍トリミング
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 250mm(換算500mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 320 ※等倍トリミング
飛び立つコサギを 「プロキャプチャー」機能にて。足元の水飛沫をトリミングしてみました。
「プロキャプチャー」モードでもJPG/RAW共に選択可能となっており、写真の画質の劣化はありません。

 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/4000 ISO 2500
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/4000 ISO 2500
飛び立つ瞬間のカワセミも撮影することができました。止まっている状態であれば飛び立った瞬間にシャッターを押し込むことで簡単に撮影することが可能です。
どちらかといえばカワセミが止まり木から飛び立つ瞬間まで1~2分のこともあれば、数分間じっとしていることもあり、飛び立つ瞬間まで粘れるかどうかが撮影の肝だと感じました。忍耐が必要です。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 306mm(換算612mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 6400 等倍トリミング
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 306mm(換算612mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 6400 等倍トリミング
飛び立つ瞬間のシジュウカラ。シャッタースピード1/3200の設定にしても羽がぶれてしますが、これはこれで躍動感が感じられ好きな写真です。
「プロキャプチャー」機能という補助があるおかげで余裕をもって撮影に挑める分、シャッターのタイミング以外にも構図やシャッタースピードなどの表現に意識を向けることも
細かい部分ではありますが、「OM-1 Mark II」より「プロキャプチャー」機能 AF/AE追従高速連写設定(SH2)で「120fps」「50fps」に加えて「16.7fps」「12.5fps」が可能になっています。
25fps以下の連写時の最低シャッター速が1/160(従来機1/320)になり、より撮影シーンや表現の幅を広げることができるようになりました。
野鳥などの撮影においてはコマ数が多いメリットが大きいですが、人物のスポーツ撮影などはコマ数が多すぎても不要なデータが量産されてしまうことも。
今回の撮影では3時間弱で200GB(8000枚)もの写真を撮ってしまったので、必要に合わせて設定を柔軟に変えられる点は嬉しいポイント。
最低シャッター速が1/160となったので、流し撮りにもより活用できるようになりました。
ちなみに余談ですが、先にも書いた通り「プロキャプチャー」機能を多用すると撮影枚数が膨れ上がります。
満足に撮影するのであれ256GB / 512GBのSDカードは用意したいところ。書き込み速度についても高速タイプのカードを使用するようにしてください。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 400mm(換算800mm) F5.6 SS 1/60 ISO2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 400mm(換算800mm) F5.6 SS 1/60 ISO2000
オススメポイント:さらなる進化を遂げた最大8.5段の手振れ補正
手振れ補正に定評のあるOMシリーズ、触れないわけにはいきません。
「OM-1」はボディ単体で7段分/対応レンズとの協調で8段分を実現していた手振れ補正が「OM-1 Mark II」における最大8.5段分の手ブレ補正に進化しています。
「手持ちで10秒、星空も撮れる」という衝撃的な内容を公式で謡っていますが、野鳥撮影においてもその恩恵を享受できます。
このカワセミの写真は800mmという超望遠の環境下で「1/60秒」という無謀な設定で撮影していますが、なんと全くブレていません。もちろん手持ち撮影、一脚使用もありません。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/250 ISO4000 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/250 ISO4000 2000
早朝の茂みに潜むカワセミ。通常の設定では真っ暗になってしまいますが、シャッター速度を落とすことで露出を確保。手振れ補正を信頼できるからこそ撮影出来た1枚です。
今回の500~1000mmという超望遠域を多用しましたが、ファインダー像が安定していたことでかなり快適に撮影を行う事ができました。
通常手振れ補正機能は夜景や低速でのブレを抑えるシチュエーションが想定されますが、望遠域の撮影においてもかなり大きな効果が期待できます。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/4000 ISO 3200
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/4000 ISO 3200
水を飲んでいたヒヨドリの頭上にカラスが飛んできて、一瞬警戒して顔を上げた瞬間のカット。足を縮めて屈伸運動をして、飛び立つ準備をしています。
手振れ補正に関係する部分の一つとして、露出を確保するためのISO感度耐性も触れなければならない要素です。
「OM-1 Mark II」については先代の「OM-1」と同じ画像センサーを搭載しているので、ISO感度によるノイズ感は大きく変わりませんが、感度を上げてもシャープな画質を維持しているように思えます。12800まで上げると明らかにノイズ感、ノイズリダクション感が出てくるので留意が必要です。
今回早朝での撮影という事もありISOは3200~6400まで上げることが多かったですが、破綻するほどのノイズは発生しませんでした。本ブログにおいてはすべての写真に撮影データを記載していますので、是非参考にしてみてください。
フルサイズ機で 800mm~1200mmでの撮影となってくると、テレコンを挟むイメージになるので合成絞り値がF11~13となることもザラ。
早朝の薄暗い環境化も相まってISO感度12800~も多用する環境の中で「OM-1 Mark II」だからノイズが多い、汚いというイメージを持つことはありませんでしたので、その点は安心していただければと思います。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 200mm(換算400mm) F4.5 SS 1/3200 ISO2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 200mm(換算400mm) F4.5 SS 1/3200 ISO2000
オススメポイント:使えば使うほど野鳥撮影に没頭。撮影が楽しくなるカメラ
最後のポイントは抽象的になってしまいますが、一番大切でもある部分「使っていて楽しい!」カメラであること。
何も気にすることなく思う存分楽しめて、一つの被写体を撮影するために没頭できる。
そんな撮影体験を叶えてくるカメラ、それが「OM-1 Mark II」です。
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 280mm(換算560mm) F4.5 SS 1/3200 ISO2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 280mm(換算560mm) F4.5 SS 1/3200 ISO2000
コサギがエビを捕まえた瞬間。小さな水滴まで逃さずに捉えます。
今まで野鳥撮影を行っていて「良い写真が撮れた!」という気持ちと同時に、あの時…あの瞬間…ピントが…という、あと一歩届かずという気持ちも生まれたことも事実です。
今回「OM-1 Mark II」を使っていてただただシンプルに「楽しい!」と思えたと同時に、あの時このカメラだったら撮れたのかな。というシチュエーションが沢山思い浮かんでしまいました。
長々と書いてしまいましたが「OM-1 Mark II」は野鳥撮影を行うにあたり自信をもってオススメできる一台となっています。
野鳥撮影のために「OM-1 Mark II」+望遠レンズを別システムで揃えてしまうのも一つの選択肢。
私も所有しているフルサイズ機と一緒に「OM-1 Mark II」を手に入れる方向で真面目に検討しています。
今まで先代のOM機を使って野鳥撮影をされている方、フルサイズ機を持っているけど興味が沸いてきた方、野鳥撮影を行ったことがない方にもおすすめです。
是非ご検討いただければと思います。
『OM-1 Mark II』各種のご購入はこちら!
当社インターネットサイトからのご注文は【ネット限定 マップカメラ2年保証】付きです。
「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」のご注文も受け付けております。
「OM-1 Mark II」の発売日以降、注文が多くなると想定されますので
お早目のご注文をおすすめいたします。
「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」の中古在庫がある場合は下記に商品が表示されます。
入荷が少ないアイテムとなっておりますので、併せてご検討ください。





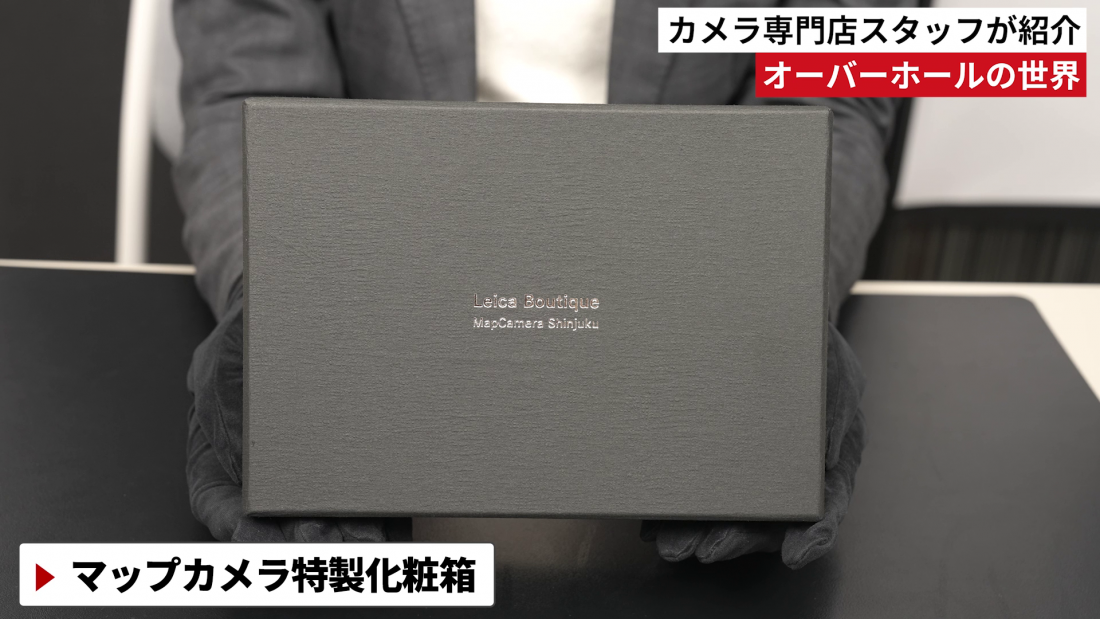


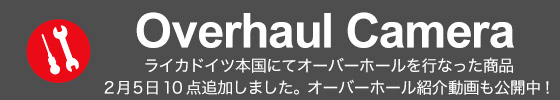
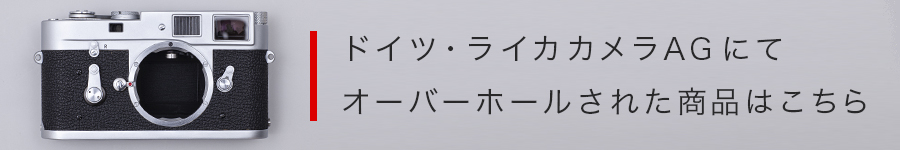
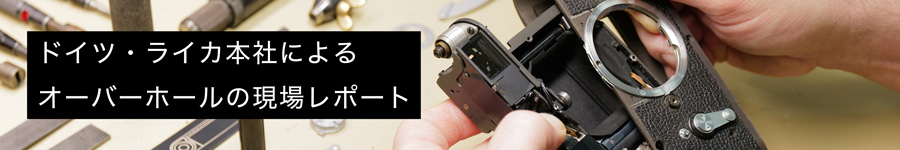





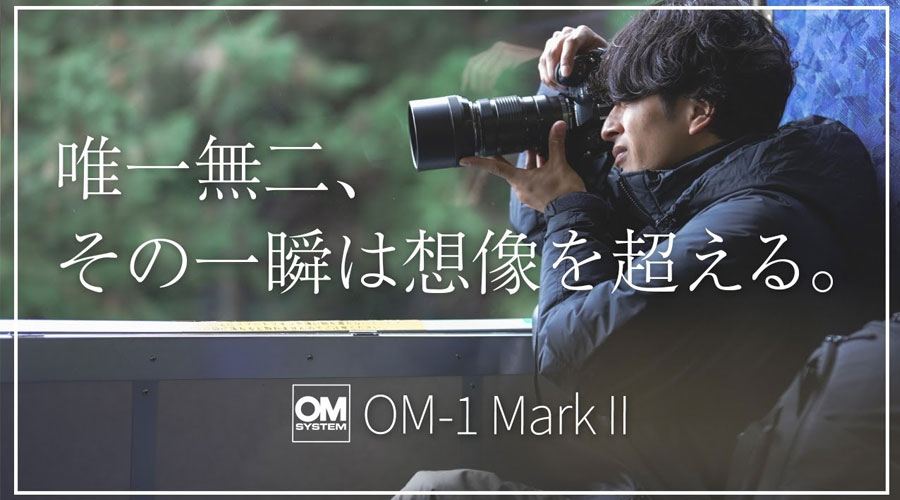


 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 263mm(換算526mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 2000 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 378mm(換算756mm) F4.5 SS 1/60 ISO 1600
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 378mm(換算756mm) F4.5 SS 1/60 ISO 1600 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※X1.25内臓テレコン使用」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/60 ISO 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※X1.25内臓テレコン使用」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/60 ISO 2000 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 335mm(換算670mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 1600
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 335mm(換算670mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 1600 「OM-1 Mark II」+「 M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS 」+「MC-20」 800mm(換算1600mm) F12 SS 1/2500 ISO 6400
「OM-1 Mark II」+「 M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS 」+「MC-20」 800mm(換算1600mm) F12 SS 1/2500 ISO 6400 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/4000 ISO 3200
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/4000 ISO 3200 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/4000 ISO 2500
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/4000 ISO 2500 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 306mm(換算612mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 6400 ※等倍トリミング
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 306mm(換算612mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 6400 ※等倍トリミング

 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 250mm(換算500mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 5000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 250mm(換算500mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 5000
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 250mm(換算500mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 320 ※等倍トリミング
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 250mm(換算500mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 320 ※等倍トリミング
 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/4000 ISO 2500
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/4000 ISO 2500 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 306mm(換算612mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 6400 等倍トリミング
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 306mm(換算612mm) F4.5 SS 1/3200 ISO 6400 等倍トリミング 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 400mm(換算800mm) F5.6 SS 1/60 ISO2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 400mm(換算800mm) F5.6 SS 1/60 ISO2000 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/250 ISO4000 2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 400mm(換算800mm) F4.5 SS 1/250 ISO4000 2000 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/4000 ISO 3200
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 500mm(換算1000mm) F5.6 SS 1/4000 ISO 3200 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 200mm(換算400mm) F4.5 SS 1/3200 ISO2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO ※TC1.25有効」 200mm(換算400mm) F4.5 SS 1/3200 ISO2000 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 280mm(換算560mm) F4.5 SS 1/3200 ISO2000
「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 」 280mm(換算560mm) F4.5 SS 1/3200 ISO2000





























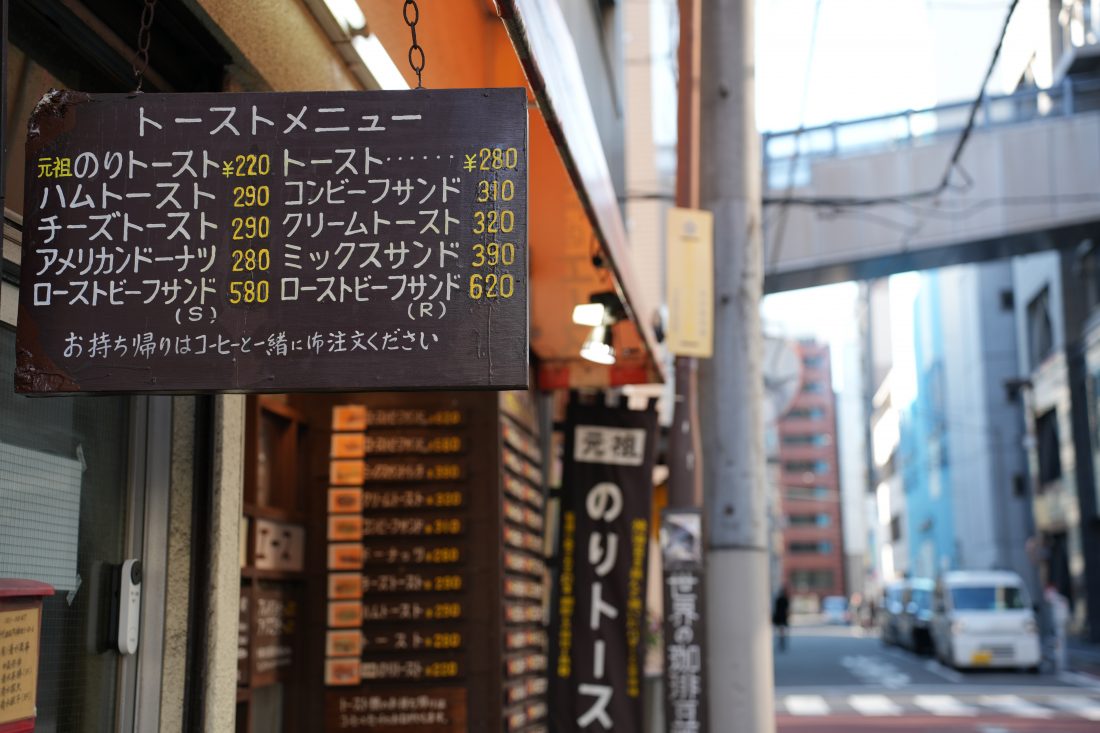









































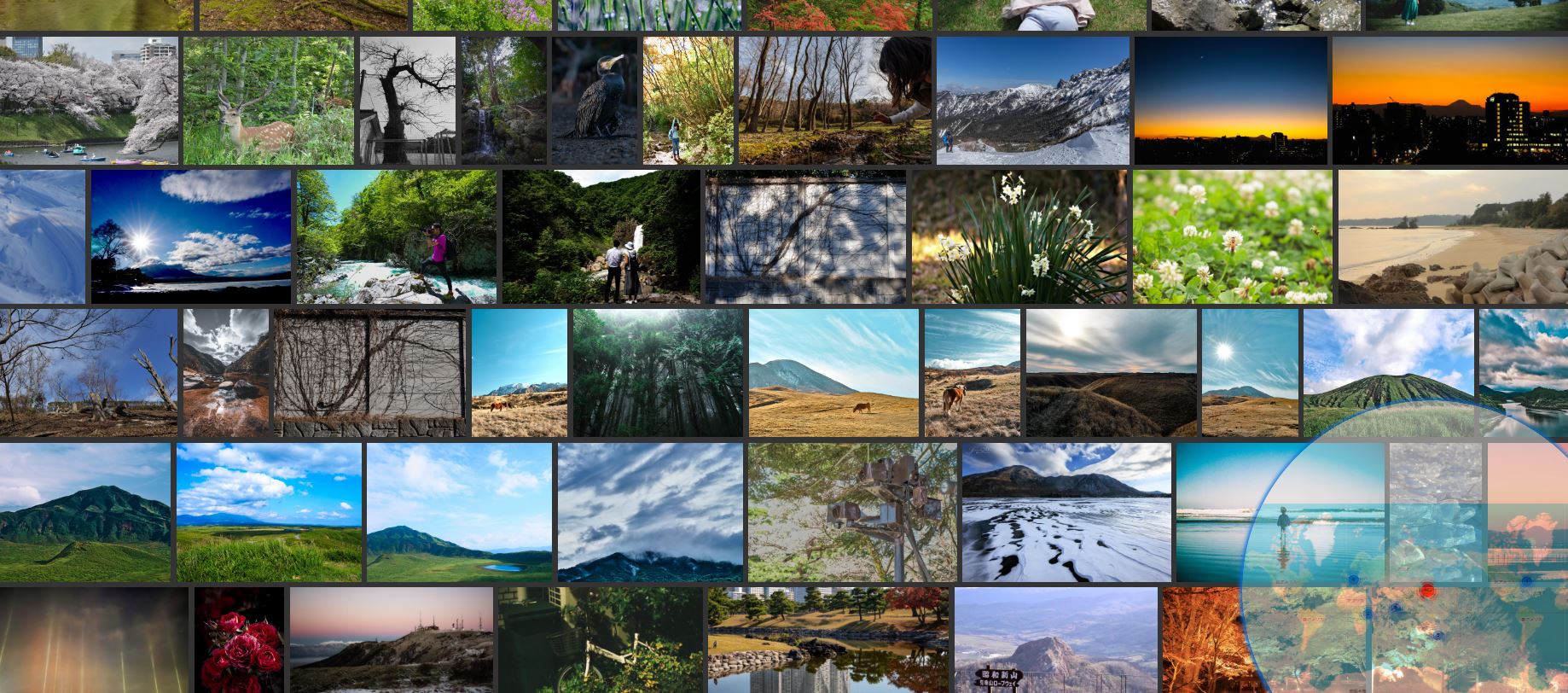





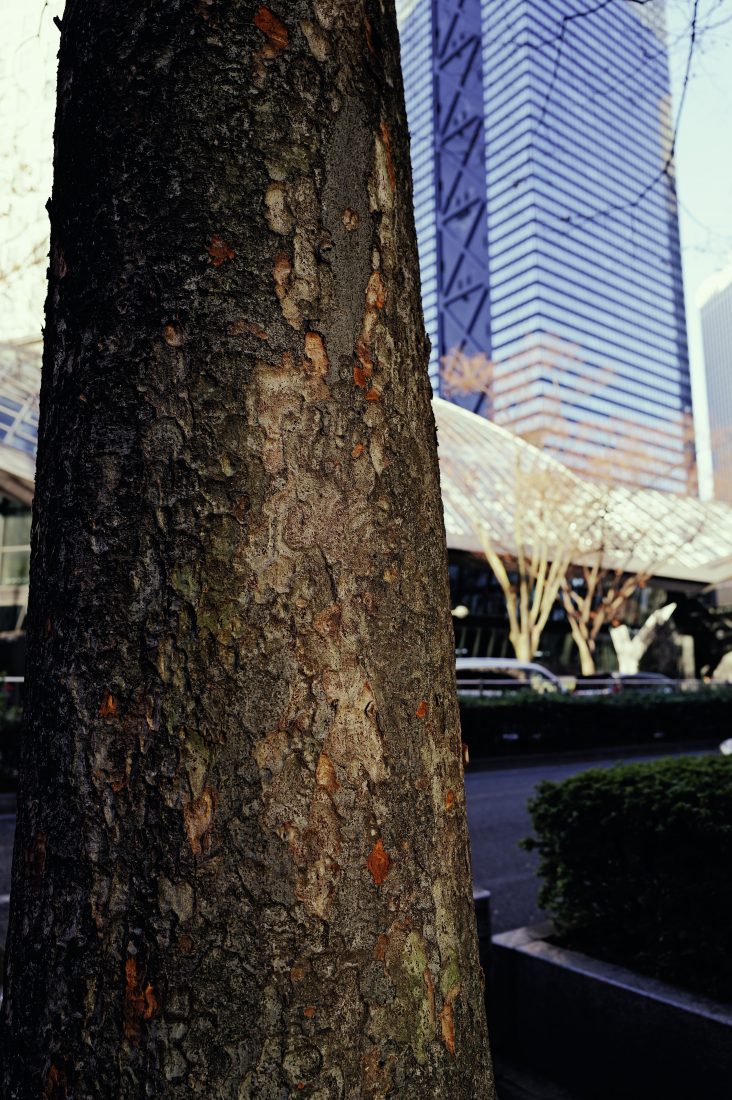

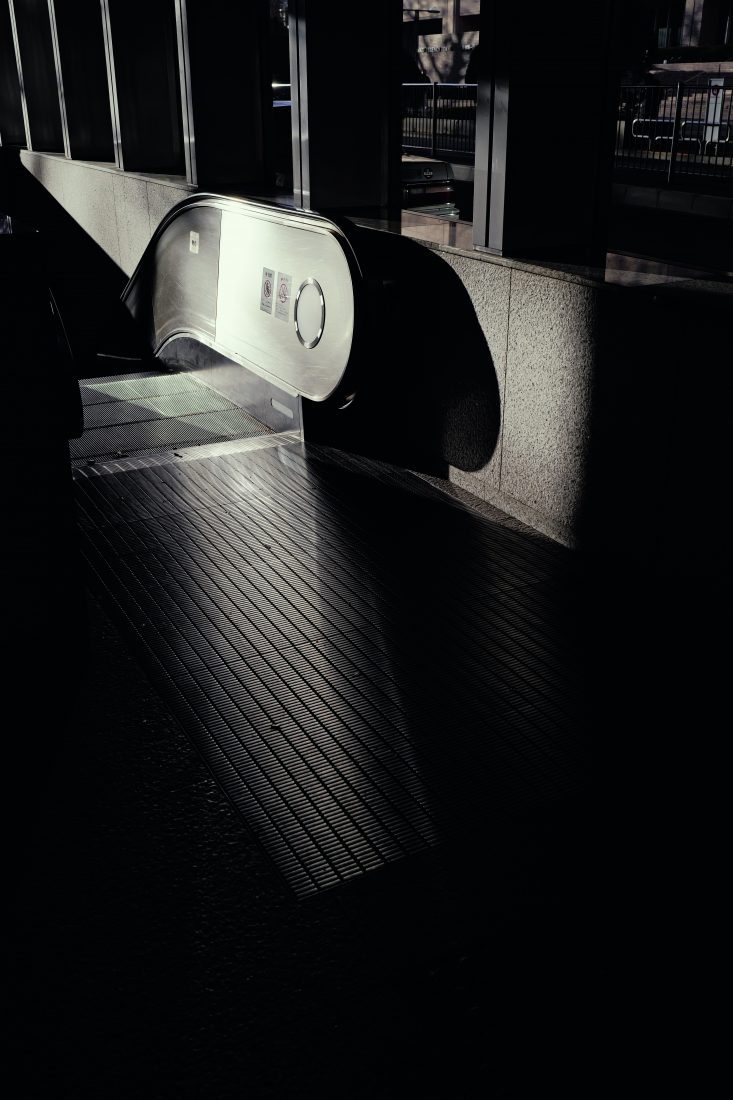

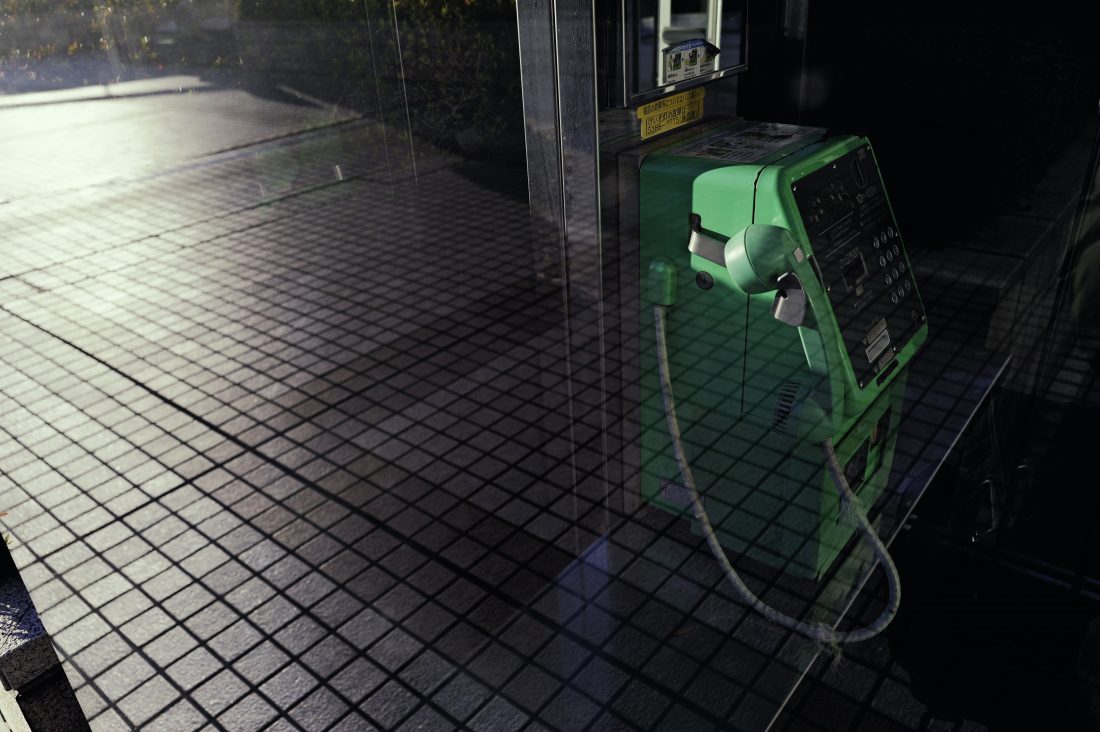
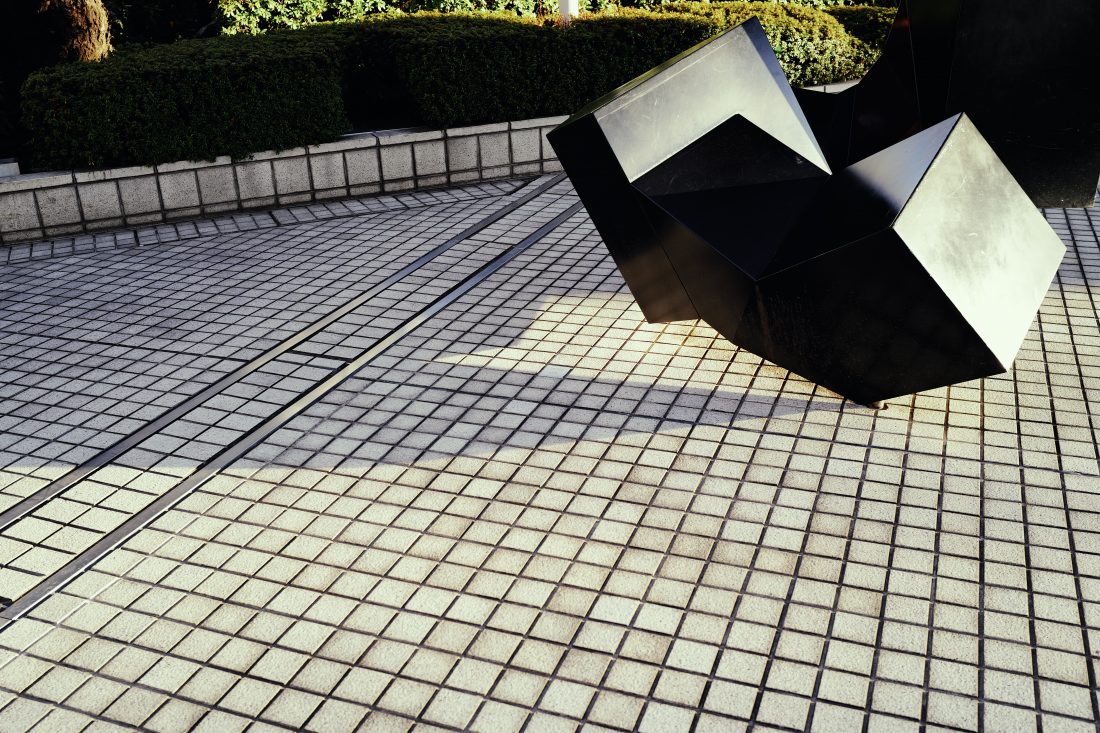




























 Canon EOS R3 + RF135mm F1.8 L IS USM
Canon EOS R3 + RF135mm F1.8 L IS USM Canon EOS R3 + RF28-70mm F2L USM
Canon EOS R3 + RF28-70mm F2L USM

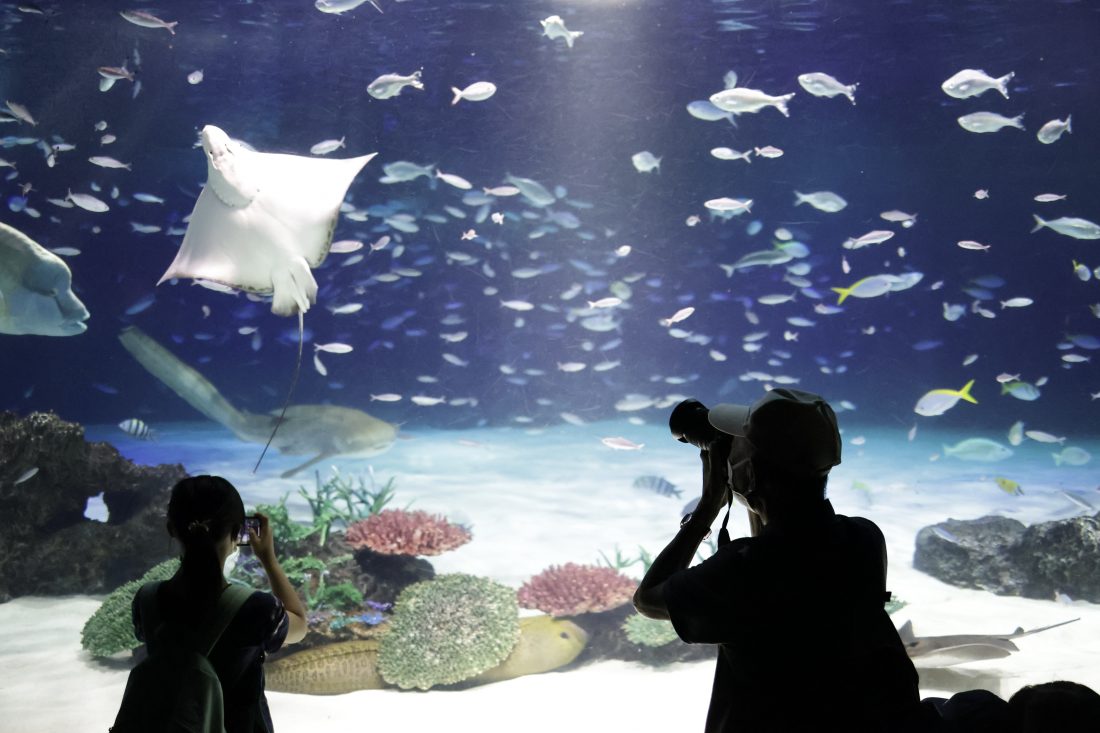 RF35mm F1.8 マクロ IS STM
RF35mm F1.8 マクロ IS STM
 Canon EOS R5 + RF50mm F1.2L USM
Canon EOS R5 + RF50mm F1.2L USM Canon EOS R5 + RF50mm F1.2L USM
Canon EOS R5 + RF50mm F1.2L USM 










 友人に窓辺に立ってもらい撮った一枚。昔のガラス特有の、ゆらぎのある感じが伝わる写真が撮れました。ボケている外の風景がまるで水彩画のように滲んでいます。
友人に窓辺に立ってもらい撮った一枚。昔のガラス特有の、ゆらぎのある感じが伝わる写真が撮れました。ボケている外の風景がまるで水彩画のように滲んでいます。
 外装のレザーにはオイルソフト
外装のレザーにはオイルソフト 裏地には、多分割型の特殊断面超極細繊維「ユニチカ ミューフェス」という高級マイクロファイバースウェードを使用。
裏地には、多分割型の特殊断面超極細繊維「ユニチカ ミューフェス」という高級マイクロファイバースウェードを使用。 紐部分にはリサイクルポリエステルコードを使用。
紐部分にはリサイクルポリエステルコードを使用。

















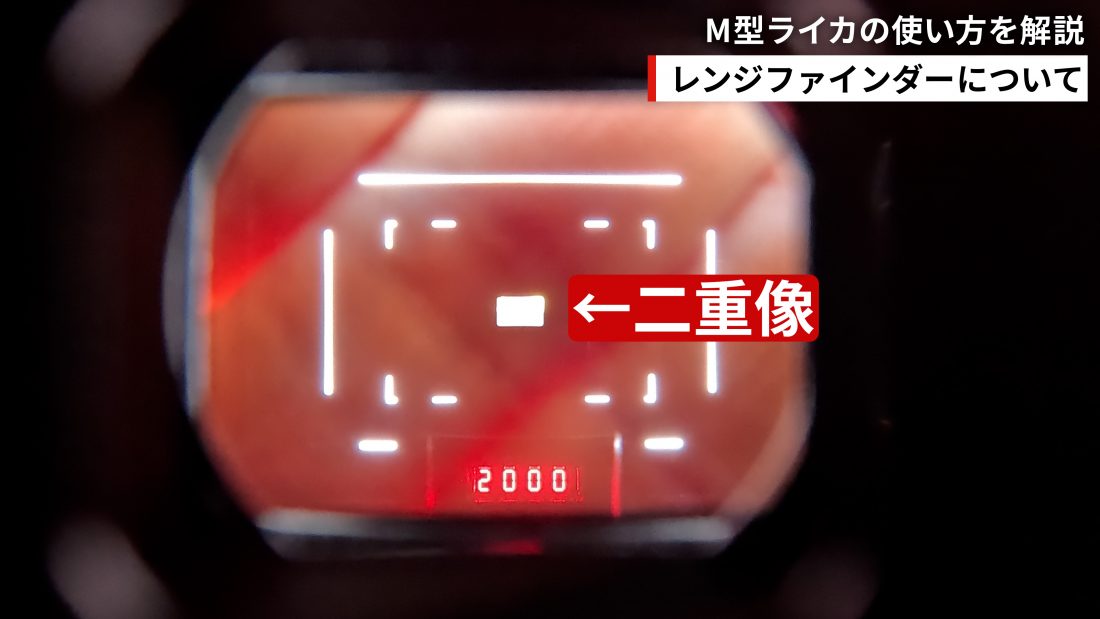


















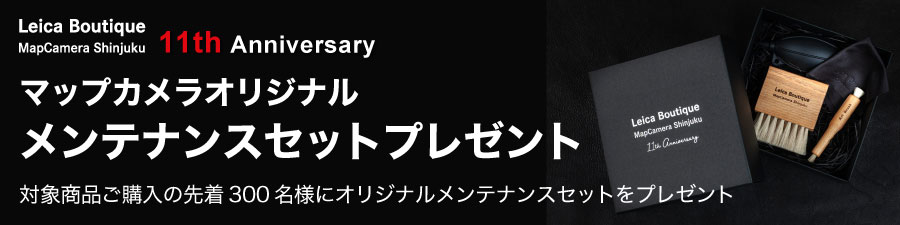

![【PENTAX】DA★ 60-250mm F4ED [IF] SDMで撮影された「旅に出たくなる写真」をご紹介!](https://news.mapcamera.com/maptimes/images/2024/01/61a02720-51be-11e8-a141-2dc04ef556b4-1536x1016.jpg)