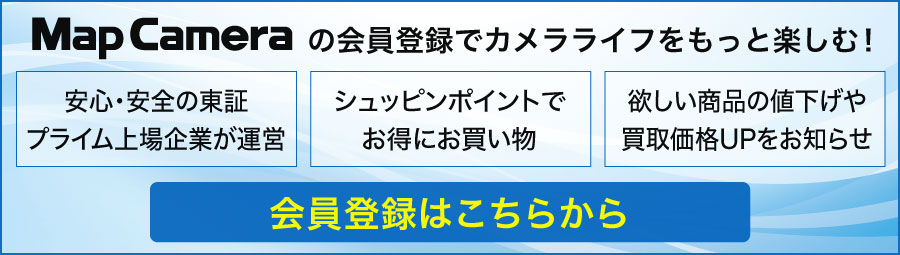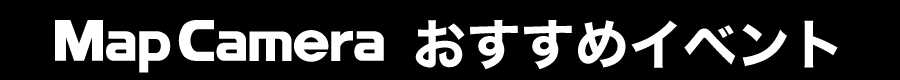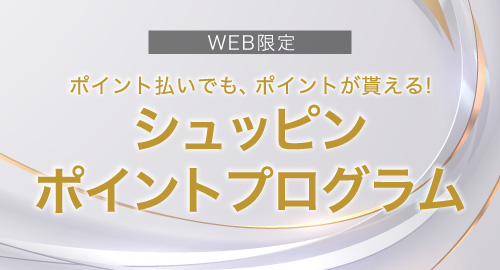【極私的カメラうんちく】第32回:超広角レンズの旅路
超広角レンズは、1950年代のレンジファインダー機や目測式のカメラから本格的な実用化が始まったが、当時はレンズを断面図で見たときに、「絞り」を挟んだ後ろ側と前側が、同じような形に作られたレンズが主流だった。後に通称ビオゴンタイプと呼ばれるこのレンズ構成は、フィルム面ぎりぎりまで設計上のレンズ配置が可能であるため、短い焦点距離のレンズを設計する上では利に適っていたといえる。
ところが、レンジファインダー機の後に台頭してきた一眼レフでは、ビオゴンタイプの設計の自由度が逆に災いして、後方に大きく飛び出したレンズがフィルムの前にあるミラーにぶつかってしまう。そのため一眼レフではビオゴンタイプのレンズが使用できなくなってしまったのである。そこで初期の一眼レフ用交換レンズには、ミラーを上げた状態(ミラーアップ)で使用する超広角レンズがラインナップされていた。本来一眼レフのミラーアップ機能は、撮影時のミラーショックによるブレを回避するためにあるが、この場合はレンズの邪魔にならないようにミラーをフォーカシングスクリーン側に固定してしまうために利用されていたのである。ミラーアップで使用する一眼レフ用の超広角レンズとしては、ニコンFマウント用として発売されていたニッコール21mmF4が有名だが、このレンズは元々レンジファインダー機ニコンSシリーズ用だったものを、ミラーアップ専用レンズとして一眼レフのFマウント用に転用したものである。
しかしミラーアップは一眼レフの機動性や優位性を大きく損なうばかりでなく、なにより測距機能が失われてしまう不便さから、ミラーアップが不要な超広角レンズの出現が切望されるようになる。実は初期の一眼レフ用交換レンズのラインナップにも、ミラーアップが不要な比較的原始的なレトロフォーカスタイプ(逆望遠型)の広角レンズが既に加わってはいたが、当時の設計手法で超広角レンズを設計するとレンズ全長が長くなり、また画角やレンズの明るさに比例して前面のレンズが大きくなり過ぎることから、28ミリ程度の焦点距離までしか実用化することが出来ずにいたのである。またレトロフォーカスタイプはビオゴンタイプに比べて歪曲(ディストーション)が発生しやすく、その補正に苦慮したこともレトロフォーカスタイプの超広角レンズの設計をより困難なものにしていた。その後、対角線画角が90度を超える超広角レンズがレトロフォーカスタイプで実用化するのは1960年代後半のことであり、システム一眼レフの出現から数えて実に10年近い月日が流れていたのである。また丁度そのころ、当時としては画期的な15ミリの焦点距離を実現したホロゴンが発明されている。ホロゴンはレンズ後端からフィルムまでの距離が殆ど無いため一眼レフに使用できず、またあまりにも特殊なレンズ構成のため「絞り」を内蔵できなかったが、わずか3枚のレンズで超広角と高解度を両立させた超広角レンズの名作である。
歪曲(ディストーション)とは広角レンズの評価の上で重要な項目だが、しばしばパースペクティブ(遠近感)がもたらす「違和感」と混同される。歪曲と広角レンズがもたらす「非現実的な遠近感」とは本来全く別のものである。完璧に歪曲を補正したレンズであってもひとたび立体的な被写体を撮影するとしばしば非現実的な遠近感をもたらすが、それは被写体が立体物であるがゆえであり、むしろレンズが正確な仕事をした結果なのである。
現在、一眼レフで使用できる最も画角が広いレンズは(フィッシュアイレンズを除くと)焦点距離12ミリをカバーしたシグマの「AF 12-24mmF4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL」と、ミラーアップで使用するコシナの「ウルトラワイドヘリアー12ミリF5.6」である。
それにしても最大画角のレンズ同士が、片やオートフォーカスズームレンズに対して片や目測式のミラーアップレンズという、「使い勝手」においてあまりに滑稽なほど両極端な組み合わせなのには思わず苦笑してしまう。その理由を問うのは愚かなことなのかも知れないが、対角線画角120度を超える特殊性がその理由のひとつとなっているのは間違いない。そして、それをかつて一眼レフが辿った一眼レフ用超広角レンズの進化形態が、半世紀に及ぶ永い旅路の末に究極の形で現代に露出した現象と考えるとき、特別な感慨を覚えるのは筆者だけでは無いだろう。