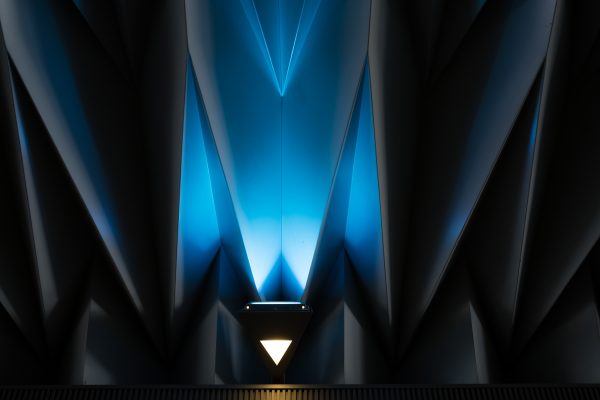【Nikon】今だからこそ、一眼レフを楽しみたい。
BEST BUY LibraryMapCamera 31st AnniversaryNikonズームレンズを楽しむフィルムカメラを楽しむ一眼レフ単焦点を楽しむ夏満喫
マップカメラの31周年創業祭がついにスタート!日頃お客様からご愛顧をいただき、今年で31周年を迎えることが出来ました。
創業祭に併せ、毎年テーマを決めてお客様に楽しんでいただけるシリーズブログを執筆していますが、2025年は「BEST BUY」がテーマです。
新しい機材との出会いは、いつも胸が高鳴るもの。しかし、選択肢が多すぎて迷ってしまうこともあります。
この「BEST BUY」シリーズは、そんなあなたの疑問や悩みに寄り添い、本当に「買ってよかった」と思える逸品をマップカメラスタッフが厳選してご紹介します。
性能、使い心地、そして所有する喜び。手に取るたびに新たな発見がある、そんな魅力溢れる製品の世界へ、ようこそ。
時はミラーレス一眼カメラ全盛。各社がミラーレス一眼の市場でしのぎを削る中、敢えて今、筆者は一眼レフカメラを使い続けています。
留まるところを知らぬ性能の向上が続くミラーレス一眼カメラですが、一眼レフカメラに惹かれるのは何故なのか。これまでに撮影した写真と共に考えていきたいと思います。

筆者のメインとするボディは「Nikon D6」。ニコンのデジタル一眼レフカメラにおける終着点、まごうことなきフラッグシップモデルです。
つい先日ついに生産完了が発表されてしまいましたが、その性能はまだまだ第一線で活躍できるもの。



まずは私のメインである被写体の動物の作例からご紹介いたします。
レンズは上から順に500mm、200mm、105mmを使用しています。
まずD6を語るうえで欠かせない点がAF性能の高さだと思います。
特に追従能力に関しては「掴んで離さない」と形容されるような強力なAFユニットを積んでおり、これは最新のミラーレス一眼と比較しても同等か、むしろまだD6のほうが優位なのではないかと思うほどです。


2つ目の特長が、暗所への強さ。
ISO感度を高く設定してもノイズの増加は最小限に留められ、またほとんど肉眼で捉えることのできないシチュエーションでもピントを合わせてくれます。ISO感度は常用で最大102400まで対応しています。これはニコンのデジタルカメラ中一番高い値です。
特に1枚目のカットでは、シャッターを切って初めて奥に魚やヒトデがいることに気がつきました。それでいてピントは中央1点に設定したところ、狙った場所に正確に合わせてくれました。
ISO感度を上げても解像感が損なわれにくいので、細かな描写が求められるマクロ域での撮影でも威力を発揮します。

そして3つ目の特長が、圧倒的な信頼性。
多少の衝撃や水滴程度であれば、撮影を続行することができます。もちろん撮影後のお手入れは必須ですが、海水の飛沫がかかってしまうような場所でも撮影ができるのは驚きです。


さてそんな圧倒的な性能を持ったD6ですが、プロの方はもちろん、写真を趣味としているすべての方におすすめしたい機種なのです。
まず圧倒的なAF性能。動体を撮らずとも、どんな状況でもピントを合わせてくれるその信頼感はスナップ撮影においても有効。
暗所の強さも、ノイズを気にせずに撮影できるのはストレスフリーです。
また大きなグリップは、重量級のレンズを装着しても抜群のグリップ感を誇ります。
そしてD6を語る上で欠かせないのがシャッターフィーリング。ミラーを高速で動かし、かつブレは抑えるという難易度の高いチューニングがされた結果、シャッターを切る際に手に伝わる感触は唯一無二になっています。「自分は今写真を撮っているんだ!」という気持ちにさせてくれるカメラです。
次に紹介しますのは、フィルム一眼レフカメラにしてニコンFマウントの初号機、Fです。

1959年に発売されたF。最初に紹介したD6とは、発売年で比較すると実に61年もの差があります。
いわばFマウントの原点とも言うべきカメラですが、プロユースを前提としたカメラなので耐久性は抜群で、未だに現役で活躍しています。
三角屋根が特徴的なボディはファインダーが交換可能です。このファインダーはアイレベルと呼ばれるもので、露出計は内蔵されていません。
フォトミックファインダーを装着することで露出計を使用することが可能ですが、このファインダーはかなり巨大で、しかも三角屋根の特徴がなくなってしまいます。
筆者はこの三角屋根が好きなので、アイレベルファインダーで撮影することがほとんどです。露出計は使用せず、勘に頼っての撮影です。

今回使用したフィルムは「FUJIFILM FUJICOLOR100」。ISO100のカラーネガフィルムです。現像を当日中に仕上げることができるフィルムは少なくなってしまいましたが、こちらは当日仕上げができる現像所が多い印象です。

フィルムカメラの特長として、ボディの薄さがあります。デジタルカメラではセンサーの後ろに基盤やモニターを置かなければならない都合上、どうしてもボディに厚みが出てきてしまいがちです。それに対してフィルムカメラではフィルム面の後ろには圧板があるのみで、その分ボディが薄くなります。カメラを持ち歩くにあたって、ボディの小ささは重要項目。実はカメラを持ち出しての散歩にフィルムカメラは適しているのです。

光の表現や粒状感、色の出方など、フィルム写真に特徴的なデジタルカメラでフィルム写真を再現しようという試みがされていますが、化学反応を利用して像を写し出す銀塩写真には、デジタルには表現しきれない空気感があると感じます。

先程D6の作例としてご紹介した巨大な狛犬をフィルムでも撮影してみました。
普段私はデジタルとフィルムの2台体制で撮影に出向くことが多いのですが、装着するレンズとして特によく使用するのが50mmです。デジタルとフィルム両方にそれぞれ50mmのレンズを組み合わせることもしばしば。撮れる画角はほとんど同じですが、その性質は全く異なるので写真は面白いと思います。

望遠レンズに付け替えても良い写りをします。
フィルムはハイライトが飛びづらいという特徴があり、石畳の質感も白が完全に飛ぶことなく表現することができます。

フィルム一眼レフカメラのFと、デジタル一眼レフカメラのD6。せっかくなのでこの機会に並べてみました。
スペックという面で見ればこの2機種は比べるのもおこがましいほどの進化を遂げていますが、その根底にあるのは、プロの使用を念頭に置いた設計思想。何が何でもシャッターを切らなければならないプロフェッショナルにとって、これほどまでに信頼できるカメラは他にないと思います。
そしてこの2機種は実はどちらも同じニコンFマウントを採用しているという共通点があります。極端に古かったり新しかったりするレンズには対応しませんが、AiタイプからDタイプまでの純正レンズは、今回ご紹介した2機種両方に対応しています。
不変と呼ばれるほどの圧倒的な互換性を持つFマウント。近年Nikonはミラーレス専用設計のZマウントへと舵を切っていますが、Fマウントもまた、これからも頼れる存在としてあり続けてくれるのです。そこにミラーがある限り。
マップカメラスタッフが選ぶ「BEST BUY」シリーズ。次回もどうぞご期待ください。