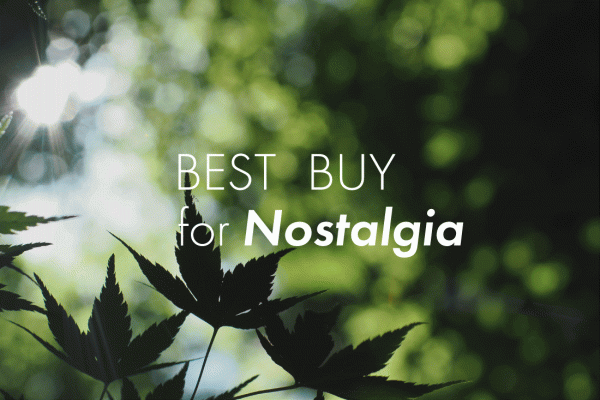【HASSELBLAD】今日は、500C/MとCFV100Cで
私は学生時代にカメラを始めてから、趣味が高じて様々なカメラを触ってきましたが、いまだに最高の撮影体験ができるカメラの一つは、HASSELBLADの500シリーズだと考えています。
フォーカシングフードを立ち上げる時の独特の金属音。
フォーカスリングを回したときに、大きなスクリーンで浮きあがってくる被写体。
シャッターを切るときのバックシャッターのバコッ!という大きな音。
巻き上げるクランクの、カリカリという感触。
そして現像後に感じる、6cm × 6cmというフォーマットの独特な立体感。
似ているカメラは数多くあれど、HASSELBLADの500シリーズからしか感じられない撮影体験があります。今回は、最近も人気継続中な500シリーズと、デジタルバック CFV 100Cを組み合わせて撮影してみました。

組み合わせたボディは、HASSELBLAD 500C/Mと、レンズにはCF 80mm F2.8。500シリーズの中では定番中の定番ともいえる組み合わせで、生産数が多いため中古市場における供給数も多く、人気なHASSELBLADの中でも比較的入手が容易です。
80mmはCFV 100Cの44mm × 33mmで使用する場合、35mm判換算で約64mm相当となり、標準からやや望遠寄りな手触りに。
しかし開放F値2.8と中判センサーの効果によって、画面に独特な立体感が生み出される印象があります。

私は過去に、907X 50Cを試用したこともあります。その時と比べて100C、すなわち1億画素となったことで描写がさらに高精細になったことに加え、カラーソリューションも進化。
ハッセルブラッド ナチュラルカラーソリューション(HNCS)と呼ばれるHASSELBLAD独自の色再現性により、より自然ながらドラマチックな描写が可能になりました。

ついついなんでもない山道の道すがら、画面の中ほどのピントを置くような構図を撮ってしまいたくなります。
ちなみに、撮影の感覚としては、ほとんど500シリーズを使う感覚と変わりません。CFV 100Cの電源を入れて、あとはいつも通り撮影するだけ。バックシャッターの開閉に合わせて自動で画像を記録してくれます。

このカットの木の表面のディテールにご注目。16bitもの色深度と、最大15ストップものダイナミックレンジにより、明暗差の激しい被写体でも丁寧に描き分けをしてくれます。

一方でマニュアルフォーカスのレンズを使う場合気を付けなければならないのがピント。今回の撮影では多くの場合ルーペを使いながらピント合わせをしており、その場合のフォーカシングは問題ありませんでしたが、気を抜いて撮影すると上記のようなカットに…。構図を吟味した結果フォーカスがおろそかになってしまいました。
しかしこういうシチュエーションでも、デジタルなら気兼ねなく再撮影できるのもよいところです。

もともとのCF 80mm F2.8のポテンシャルが高いだけあって、基本的に絞り開放での撮影でしたが、近距離から遠景まで卒なくこなしてくれました。欲を言えば、CF 60mm F3.5 などのレンズがあれば、フルサイズ換算48mm相当となり標準レンズとしての利便性が向上するかもしれませんが、こちらは生産数が80mmほど多くないためややレアなレンズとなっており、いつか試したいところ。

しかしCF 80mm F2.8も発売から50年前後経つレンズ。高性能とはいえ、描写には幾分か柔らかさも垣間見れます。その柔らかさも、現代のシャープな描写の優等生レンズにはない独特な個性として、光って見えます。
907X 100Cは、決して安いお値段のカメラとは言えません。
一方で、撮影に必要なフィルムの供給数は減少し、高単価化が進む現状。
1本あたり2,000円前後のフィルムをHASSELBLAD 500シリーズとA12マガジンで撮影可能な約12枚。もし1000カット写真を撮りたい場合に必要なフィルムの本数は約83本となり、それだけで約16万6千円もの金額に。
完全な互換とは言えないかもしれませんが、907X 100Cのデジタルバックである「CFV 100C」を使用すれば、44mm × 33mmという中判クラスセンサーを、500シリーズというヘリテージシステムで使用可能。
2025年11月2日時点のHASSELBLAD 907X 100Cの新品当社販売価格は¥1,039,500(税込)となりますので、フィルム1000カット 16.6万円と仮定した場合、6200カット撮影すれば元が取れてしまうという計算になります。
そう考えると、100万円を超えるカメラで高額!という印象も、なんだか変わって見えてくる気がしませんか?
最高の撮影体験を、現代の最高のテクノロジーでお楽しみいただくのは、今なのかもしれません。
■今回ご紹介した機材はこちら↓