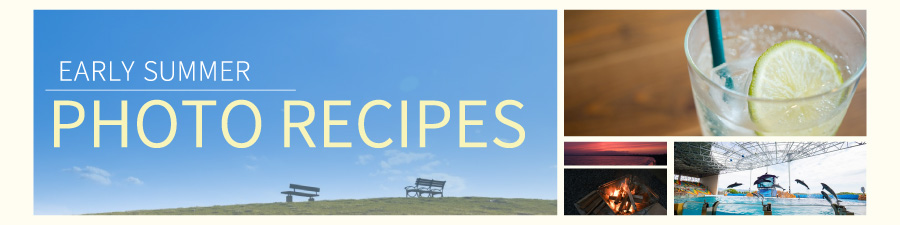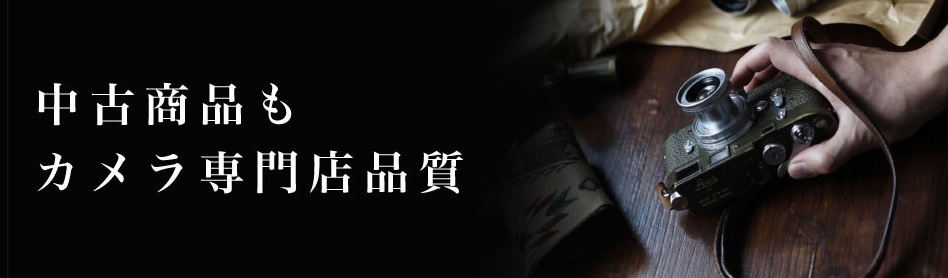スポーツ撮影・運動会に使いたいおすすめの望遠レンズ特集│メーカー別でご紹介します!
9月に入り、もう間もなくスポーツの秋、運動会シーズンに突入いたします。
運動会やスポーツの大会など、一年に一回の大切な晴れ舞台、主役であるお子様を綺麗に大きく残したい!そんなお考えをお持ちの方は多いはず。
今回はそんな大切なシーンを逃さず撮りきるためにおすすめしたい望遠レンズをご紹介させていただきます。カメラ本体も合わせてご検討中の方にも向けておすすめのカメラボディもご紹介させていただきますのでぜひ合わせてご確認ください。
○ 専門店厳選のおすすめ望遠レンズ
○ 望遠レンズにおすすめのカメラボディ
目次
望遠レンズの選び方 | 望遠の必要なシチュエーション

望遠レンズとは遠くにいる被写体を大きく写すために必要なレンズで、焦点距離を100mm以上に出来るレンズのことを一般的に望遠レンズと呼んでいます。
運動会やスポーツの大会ようなシチュエーションのほとんどは近づいて撮るというのが難しいシチュエーションだと思います。物理的に近づけないだけど被写体は大きく切り取りたい、そういったシチュエーションにおいて特定の被写体を大きく切り取るには、やはり望遠レンズがどうしても必要になってきます。
本記事では、初めて購入する方向けの望遠レンズから更なるステップアップを検討している方に向けたおすすめの望遠レンズもご紹介させていただきます。
何mmくらいの焦点距離を選ぶのがおすすめ?

望遠レンズがおすすめと言われても、各メーカーから様々な種類が発売されておりどういったものを選べばいいのか分からないかと思います。
一番人気があるのは小型・軽量のダブルズームレンズキット等に付属している50-200mmくらいの望遠ズームです。しかしながらご利用いただく環境や施設の大きさ・撮影する被写体の動き方によっておすすめしたい望遠レンズの焦点距離は変わってきます。
少し引いた写真や全身の写真など会場の雰囲気を重視した写真。
例:屋内競技の写真など。
○ 200mm~400mm
全身から半身のバストアップ。背景が強くボケるので、被写体を際立たせた撮影が可能。
例:グラウンドなどで行われる運動会など。
○ 400mm~600mm
広い屋外での半身もしくは顔のアップ。野球場の観覧席などからの撮影をするのであればこれぐらいの焦点距離がおすすめ。
例:野球やラグビーの試合など。
小学校や中学校の運動会くらいの規模感であれば300mmもしくは400mmくらいまでズームが出来るレンズであれば、使いやすく人気の高いレンズです。
野球場のスタンド席からなどの撮影となると更に望遠の距離が必要になりバストアップで特定の被写体を撮るとなると400mm~600mmもしくはそれ以上の望遠が出来るレンズが特におすすめです。
また、望遠レンズを選ぶ際は、望遠ズームレンズを選ぶことを強くおすすめします。
単焦点のようなズームが出来ないレンズはF値が明るいものが多く、画質面でも優れるレンズが多いので選ばれがちですが運動会やスポーツ撮影であれば、焦点距離を変更できる方が圧倒的に便利です。航空祭やサーキット場の特定の場所でこういう風に撮るというのがある程度決まっている方であれば、単焦点はおすすめですが初めての方や撮影する場所のロケーションが分からない・状況によって変わってしまうのであればズームの方が汎用性に優れます。
お持ちのカメラのセンサーサイズをチェック
望遠レンズを選んでいくにあたって、ご自身がお持ちのカメラのセンサーサイズをご確認いただきそれに合わせて必要な焦点距離のレンズを選んでいきます。

○ APS-C・・・1.5倍
○ マイクロフォーサーズ・・・2.0倍
例えば、400mmまでの焦点距離が必要な場合はフルサイズはそのまま400mm、APS-Cは約250mm~300mm程度、マイクロフォーサーズであれば200mmの焦点距離の選んでいただくと換算で400mm相当の焦点距離になります。
新品と中古の違いについて
レンズを購入する際に気になるのが新品と中古の差。
新製品から旧商品まで、カメラ機材は新品/中古品が溢れていて迷ってしまう事も多いと思います。マップカメラも新品/中古品それぞれ扱っておりますので、当店のサービスを基準にメリットをまとめてみました。
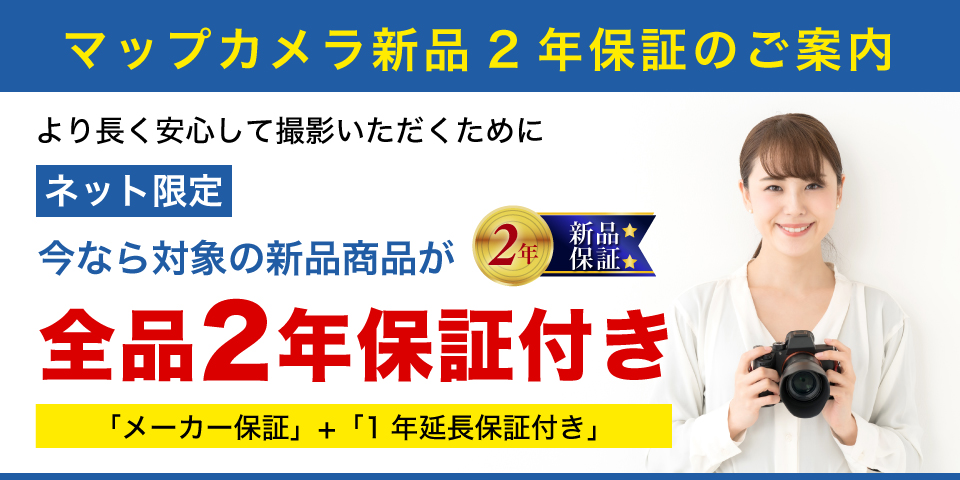
一般的なカメラやレンズについては基本1年間のメーカー保証が付いており、故障や不具合があった場合にメーカーの窓口にて修理が可能です。さらにMapCamera.comでご購入の際は通常一年保証のカメラについては追加で一年付いて合計二年の保証になっており、長く安心して使っていただけるようになっております。
○ ファーストオーナーになれる
中古とは異なり汚れや傷や使用感がなく、気持ちよく使い始めることが出来ます。
中古品のメリットは何より安く購入出来るというところが一番のメリットです。節約した分で旅行を楽しんだり、追加でレンズフィルター等の撮影機材の購入資金に充てることもできます。
○ 旧モデルを買うことが出来る
新品は基本的に最新モデルが更新された場合、その一つ前のモデルは販売終了してしまうことが多いです。中古であれば、そういった販売終了してしまった旧モデルも購入することが出来ます。ご自身の用途に合ったカメラを新旧世代から選ぶ頃が出来るのもメリットの一つ。
安くお買い得に購入できる、中古商品には多少なりデメリットは存在します。
多くの方が想像するデメリットというと、製品の不具合に関する部分であったり、保証の部分だと思います。
中古は新品と異なりワンオーナー以上の商品なので、経年使用による不具合などが起こりやすいと考えている方も多いのではないでしょうか。
ですが、そこはご安心ください!
専門の修理業者および弊社専門スタッフにて必ずメンテナンスを実施。必要に応じて部品交換や細部清掃を行っています。
例えば、レンズであれば全数点検と動作チェックを行い、撮影に影響のあるチリ・ホコリの写り込みや不具合があった場合はそれらを取り除いたのち販売させていただいております。
○ 業界屈指の1年保証付き!新品商品と同様に末永くご利用頂けます。
一般的には1か月~6ヶ月の販売店が多い中、マップカメラでは最長クラスの1年保証を実現!長期保証をお約束できるのは確かなメンテナンス品質の裏付けでもあります。
マップカメラであれば、新品・中古どちらも安心してお求めいただけます。
どちらにもそれぞれに大きな魅力がありますので、ぜひご自身の二ーズに合わせてご選択ください。
専門店スタッフ厳選おすすめ望遠レンズ|おすすめポイントを解説します!

今回おすすめさせていただく望遠レンズは高コスパ・人気モデルを選りすぐってご紹介させていただきます。
初めての方でも使いやすいかどうか、コストパフォーマンスの高い優れた製品であるかを専門店スタッフならではの視点から分かりやすくご案内いたします。
また上位モデルのへのステップアップをご検討中の方に向けてのおすすめレンズを合わせてご紹介しておりますので、合わせてご確認ください。
Canon(キヤノン)
RF100-400mm F5.6-8 IS USM

RF100-400mm F5.6-8 IS USMは、見た目こそ少し大きいですが望遠レンズの中では非常に小型・軽量なレンズで持ち運びや撮影の慣れていない方の長時間の撮影でも疲れにくい設計になっております。
APS-Cのカメラボディを組み合わせると160-640mm相当の超望遠の領域まで一本でカバー出来てしまうとても優秀なレンズです。
金額も望遠ズームの中では破格の価格設定になっており、運動会などはもちろん大きい会場でのスポーツ撮影などを撮る予定のある方はとりあえず買っておいて損はないといっても過言ではない一本になっています。
APS-Cセンサー搭載の小型・軽量ミラーレスで秒間15コマに対応した連写も可能な人気モデル
○ EOS R50
EOS R10同様小型・軽量ボディなので本レンズとの相性は抜群。これから始める方にもおすすめ出来るコンパクトな組み合わせです。
○ EOS R6MarkII
秒間40コマの高速連写に対応したフルサイズモデル。高感度に強い約2400万画素の最新センサーのおかげで強気にISOを上げて撮影することが出来ます!
RF70-200mm F4 L IS USM

RF70-200mm F4 L IS USMは、比較的狭い環境の運動会の撮影であったり、動物園での撮影といったシチュエーションに使い勝手のいい焦点距離のレンズになります。今回のメインテーマとは少し外れてしまいますが、200mmまでズームが出来るのでポートレート撮影なんかでも非常に活躍してくれるレンズです。
更にRF70-200mm F4 L IS USMは、Canonでは上位モデルのレンズとして呼称されるLレンズにカテゴリされるレンズなので画質は申し分ありません。
レンズサイズもF4通しなので極端に重たくない約700gなところも、長時間撮影していてもツラくないのでおすすめポイントです。
APS-Cセンサー搭載の小型・軽量ミラーレスで秒間15コマに対応した連写も可能な人気モデル。換算112-320mm相当になるのでモータースポーツの撮影の撮影にも使いやすい焦点距離です。
○ EOS R7
言わずと知れたEOS Rシリーズのフラッグシップ機。ハイエンドモデルのEOS R3と同等のAFセンサーを搭載しており優れた被写体検出性能で正確に被写体を検出可能です。
○ EOS R5MarkII
EOS Rの高画素対応モデル。Lレンズであれば高画素であるEOS R5MarkIIの描写性能を如何なく発揮してくれること間違いなしです。
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMは、CanonのRFマウントで一番望遠域の出る望遠ズームのLレンズです。
従来のモデルには無かった500mmまでをカバーする超望遠ズームになるので、今までもう少し寄りたくてテレコンバーターレンズなどを用いていた経験がある方にとっても、テレコンバーターレンズ無しでそのまま撮り切れてしまうようになりました。
もちろん別売のテレコンバーターレンズを使えば最大で1000mmまでズーム域を伸ばすことが可能になっているので、撮れる範囲が大幅に広がっています。
APS-Cモデルに取り付けるとなんと、テレコンバーター無しで800mmまでズームすることが出来ます。本体重量が軽くなったとはいえ2㎏弱あるので、グリップの深いEOS R7がAPS-Cではおすすめです。
○ EOS R5MarkII
約4500万画素の高画素機でもLレンズであれば、描写性能を如何なく発揮できます。またAPS-Cクロップを用いれば1700万画素の800mm相当で撮影することが可能です。
○ EOS R6MarkII
秒間40コマの連続撮影が可能なEOS R6MarkIIであれば、AIを用いたトラッキング技術と合わせて高画質でピントもしっかり合った撮影が可能です。一番おすすめ出来る間違いない組み合わせNo.1です。
SONY(ソニー)
FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS

FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSSはフルサイズ対応Eマウントの望遠ズームレンズです。
全域で解像度が非常に高く、発売から結構時間の経っているレンズですが今もなお人気を誇る定番レンズの一本です。
SONYの人気のフルサイズであるα7CII。約850gとちょっと重ためのレンズですが、α7CIIならバランスのいい組み合わせです。
○ α6400
換算で105-450mmとなり、超望遠に近い焦点距離をカバーすることが出来ます。
○ α7III
ロングセラーの人気ミラーレスのα7IIIとの組み合わせ。使いやすいので、α7IIIユーザーの方で望遠レンズお探し中の方はぜひご検討ください。
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSはSONYのAPS-C専用設計の望遠ズームレンズです。
換算105-525mm相当の超望遠の範囲をカバーしているにも関わらず、約630gの小型・軽量設計という汎用性の高さが魅力のレンズ。
レンズ内に手ブレ補正がしっかり搭載されているので、ズームをしても手ブレを気にせず安心して撮影することが出来ます。
○ ZV-E10II
換算で105-450mmとなり、超望遠に近い焦点距離をカバーすることが出来ます。
FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSは、SONYのフルサイズ用のレンズで展開されているフラッグシップのG Masterと呼ばれるグレードのレンズです。
G Masterとは高画素機で使用しても、申し分ない解像度を再現できる描写力を持ったレンズで重量は約1.4kgとミラーレスならではの軽量設計になっており手持ち撮影も簡単に行えます。
優秀な瞳AFとしっかりとその検出した瞳にピントを合わせ続けることが出来るレンズモーターを搭載しているので、動体撮影において間違いのない組み合わせ。
○ α7RV
本レンズはフラッグシップであるG Masterレンズなので、高画素機でおよそ6000万画素もあるα7RVの描写能力にもついてこれる解像力を持っているレンズです。
Nikon(ニコン)
NIKKOR Z 28-400mm F4-8 VR

フルサイズ対応でありながら広角28mmから望遠域の400mmまでという驚異の焦点距離域をカバーしている高倍率ズームレンズ。
重量は約730gと非常に小型・軽量設計で持ち歩きしやすく、荷物を減らしたいときやあまりたくさんレンズを持ち歩けない時にとても重宝するレンズです。
エントリーモデルに位置付けながらも上位モデルに引けを取らないZ5II。汎用性の高い本レンズと合わせてカメラデビューに非常におすすめな組み合わせです。
○ Z6III
部分積層を搭載した最新センサー搭載で、本レンズとの組み合わせで普段使いの撮影から動きのある望遠の要る被写体まで常時快適に撮影が可能です。
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sは、Nikonの最上位レンズであるS-Lineというシリーズに該当する望遠ズームレンズです。
Nikonならではの高い光学技術で色にじみや収差を徹底的に抑えてくれるので、全域でクリアな写真が撮影可能です。
部分積層搭載で深いグリップが安定したハンドリングを実現しているので、安定した撮影が行えます。
○ Z8
積層型センサー搭載の上位モデルであるZ8。本レンズとの組み合わせであれば撮れない被写体はほとんどないといっても過言ではありません。
○ Z5II
エントリーモデルでありながらも高い性能を有しているZ5II。本レンズだと性能を持て余すことはありませんのでおすすめの組み合わせです。
FUJIFILM(フジフイルム)
フジノン XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR

フジノン XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WRはフルサイズに換算すると105-450mm相当の超望遠レンズです。
WRと表記があるFUJIFILMのレンズは防塵防滴設計のため、防塵防滴のカメラと組み合わせれば悪天候でも強気に撮影に臨めます。
X-M5は現行モデルで最軽量の355g、ポケットにも収まるサイズ感ではありますが最新のAF技術で動体撮影もかなり優秀なのでぜひ使ってほしい組み合わせ。
○ X-T5
フジフイルムの代名詞ともいえる人気のX-Tシリーズの最新モデル。優れた被写体検出AFが搭載されており、動きのある撮影を快適にしてくれます。
○ X-H2
X-T5同様に優れた被写体検出AFが搭載されており、動きのある撮影を快適にしてくれます。ファインダーのドット数が優れている為、覗きながら撮るのがメインの方であればこちらがおすすめ。
フジノン XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR

フジノン XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WRは換算150-600mm相当の超望遠に該当するズームレンズ。
防塵・防滴仕様で重量は約1.4kgに抑えた軽量設計なので、快適に手持ち撮影が行えます。
積層センサーで7.0段の手ブレ補正。更に秒間40コマの高速連写、間違いなく安定して結果を出すことが出来る組み合わせです。
○ X-T5
普段使いを考慮してボディも軽量化を考えたい方はこちらがおすすめです。
○ X-H2
X-H2Sよりも、高画素を優先させたい方はこちら。
レンズ選びならサードパーティ製もおすすめ
レンズの選び方として、おすすめをしたいのがサードパーティ製のレンズを選択肢に入れるということ。
サードパーティ製のレンズというのは、カメラメーカーが作っているレンズとは異なるレンズを専門に作っているレンズメーカーが作ったレンズのことを一般的には指します。
後述するSIGMA(シグマ)やTAMRON(タムロン)がレンズメーカーとしては代表的なメーカーで非常に優れたクオリティでありつつも、価格をそれなりに抑えることが出来るため、長年多くのカメラマンから指示されてきました。
現在もミラーレスに対応したレンズを多く製造・販売しており、今もなおミラーレス市場では安定した人気を誇っています。今回はその中から特に人気のレンズをピックアップしてご紹介します。
SIGMA(シグマ)
Contemporary 100-400mm F5-6.3 DG DN OS

Contemporary 100-400mm F5-6.3 DG DN OSは、SIGMAから発売されている望遠ズームレンズ。
DG DNという表記が最近リリースされているミラーレス用に再設計されたモデルのことで、DG HSMという一眼レフ用の設計モデルも販売されているので購入時はご確認お願いします。
純正の望遠レンズよりかなり安価に買うことが出来るので、とりあえず望遠を一本買って使ってみたいと考えているのであればおすすめです。
○ X-T5
換算150-600mm相当の超望遠になります。かなりお手頃で純正よりも軽いので取り回しはしやすいと思います。
○ S5II
Panasonicのフルサイズセンサーのカメラ。Lマウントを採用しておりSIGMAとLeicaのLマウントを使うことが出来ます。
TAMRON(タムロン)
50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD/Model A069

50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD/Model A069は、従来の望遠ズームよりもう少し広く撮れることが可能になった新しい定番の望遠ズームレンズです。
人気の高い300mmまでに対応した望遠ズームの多くはワイド端が70mm前後のものが多く、標準域として使うには少し不便でした。本レンズはそんな「もう少し」に応えてワイド端が50mmになり望遠撮影も標準域の撮影も一本の可能になりました。
ハーフマクロに対応で寄りも引きもこれ一本で対応出来てしまう上に本体重量は670gと非常に軽量。運動会やスポーツの撮影はもちろんのこと、ご自宅等の屋内でのペット撮影も出来てしまいます!
APS-Cセンサー搭載のファインダー搭載モデル。換算で75-400mm相当になるので、望遠ズームとして非常に使い勝手のいい焦点距離になります。
○ VLOGCAM ZV-E10II
α6400同様、ちょっとレンズが大きい印象を受けるとは思いますが持ちやすく扱いやすい望遠ズームレンズ。レンズ側に手ブレ補正が入っているのでテレ端でも安心して使えます!
○ α7CII
SONYの人気フルサイズモデルの第二世代。小型ながらグリップが深いので持ちやすさ◎
18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD/Model B061

※APS-Cセンサー専用設計の為、フルサイズに使用する際は自動でクロップされます。
18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD/Model B061は換算27-450mm(RFは換算28.8-480mm)の高倍率ズームレンズ。
標準域から望遠域まで幅広く一本で対応出来るレンズで、付けっぱなしに出来るレンズとして非常に人気の高いレンズです。APS-Cのカメラをご利用いただいているユーザーの方はもちろんカメラをご購入検討の際に普段使いから動物園や運動会様々なイベントに対応させたいとお考えの方はこのレンズを選んでおけば間違いありません。
唯一の懸念点は重量が640g前後とAPS-C専用設計のレンズとしては少し重ためなところ。ですが、以下のおすすめカメラボディとの組み合わせであれば、比較的グリップが深めなのでそこまで不便は感じません。
EVFが搭載されていないモデルですが、第二世代になりバッテリーの大型化に伴いグリップも大きくなりました。そのおかげでこういったちょっと大きめなレンズでも持ちやすくなっています。
○ Z50II
Nikonのカメラはグリップの深いモデルが非常に多く、特にZ50IIはNikon上位モデルに匹敵するほどグリップが深く設計されているのでこのレンズとの相性はとてもいいと思います。
○ EOS R10
ある程度グリップは深く持ちやすさを損なわず、全体的に小さく収まってくれるので小さめのカバンにも収まってくれるサイズ感。
50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD / Model A067

50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD / Model A067は上記で紹介した50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD/Model A069よりもさらに望遠域に特化させた望遠ズームレンズです。
重量は約1.2㎏と少し重ためのレンズではありますが、望遠域をさらに求める方には非常におすすめしたい一本です。
最大撮影倍率は50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD/Model A069と同じく50mm側でハーフマクロに対応しているので、サイズ感にさえ目をつむることが出来れば普段使いにも持って来いな便利な望遠ズームレンズです
大きめのグリップでサイズ感のバランスが非常にいい一台。優秀な人物/動物瞳AFが搭載されているので運動会やスポーツ撮影も快適なること間違いなしです。
○ Z8
Nikonの人気上位モデルとの組み合わせ。高画素機でも申し分ない解像力を発揮出来るので安心しておすすめ出来る一本です。
○ Z50II
換算で75-600mmという超望遠に出来てしまう組み合わせ。航空機など、どんなシチュエーションでも幅広く対応出来ます。
まとめ │ 関連記事のご紹介
今回は、運動会にスポーツ撮影に使いたいおすすめの望遠レンズをご紹介させていただきました。
上記用途以外にも、飛行機やモータースポーツ、動物園や野生生物の撮影など望遠レンズは様々な撮影シーンで活躍してくれる汎用性の高い定番のレンズです。
昨今はカメラの性能も向上しており、カメラのAI技術等を用いて簡単に被写体を検出してくれる機能も追加されているので、始めやすい環境になってきています。
新しいレンズとの出会いは、これからの毎日をもっと楽しくしてくれるはずです。
この記事であなたにピッタリな望遠レンズに出会えることを、願っています。
また、本記事以外にも初めてのカメラ選びやカメラを選んだあとのレンズ選びなど、カメラライフを充実させる関連記事をご紹介させていただきます。ぜひ合わせて読んでみてください。

これからカメラを始める方に向けてカメラの選び方とおすすめのカメラを9選、専門店スタッフが厳選した記事はこちらから確認出来ます。

カメラのステップアップをご検討中の方向けに初心者~中級者の方おすすめのカメラを16選ご紹介しております。
こちらの記事もぜひ合わせて確認してみてください。

もっと小型で、もっとコンパクトでもっと遊びが欲しい。そんなカメラをお探しの方はぜひコンパクトデジタルカメラをおすすめします!
カメラをお持ちの方でも、ちょっと手に取ってみたくなるような小さいカメラを。本格的な高画質ではなく平成レトロを感じるようなエモい写りをしてくれるカメラを厳選してご紹介。
『PHOTO RECIPES』では撮影したいシーンに合わせたおすすめ機材もご紹介しています。目的に合った一台を選ぶヒントに、ぜひご覧ください。