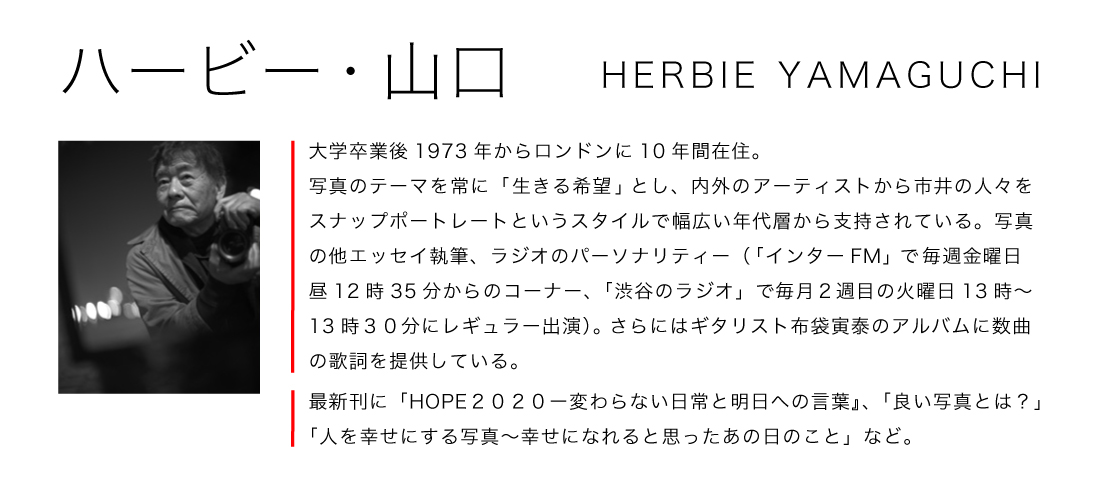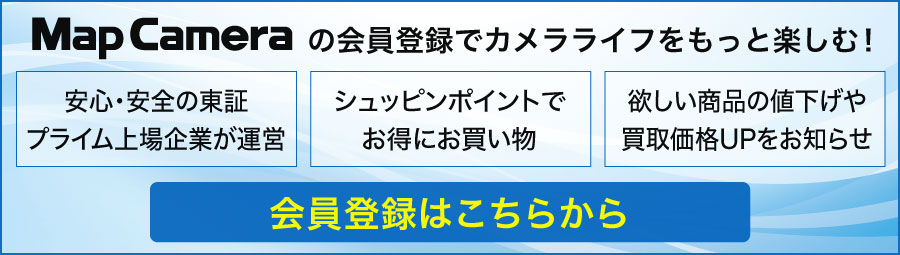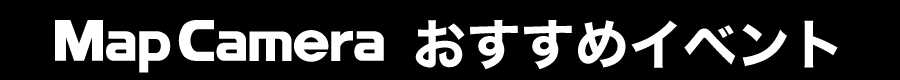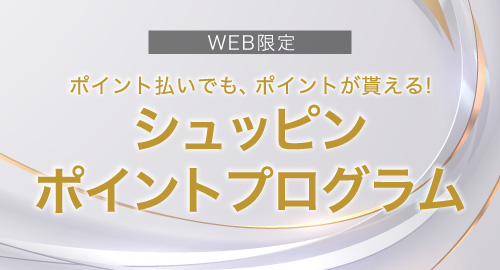【特別版】写真家:ハービー・山口『It’s only August』
2022年08月20日
35mm50mmAPO SUMMICRONKernLeica M10-PLeica M11Leica Special ContentsNoctiluxRodenstockハービー・山口写真家

俳句には季語がある。
写真にも季語があって良いのだと思う。
私なりの季節の解釈がある。
「春は希望が写り、夏には色気が写り、秋には寂しさが写り、そして冬には人の背中に人生が写る。」
いささかキザな言葉をお許しいただきたい。私はこうした気持ちを持って、それぞれの季節に向かってシャッターを切っている。

イギリスに住んでいた1979年、8月の終わりだった。ロンドンのチェルシーという高級住宅街の一角で開かれたパーティーに行ったことがある。芝生の庭があり、白い瀟洒(しょうしゃ)な家が、その家のオーナーの社会的ステータスを物語っていた。
誰かに見せたいと思って、キャビネの大きさのプリントを10数枚、箱に入れて持って行った。私より少し若いかと思われる女性が近くにいて、その彼女とビールで乾杯したのをきっかけでプリントを見せた。パトリシアという名前で、薄い生地でできた黒いワンピースを着て、長い髪を一つにまとめて背中に垂らしていた。彼女は見終わったプリントを私に戻し、「あなたにはこんな写真が撮れるんだから羨ましいわ!」と言って褒めてくれた。
お世辞であっても私には嬉しい一言だった。近くにはテムズ川があって、この庭には涼しい風が吹き抜けていた。パトリシアに季節のことを話してみた。「先週、レディング・フェスティバルに行ったんだけど、日中は暑くて、観客は裸でビールを飲みながらバンドの声援を送っているんだ。夕方になると急に気温が低くなってさ、あっという間に暗くなってしまうんだ。今年の夏はもう終わりかと思うと寂しくてね…」

2022年の今でこそ、夏は例年になく40度を超える猛暑で辟易(へきえき)としているが、私がイギリスに住んでいた当時、夏の気温は30度を超えることはほとんどなく、湿度も低くサラサラとした空気だった。夏はとても心地のよい季節だった。しかし、それは長く続かず、9月の声を聞くと、あっという間に日照時間は短くなり、またあの暗く長い冬に突入してしまうのだ。イギリス人はこの短い夏を貪るように公園や自宅の庭に出て、全身を日差しにさらし、短い夏を楽しむのだった。
パトリシアのグラスに僕のグラスを重ねて言った「寂しい夏の終わりのパーティー…」。するとパトリシアは微笑んで「It’s only August」との言葉を返した。この人はどこまでも物事をポジティブに受け止める性格らしい。「Only August~まだ8月なんだから、まだ寂しがらなくても大丈夫だから」か…彼女の巧みな言葉を頭の中で繰り返した。
僕はこの頃29歳、ロンドンに渡り6年が過ぎ、一度も日本には戻っていなかった。この先僕はいつまでロンドンに住んで、そして写真家として花咲く日が来るのだろうか?そんなことを思うと気分が落ち込んだ。「落ち込み〜ディプレッション(depression)」だった。このパーティーで出会ったパトリシアの短い会話は、僕にとって救いだった、元気をもらった。

秋になり何度か彼女から電話があった。世間話をして電話を切った。「会いたくなったら僕から電話するからさ」その会話が最後だった。ディプレッション(depression)はまだ続いていて、その後も僕から彼女に電話をすることはなかった。僕は彼女に寂しさしか与えられなかった。
「黒いワンピースと束ねた長い髪…夏には色気が写り、秋には寂しさが写る」。前述した季節のこだわりはこうしたロンドンの体験から来たものだった。

2022年、かつてのロンドンの夏とはまるで違う、猛暑にうだるヨーロッパの夏、そして日本の夏だった。ライカM10PとM11にアポズミの50ミリやノクティルックス、何本かのオールドレンスを付けて東京を歩いた。
私が手に入れたノクティルックスは1978年製だ。このレンズが作られた一年後、チェルシーでのパーティーで僕はパトリシアに出会ったのだった。
中目黒、代官山、原宿、強い夏の日差しの中で、元気に闊歩する若い世代にレンズを向けた。突然のスコールのような激しい雨が降ってきた。皆んなコンビニの屋根の下に避難した。

そして地方に出かけた時にはホテルの窓から見下ろす風景を撮った。

京都でのトークショーの帰り、新幹線はほぼ満席に近かった。夏休みの旅行や帰省からの東京に帰る人々だった。「写真を撮っても宜しいですか」「えーっ!旅の後で、顔が疲れきてっているから、恥ずかしい!」「ハービーさん!△△会社の〇〇です。田舎から東京に戻りました、偶然に同じ新幹線だなんて!」様々な偶然や成り行きがあった。

コロナの陽性者も多く、さらに猛暑の夏の真っ最中だったが、出会う人々は元気な姿を見せてくれていた。
夏というとあのパトリシアと出会った夏を思い出す。僕が29歳だった。あれから43年が過ぎてしまった。僕はいまだに地球がどう変化しても、年を重ねてもカメラと共に生きている。

それにしても街で見かける日本の若者たちは素敵になった。英国に行ったばかりの時は、英国人の美しさに惚れ込んだものだが、40年が経った今、日本の若者たちは決して引けを取らないカッコ良さを手に入れた。ここ数年は企業も学校も髪の毛を染めることに寛容になったのだろうか。かつて黒一色だった髪は明るく染められてとても美しい。

原宿の交差点で、ちょうど8月の長い日差しが、信号待ちをしている女の子たちの毛先を程良く輝かせていた。風が吹き抜けるとなおさら美しい群集だ。信号が青になると、皆一斉にそれぞれの方向に急ぎ足で去ってしまう。
そんなに急がなくたって良いのに。もっと長く君たちの美しさを僕に見せてよ!だが時は止まらない。だから僕はその美しい一瞬を写真に撮って永遠に残そうとしているんじゃないか。君たちは街という舞台の完璧な主役なんだから…

いつか僕の写真の中に自分の姿を見つけることがあったら、君たちの誇りにして欲しい。僕は君たちの明日の幸せを祈ってシャッターを切っているんだから、何か良いことがきっと起こるぞ…
戦争はいらない、一人一人が得意なこと、人の役に立つことを見つけて精一杯生きたら!人々はもっと輝くんだ。

僕はこの先もずっと変わらず目の前の人にレンズを向けていくことだろう。1979年のあの頃、パトリシアに寂しさを与えてしまった様なことはもうしないつもりだ。写真を通して人々にポジティブな元気を与えたい。
夏の終わりに、カメラを持って街に出てシャッターを押すたびに思い出すあの一言、「It’s only August〜寂しがらなくても大丈夫だから」