日頃よりマップカメラをご利用いただき誠にありがとうございます。
今回はマップカメラのスタッフが日々運営している公式インスタグラムのご紹介をさせていただきます。
最愛のカメラを皆々様にご紹介する為のアカウント。その名も「自機自賛」
今回、The Map Timesでご紹介させていただくのは、毎週水曜日に投稿される「スタッフコーデの日」です。
カメラ好きのスタッフが、撮影に出かける際、季節やカメラに合わせてどんなファッションで出かけているかをご紹介しています。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨春¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
 『Leica M5 × Leica ズマリット L50mm F1.5』
『Leica M5 × Leica ズマリット L50mm F1.5』
Leica M5、1971年から1975年にかけて製造されたM型ライカの1機種。
ライカで初めて露出計を内蔵したフィルムカメラです。大ぶりなレトロ柄のワンピースと合わせています。
 『Leica ゾフォート』
『Leica ゾフォート』
FUJIFILMのinstax miniと互換性のあるのインスタントカメラです。
カラーリングの種類が多いのでファッションアイテムの一つとして持ち歩いています。
 『FUJIFILM X-S10 × XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS×ARTISAN&ARTIST ピンドットコードストラップ』
『FUJIFILM X-S10 × XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS×ARTISAN&ARTIST ピンドットコードストラップ』
ARTISAN&ARTIST のストラップは頑丈で、ファッション性も高くカメラもオシャレも楽しみたい。
そんな富士フイルムユーザーからも人気の声が高いブランドです。
 『SONY α6400 × E18-135mmF3.5-5.6 OSS』
『SONY α6400 × E18-135mmF3.5-5.6 OSS』
だんだんと暖かくなってピクニック日和。ピクニックのお供に選んだのは、軽いのにAF機能がとても優秀なSONY α6400。
手荷物を増やしたくないお出かけにオススメのセットです。
 『Rollei ローライフレックス 3.5F(プラナー)』
『Rollei ローライフレックス 3.5F(プラナー)』
二眼レフカメラは、独特のデザインからノスタルジックな雰囲気が漂い、オールドカメラファンの間で長く愛されてきました。
こんな愛らしいフォルムのカメラをぶら下げて緑の中を歩けば、あなた自身が絵になる存在に!
お洒落に写真撮影を楽しみたい方におススメの1台です。
==pick up==
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨夏¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
 『RICOH GR III』
『RICOH GR III』
究極のスナップシューターを目指して主要デバイスを一新したハイエンドコンパクトデジタルカメラ
写真の商品は限定カラーのデコレーションリングが付属されております。中古だからこそ手に入る商品です!
 『SONY RX100V』
『SONY RX100V』
0.05秒の高速AFと定評のある大型1.0型センサーを搭載した、高性能、高画質コンパクトデジタルカメラです。
ちょっとしたお出かけに+αでいかがでしょうか?
 『FUJIFILM X-T30 × XF 35mm F2 R WR』
『FUJIFILM X-T30 × XF 35mm F2 R WR』
X-T30のカラー展開はブラック・シルバー・チャコールシルバーの3種類あります。
ご自身の服装に合わせてカラーをチョイスするのもおすすめです。
 『OLYMPUS PEN E-PL10×14-42mm EZレンズキット ホワイト』
『OLYMPUS PEN E-PL10×14-42mm EZレンズキット ホワイト』
オシャレなデザインで、持っているだけで気分が上がるカメラ。
サイズ感もコンパクトで見た目もファッションも同時に楽しめる一台です。
 『SONY ZV1シューティンググリップキット』
『SONY ZV1シューティンググリップキット』
SONYの大人気なVlogカムです。被写体を際立たせるボケみを実現してくれます。
思い出や日常をVlogに残して、特別な毎日にしてみませんか?
 『SONY α6400 パワーズームレンズキット ブラック』
『SONY α6400 パワーズームレンズキット ブラック』
小さくても写りはさすがのミラーレス一眼レフです。高速AFでポートレートや動画撮影にオススメです。
==pick up==
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨秋¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
 『Leica SL2 × Noctilux M50mm F1.2 ASPH. ×Mレンズアダプター ライカMレンズ/ライカSL・TLボディ用』
『Leica SL2 × Noctilux M50mm F1.2 ASPH. ×Mレンズアダプター ライカMレンズ/ライカSL・TLボディ用』
世界で初めて非球面レンズを採用した伝説のノクティルックスM50mm、約50年の時を経て復刻版が登場。
幻想的な写りはそのままに解像力を向上させた究極の逸品です。服装はラフに、ライカを使いこなしましょう。
 『 SIGMA fp × Contemporary 45mm F2.8 DG DN』
『 SIGMA fp × Contemporary 45mm F2.8 DG DN』
ジャケットのポケットにも収まるSIGMA fpとレンズキットになっている45mmのセット。コロンとした「ましかく」な雰囲気が素敵な逸品です。
威圧感の無いシンプルな形なので、服装や場所を選ばず馴染んでくれます。
 『 FUJIFILM X-S10 × フジノン XF23mm F2 R WR』
『 FUJIFILM X-S10 × フジノン XF23mm F2 R WR』
小型軽量なカメラセットです。
35mm相当(35mm判換算)の焦点距離と明るい開放F値2.0のレンズでスナップからアウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
 『SONY α7Ⅳ × SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN』
『SONY α7Ⅳ × SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN』
12/17に発売したα7Ⅳ、バリアングルになってさらに使いやすくなりました。
日常の風景をミラーレス画質で綺麗に残してみませんか?
 『FUJIFILM X-S10 × フジノン XF 35mm F1.4 R 』
『FUJIFILM X-S10 × フジノン XF 35mm F1.4 R 』
18種類の「フィルムシミュレーション」が搭載されているX-S10。ちょっとしたお散歩から、待ちに待った長旅も、お出かけのお供に選ぶだけで自分の世界観をいつでもどこでも楽しめます。
 『SONY a7III × CONTAX Planar T*50mm F1.4 MM』
『SONY a7III × CONTAX Planar T*50mm F1.4 MM』
2018年に発売されてから現在も定評のあるSONY a7III。マウントアダプターを使って、CONTAX Planar T*50mm F1.4 MMを装着しています。
優しい雰囲気もシャープな描写も得意なレンズです。
==pick up==
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨冬¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
 『Leica Q(Typ116) ブラック』
『Leica Q(Typ116) ブラック』
ズミルックス28mmf1.7 ASPH.を搭載したフルサイズコンパクトカメラ。
28/35/50mmの画角が選べるデジタルクロップで様々な場面や被写体に対応できます。
ライカのレンズでマクロ、AF撮影が楽しめる点も魅力です。
 『OLYMPUS PEN E-P7 × M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8』
『OLYMPUS PEN E-P7 × M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8』
キラキラと輝く街とふわふわのかわいいお洋服にぴったりのカメラ。
コンパクトで少しクラシカルなデザインが乙女心をくすぐります。
 『α7RIV ボディ ILCE-7RM4A × 縦位置グリップ VG-C4EM × 50-500mm F5-6.7 DiIII VC VXD A057S』
『α7RIV ボディ ILCE-7RM4A × 縦位置グリップ VG-C4EM × 50-500mm F5-6.7 DiIII VC VXD A057S』
野鳥を撮りに新宿某所へ…
α7RIVには縦位置グリップを付け、ホールド性と操作性をアップして使っています。
 『CONTAX T3』
『CONTAX T3』
京セラ・コンタックス製のコンパクトフィルムカメラです。コンパクトなT3であれば撮りたいと思った時にいつでも取り出して使えます。
寒い日に持ち出すとチタンのボディがキンキンに冷え、ポケットの中で温めるひと時も愛おしいと思わせてくれるカメラです。
 『SONY α7RⅡ × Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z』
『SONY α7RⅡ × Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z』
高画素機とZeissの組み合わせとは思えないほど気軽に撮影が楽しめます。
お気に入りのストラップをつけることにより、カメラがまるでファッションの一部かのように馴染んでくれました。
 『Leica M4 50JAHRE × ズマロン M35mm F2.8 × IROOA 12571 レンズフード × シルクコードストラップ京紫 』
『Leica M4 50JAHRE × ズマロン M35mm F2.8 × IROOA 12571 レンズフード × シルクコードストラップ京紫 』
Leica M4 50JAHREはA型ライカ発売から50年を記念して1975年に1750台生産された限定モデルです。
マップカメラオリジナルカラー京紫の別注ストラップ。M型フィルムカメラにも小柄なデジタルカメラにもおすすめです。
==pick up==
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
今回ご紹介させていただいた投稿の他にも、新製品のご紹介や、オススメの商品など様々なコンテンツを配信しております。
こちら@jikijisan_mapcameraをクリックして頂くと、インスタグラムのページが開けます。
是非ご覧ください。













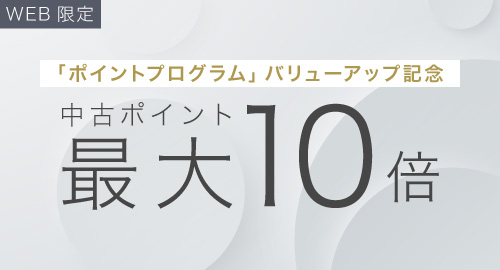



















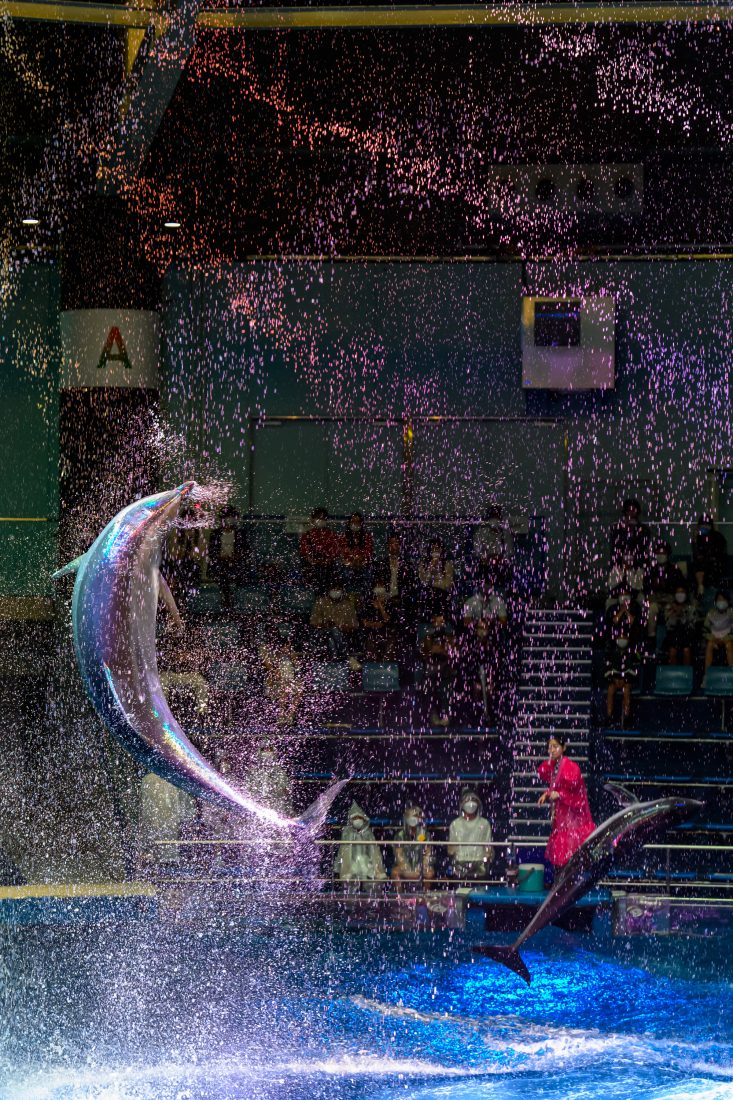



 まず1点目は「MCON-P01」から拡大性能と画質向上を行い、レンズフィルター径 φ37mm、φ46mmに対応したマクロコンバーターレンズである「MCON-P02」です。
まず1点目は「MCON-P01」から拡大性能と画質向上を行い、レンズフィルター径 φ37mm、φ46mmに対応したマクロコンバーターレンズである「MCON-P02」です。


 中央付近のふわふわな部分にめいっぱい近付いてみましたが、一見どの部分かわからないほどです。
中央付近のふわふわな部分にめいっぱい近付いてみましたが、一見どの部分かわからないほどです。
 装着前はアクセサリーを飾ったトレイや机の部分まで写っていますが、装着後はネックレスのトップ部分だけをクローズアップして撮影できました。装着しただけでマクロレンズのように撮影出来るのでちょっとした小物撮影に重宝すると思います。
装着前はアクセサリーを飾ったトレイや机の部分まで写っていますが、装着後はネックレスのトップ部分だけをクローズアップして撮影できました。装着しただけでマクロレンズのように撮影出来るのでちょっとした小物撮影に重宝すると思います。
 また別のアクセサリーも最短撮影距離で撮影してみました。実際装着すると写りはどうなるのかと思いましたがよく解像してくれています。
また別のアクセサリーも最短撮影距離で撮影してみました。実際装着すると写りはどうなるのかと思いましたがよく解像してくれています。
 指輪も装着前だと集めてもぽつんと寂しい印象ですが、装着後はここまで大きく写せます。
指輪も装着前だと集めてもぽつんと寂しい印象ですが、装着後はここまで大きく写せます。











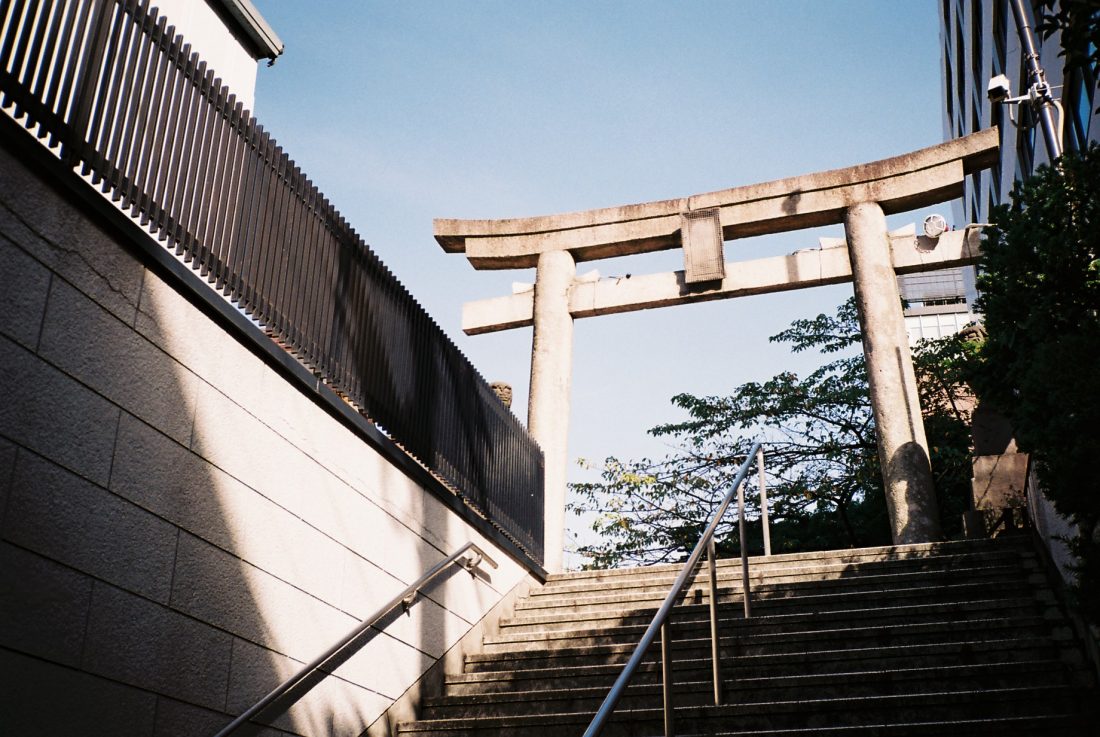





























 『Leica M5 × Leica ズマリット L50mm F1.5』
『Leica M5 × Leica ズマリット L50mm F1.5』 『Leica ゾフォート』
『Leica ゾフォート』 『FUJIFILM X-S10 × XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS×ARTISAN&ARTIST ピンドットコードストラップ』
『FUJIFILM X-S10 × XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS×ARTISAN&ARTIST ピンドットコードストラップ』 『SONY α6400 × E18-135mmF3.5-5.6 OSS』
『SONY α6400 × E18-135mmF3.5-5.6 OSS』 『Rollei ローライフレックス 3.5F(プラナー)』
『Rollei ローライフレックス 3.5F(プラナー)』 『RICOH GR III』
『RICOH GR III』 『SONY RX100V』
『SONY RX100V』 『FUJIFILM X-T30 × XF 35mm F2 R WR』
『FUJIFILM X-T30 × XF 35mm F2 R WR』 『OLYMPUS PEN E-PL10×14-42mm EZレンズキット ホワイト』
『OLYMPUS PEN E-PL10×14-42mm EZレンズキット ホワイト』 『SONY ZV1シューティンググリップキット』
『SONY ZV1シューティンググリップキット』 『SONY α6400 パワーズームレンズキット ブラック』
『SONY α6400 パワーズームレンズキット ブラック』 『Leica SL2 × Noctilux M50mm F1.2 ASPH. ×Mレンズアダプター ライカMレンズ/ライカSL・TLボディ用』
『Leica SL2 × Noctilux M50mm F1.2 ASPH. ×Mレンズアダプター ライカMレンズ/ライカSL・TLボディ用』 『 SIGMA fp × Contemporary 45mm F2.8 DG DN』
『 SIGMA fp × Contemporary 45mm F2.8 DG DN』 『 FUJIFILM X-S10 × フジノン XF23mm F2 R WR』
『 FUJIFILM X-S10 × フジノン XF23mm F2 R WR』 『SONY α7Ⅳ × SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN』
『SONY α7Ⅳ × SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN』 『FUJIFILM X-S10 × フジノン XF 35mm F1.4 R 』
『FUJIFILM X-S10 × フジノン XF 35mm F1.4 R 』 『SONY a7III × CONTAX Planar T*50mm F1.4 MM』
『SONY a7III × CONTAX Planar T*50mm F1.4 MM』 『Leica Q(Typ116) ブラック』
『Leica Q(Typ116) ブラック』 『OLYMPUS PEN E-P7 × M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8』
『OLYMPUS PEN E-P7 × M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8』 『α7RIV ボディ ILCE-7RM4A × 縦位置グリップ VG-C4EM × 50-500mm F5-6.7 DiIII VC VXD A057S』
『α7RIV ボディ ILCE-7RM4A × 縦位置グリップ VG-C4EM × 50-500mm F5-6.7 DiIII VC VXD A057S』 『CONTAX T3』
『CONTAX T3』 『SONY α7RⅡ × Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z』
『SONY α7RⅡ × Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z』 『Leica M4 50JAHRE × ズマロン M35mm F2.8 × IROOA 12571 レンズフード × シルクコードストラップ京紫 』
『Leica M4 50JAHRE × ズマロン M35mm F2.8 × IROOA 12571 レンズフード × シルクコードストラップ京紫 』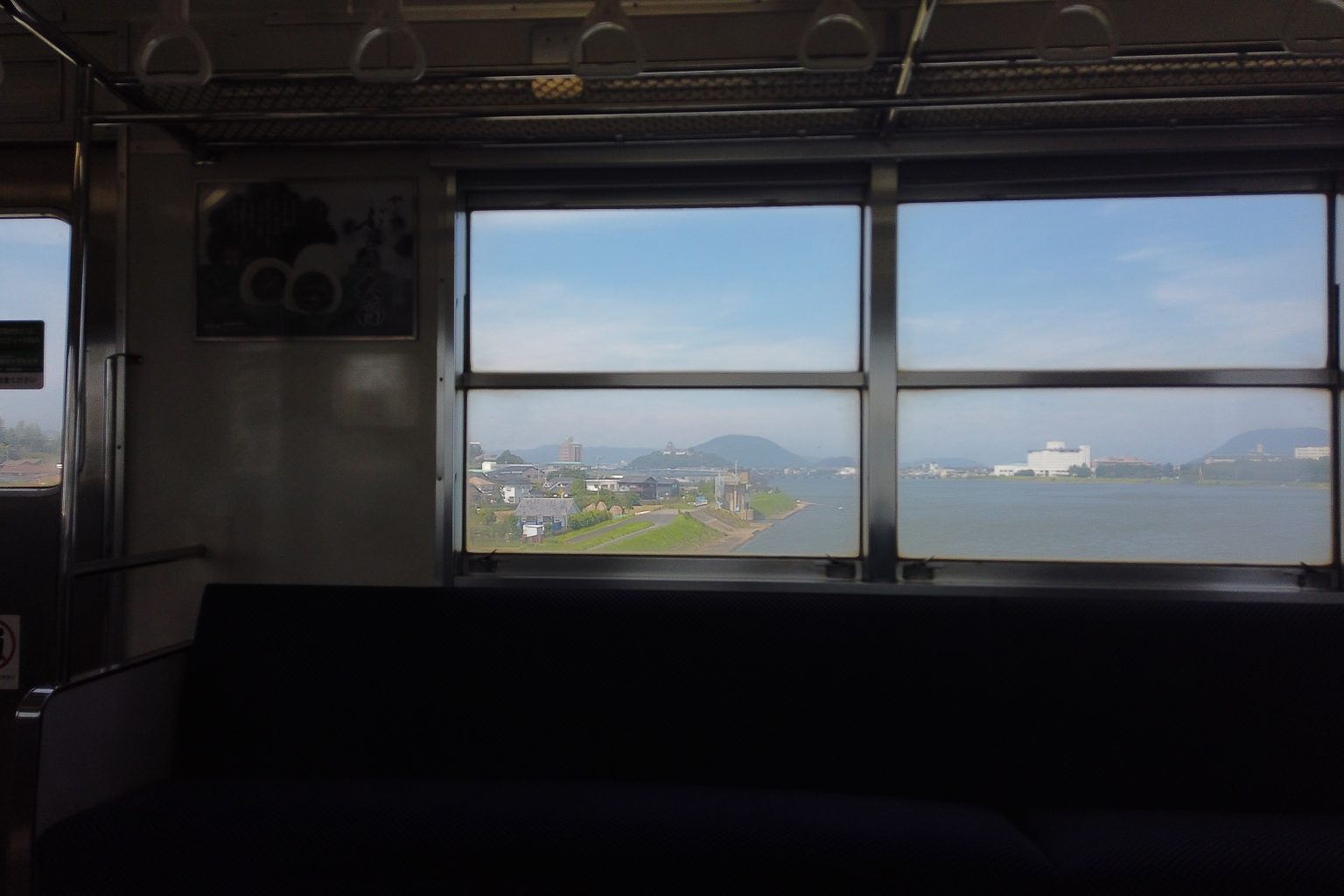

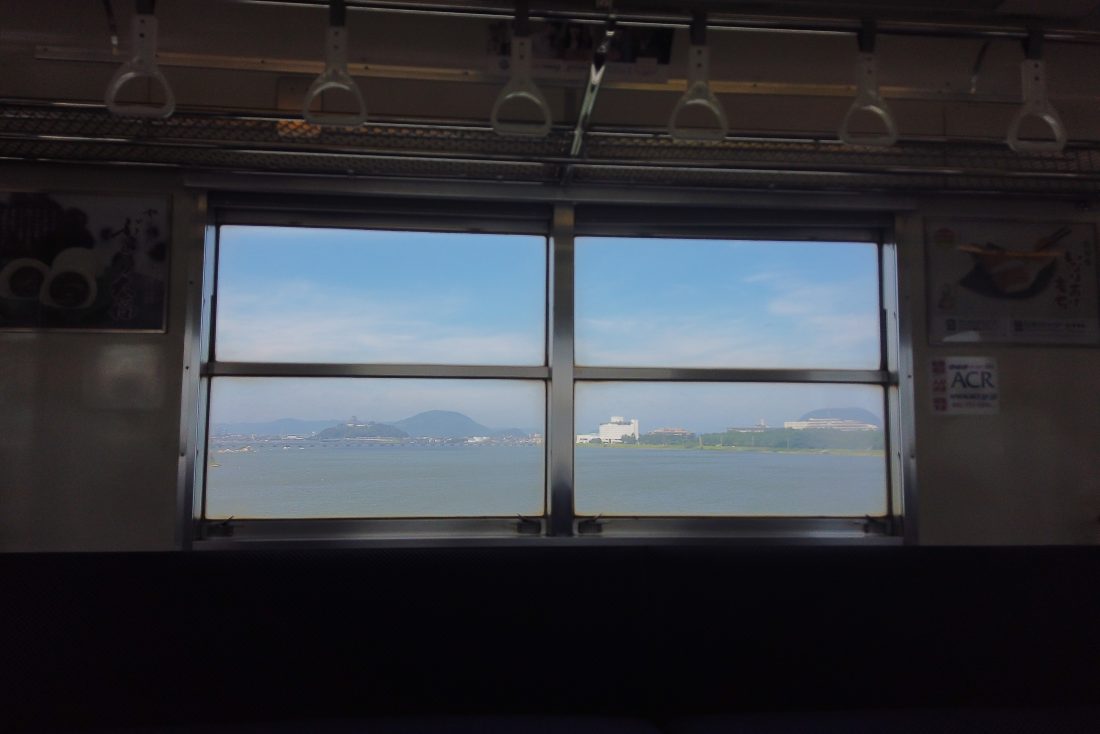





























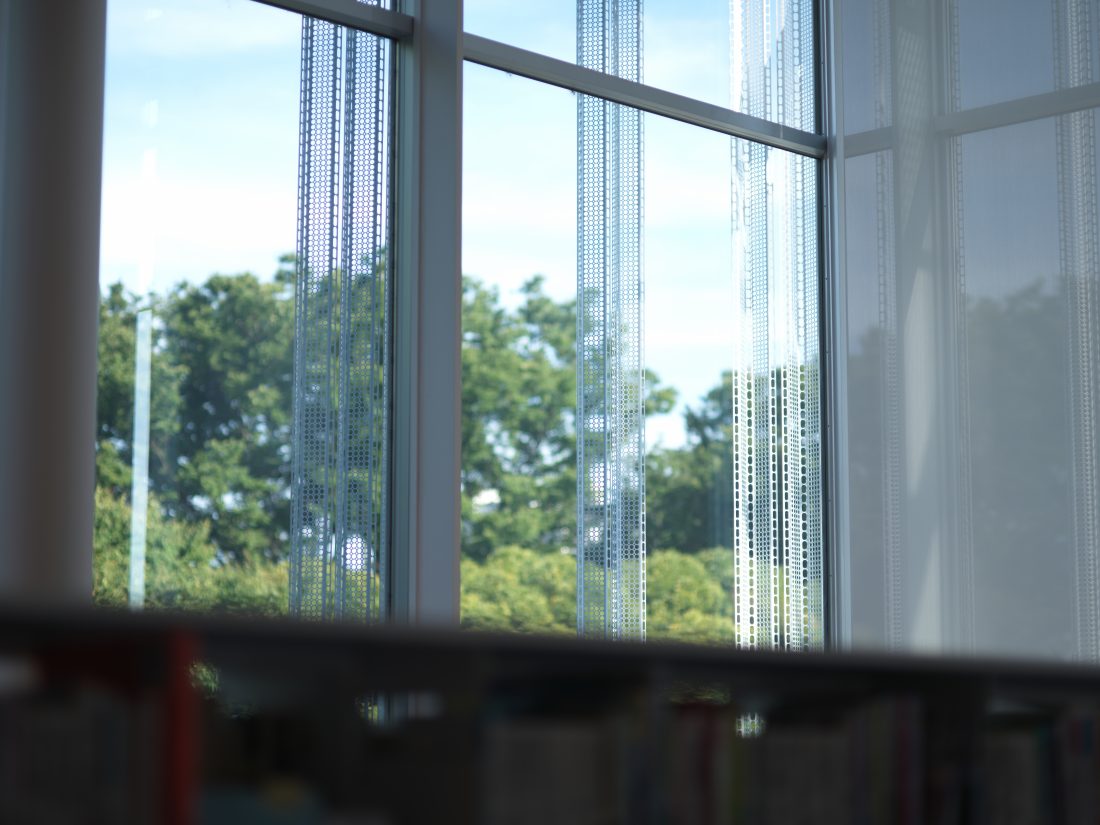













 専らデジタル派であった筆者がフィルムカメラを使用したのはつい最近のことになります。
専らデジタル派であった筆者がフィルムカメラを使用したのはつい最近のことになります。
 どのシーンを撮影してもフィルムの色合いとマッチしているなと感じました。
どのシーンを撮影してもフィルムの色合いとマッチしているなと感じました。 雨上がりの公園での1枚。降り注ぐ光と雨の水滴の対比がお気に入りです。
雨上がりの公園での1枚。降り注ぐ光と雨の水滴の対比がお気に入りです。
 Nikon F3は、Nikonのフィルムカメラの最上位機種「F一桁」機のひとつです。
Nikon F3は、Nikonのフィルムカメラの最上位機種「F一桁」機のひとつです。 F3には、絞り優先の自動露出機能が搭載されています。
F3には、絞り優先の自動露出機能が搭載されています。 壁に映っている葉の影が幻想的です。
壁に映っている葉の影が幻想的です。
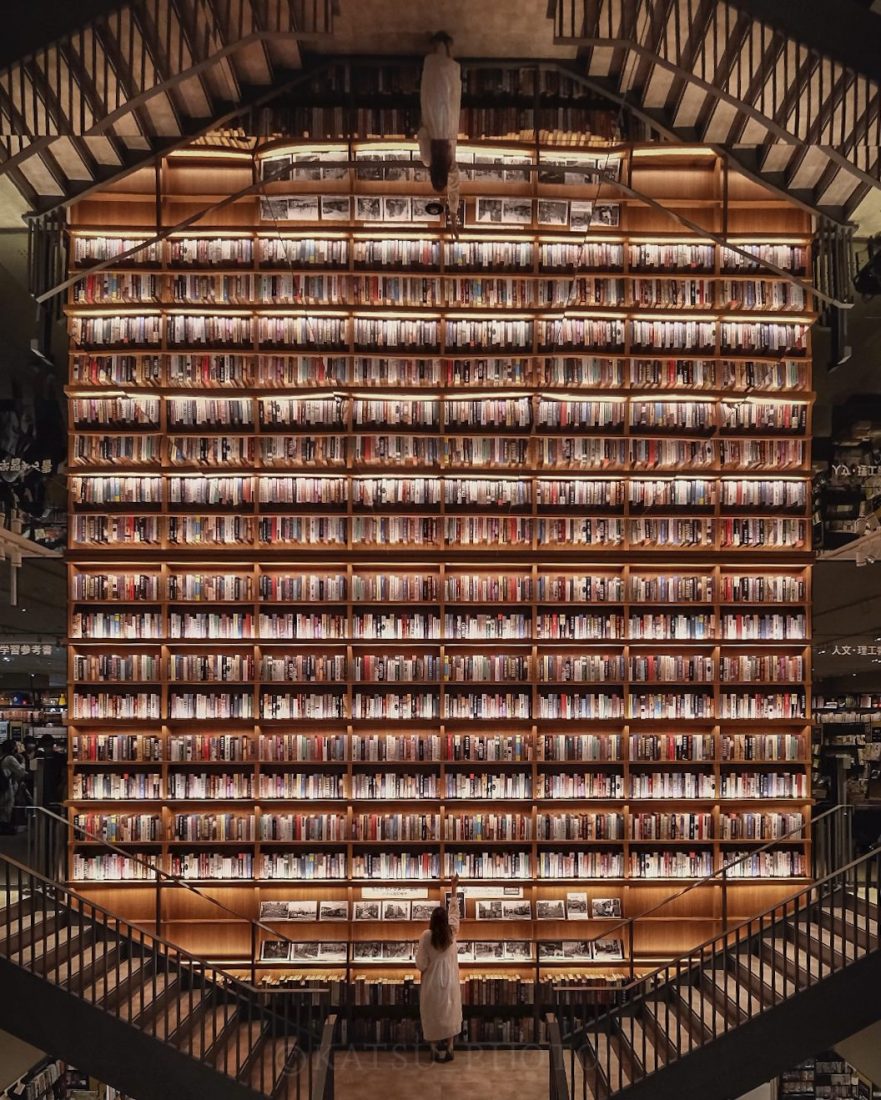








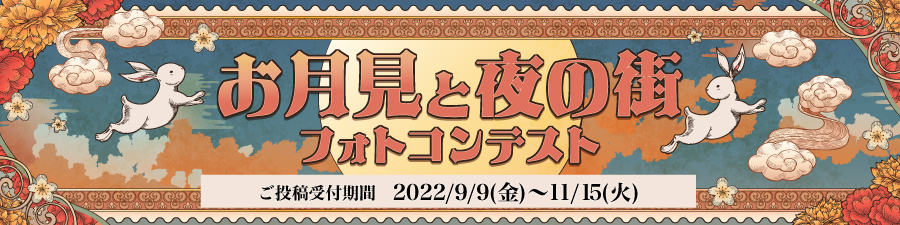

















 Rolleiflex 3.5E2(Schneider-Kreuznach Xenotar75mmF3.5)以下、同じ。
Rolleiflex 3.5E2(Schneider-Kreuznach Xenotar75mmF3.5)以下、同じ。 公園の様子はというと、こんな感じ。結構賑わっていました。
公園の様子はというと、こんな感じ。結構賑わっていました。 高画素デジタルには遠く及びませんが、それでも中判フォーマット。細かなところまでよく写っています。
高画素デジタルには遠く及びませんが、それでも中判フォーマット。細かなところまでよく写っています。 とにかくさまざまな飛行機が、山手線と同じくらいの間隔で飛んでくるのですから見ていて飽きませんでした。
とにかくさまざまな飛行機が、山手線と同じくらいの間隔で飛んでくるのですから見ていて飽きませんでした。 今度来るときは、絶対ビール持ってこよう…
今度来るときは、絶対ビール持ってこよう… Rolleiflex 3.5E2(Schneider-Kreuznach Xenotar75mmF3.5)ローライナー 2 使用
Rolleiflex 3.5E2(Schneider-Kreuznach Xenotar75mmF3.5)ローライナー 2 使用 葉の隙間から入る光が五角形になっているのが分かります。絞り羽根の枚数が少なく絞るときれいな五角形に、それが光源ボケとして出ています。
葉の隙間から入る光が五角形になっているのが分かります。絞り羽根の枚数が少なく絞るときれいな五角形に、それが光源ボケとして出ています。 ローライのボケは決してきれいとは言えません。ちょっとざわざわしたボケに、でもそれがオールドレンズらしい味わいとなっています。
ローライのボケは決してきれいとは言えません。ちょっとざわざわしたボケに、でもそれがオールドレンズらしい味わいとなっています。 ローライナー 1 使用
ローライナー 1 使用 最近、あえて前に大きなボケを持ってくることをしています。バックのボケと異なり滑らかなボケ味で、ピント合焦面の鮮鋭さを際立たせてくれます。
最近、あえて前に大きなボケを持ってくることをしています。バックのボケと異なり滑らかなボケ味で、ピント合焦面の鮮鋭さを際立たせてくれます。 ローライナー 1 使用
ローライナー 1 使用




































































